「つ」に関係する名詞
「つ」に関係する名詞の一覧を表示しています。 検索結果が多い場合は文字数で絞ることが可能です。| 61件目から90件目を表示 | < 前の30件 | | | 次の30件 > |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([学]Vaccinium praestans)ツツジ目(Ericales)ツツジ科(Ericaceae)スノキ属(Vaccinium)(コケモモ属)の落葉低木。
本州中部以北の高山帯に広く分布し、高さは5~15センチ。長い地下茎を伸ばし、所々に茎を立てながら繁殖する。 夏に小さな淡紅色の鐘状花を2、3個つける。果実は球形で紅熟し、甘酸っぱく食用になる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([朝]gun)朝鮮(韓国・北朝鮮)の行政区画単位の一つ。
道(do)の下位、面(myon)の上位。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([英]arteriosclerosis)動脈の血管壁(ケッカンヘキ)が硬(カタ)くなって弾力を失い、もろくなること。また、その状態。
老化現象の一つと言われるが、促進物質の過酸化脂質などが血管内に蓄積(チクセキ)して起こる。 慢性化すると動脈硬化症になる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([英]cabinet)日本の国家行政を担当する最高機関。
首長たる内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織する合議体。 国務の総理(事務の統一・管理)、法律の執行、外交関係の処理、条約の締結、予算の作成、政令の制定、大赦特赦の決定、また天皇の国事行為について助言と承認を行うなど多くの重要な職務権限をもつ。 内閣は閣議による意思決定にもとづいて行政権を行使し、国会に対して連帯してその責任を負う。 衆議院で不信任決議案が可決され、または信任決議案が否決されたときは、10日以内に衆議院を解散するか総辞職をしなければならない。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([英]crupper)馬具の一つ。三繋(サンガイ)の一つ。
馬の尾の下から後輪(シズワ)の四方手(シオデ)に繋(ツナ)ぐ組紐(クミヒモ)または革緒(カワオ)の装具。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([英]Five Duties)イスラム教徒(ムスリム)に義務付けられた五つの勤行(ゴンギョウ)。
「五柱([英]Five Pillars)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([英]grafting)植物、特に草木の枝・茎・芽などを切り取り、根をもつ他の個体の幹(ミキ)・茎に接ぎ、活着(カッチャク)させて殖(フ)やす方法。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([英]modern age)歴史の時代区分の一つ。現代に近い時代。中世(middle age)と現代(contemporary age)との間。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([英]omission)印刷物で、明記をはばかる字の箇所に「空白」または「○(まる)」・「×(ばつ)」などの記号を字の数だけ入れて表すこと。また、その記号。
検閲(ケンエツ)の対応策などとして行われる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([英]polychlorinated triphenyl)ポリ塩化トリフェニールの略称。殺虫剤の一つ。
性状・構造ともPCB(ポリ塩化ビフェニール)に類似した有機塩素化合物で、PCBより毒性が強く、化学公害の一因子として使用禁止。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([英]stepping stone)日本庭園などで、伝い歩く通路として、少しづつ間隔をおいて敷き並べてある平らな石。
擦(ス)り減った石臼を利用することもある。 「ふみいし(踏み石,踏石)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (『孟子』尽心篇上)君子の三つの楽しみ。
家族全員が無事で生きていること、公明正大で心に恥じることがないこと、天下の英才を得てこれを教育すること。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (『法華経』序品)釈迦(シャカ)が法華経を説かれるときに現れた「此土(シド)の六瑞(ロクズイ)」の一つとして空から降ったという四種の蓮華(レンゲ)の花。
<1>白蓮華 :曼荼羅華(マンダラゲ)。 <2>大白蓮華:摩訶(マカ)曼荼羅華。 <3>紅蓮華 :曼珠沙華(マンジュシャゲ)。 <4>大紅蓮華:摩訶曼珠沙華。 「しか(四華,四花)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (なれ合いで)ある一つの物事を順々に他の人や場所に送り回すこと。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (ふざけて言う)相づちの言葉。
相づちを打つ言葉の「なるほど」の「ほど」を「ほぞ(臍)」に掛け、さらに「ほぞ」を「へそ(臍)」に言い換えてできたシャレ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (アメリカで)小さな、狭い。つまらない。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (イスラム教で)断食。五行の一つ。 |
姉妹サイト紹介

| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (イタリア語で)ご主人。
一般に姓の前につけて使用する。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (イタリア語で)ミュール・つっかけ・スリッパ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (イタリア語で、疑問詞の)いつ(何時)。
「クワンド」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (カルタで)点に入らない札。つまらない札。素札(スフダ)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (ゴルフ・ボーリング)ハンディキャップをつけずに行う試合。また、その試合法。
「スクラッチ・マッチ(scratch match)」とも、単に「スクラッチ」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (ドイツ語で)三つ子。
「ドゥリリング」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (ヒツジの腸のように)山道などが幾重にも折れ曲がっていること。また、そのさま。
「つづらおり(葛折,葛折り,九十九折,九十九折り)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (フェンシングで)試合の前と終了時に行う挨拶(アイサツ)。
初めに剣先を下げ、次に腕を曲げて顔面で剣先を上に向ける動作を、対戦相手・主審・観客に対して1度づつ、計3度行うこと。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (フランス語で)旅に出る人へのあいさつ。
「ボンボワイヤージュ」,「ボンボアイヤージュ」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (上流階級の)婦人がくつろぐ私室・衣裳部屋・寝室・閨房(ケイボウ)。
「ブドワール」とも呼ぶ。 |
姉妹サイト紹介
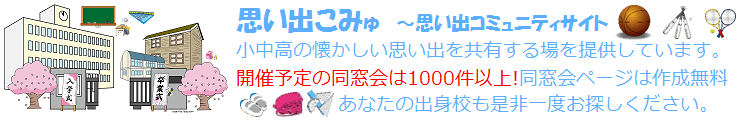
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (中国で)唐末期・五代、節度使が腹心の鎮将を駐屯させた要地。
鎮将は軍政のほか、警察・裁判・徴税などの民政もつかさどった。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (中国・日本で)(1)を原料とした、細長い乾麺(干麺)。
熱湯につけて戻し、焼きそばのように野菜・肉と炒(イタ)めたり、あん掛けにしたり、スープの具にもする。 中国南部・台湾で多く食べられている。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (位相が近く)波動が互いに干渉し合う、可干渉性の、干渉性を持つ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (体言・動詞の連用形について)そのようなふりをして、またはそのことにかこつけて、自分の利益をはかること、を表す語形要素。
「こかし」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (内容がなくて)空虚だ、もの足りない、むなしい、つまらない。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (動詞の連用形について)「激しく……する」を表す語形成要素。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (古代中国および日本の律令法で)妻を離別してはならない三つの場合(条件)。
<1>帰る家のないとき。 <2>舅(シュウト)・姑(シュウトメ)の三年の喪(モ)を務めたとき。 <3>貧乏な夫に嫁してのち富貴になったとき。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (否定構文で”a”をつけて)少しも、ごくわずかも。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (国栖)能の一つ。五番目物。作者未詳。
大友皇子に追われた大海人皇子(オオアマノオウジ)(子方)が供奉(グブ)の者を伴って都から吉野の国栖に遁(ノガ)れる。吉野川の岸にいた漁夫の老夫婦に隠してもらい追っ手の難を逃れる。夫婦は夜更けに消え失せ、やがて天女が、次いで蔵王権現が現われ祝福を受ける。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (大きく目立つ)羽根・羽毛。大羽(オオハネ)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (宝石のついた)垂飾り。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (寺で)かつお節の隠語。
「どっこ」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (後ろめたいなどの)暗い目つき。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (心情などが)あつまる・集中する。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (悪が滅び善が勝つという)天啓・黙示・啓示。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (手で)つかむ・握(ニギ)る。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (日本で)髪を剃って形は僧でも、妻子を養い生業につき、在家(ザイケ)の生活をする者。
「さみ(沙弥)」,「在家の沙弥」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (昔話などに登場する)泥や土で作った船。
初めは水に浮いているが、しだいに溶け出して沈んでしまう。 「つちぶね(土船)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (望ましくなく忌避したいものの場合)たいへんだ、とんでもない、恐ろしい、困った、つらい、情けない、たいへん悲しい、不快だ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (東北・北陸方言で)氷・つらら(氷柱)。
「しが」,「しがこ」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (栄華の最中にも)生命をおびやかす危険が、常に身につきまとうたとえ・状態。
紀元前4世紀ころ、シチリア島シラクサの僭主(センシュ)ディオニシオス一世(BC. 430ころ~BC. 367)は、廷臣ダモクレスがあまりに王位の幸福をたたえすぎたので、王は宴会の時に彼を王座につかせた。 ダモクレスは王位を満喫していたが、ふと見上げると一本の馬の毛でつるされた抜身(ヌキミ)の剣が垂れ下がっているのを見て胆(キモ)をつぶしたという故事。 「ダモクレスの剣(ケン)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (母音の上につける)長音記号。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (江戸時代、新吉原で)あつかましい者・愚かな者を指す隠語。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (物を足で)蹴(ケ)る・蹴り飛ばす・蹴り放つ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)いつも携帯する一組の小道具。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)カメラ・引伸機などの、本体とレンズ取り付け部分とつないでいる、自在に伸縮する蛇腹式の部分。ピント合せや折り畳みなどのための機構。
遮光性と柔軟性のある革・ゴム引きの布などで作られている。 接写撮影や、シフト撮影・チルト撮影も可能。 単に「蛇腹」とも呼ぶ。(ヘリコイド)(2) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)ツムギアリ属(Oecophylla)のアリの属名・総称。
樹上の枝先に葉をそのまま数枚寄せ集めて幼虫の吐き出す糸を使ってつなぎ合せて巣を作る。1つの群れで、その木の別の枝先や隣接する木の枝先などに数個~数十個の巣を作って生活する。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)ヤマノイモの葉のつけ根に生ずるイモのような珠芽。
「ぬかご(零奈子)」とも呼ぶ。薯蕷) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)五節句の一つ、五月五日の節句。
日本では奈良時代に中国から祝う習慣が伝来し、ショウブ(菖蒲)やヨモギ(蓬)を軒に挿して邪気を払い、粽(チマキ)や柏餅(カシワモチ)を食べる風習ができた。 ショウブが「尚武(ショウブ)」に通じることから、江戸時代以後は男子の節句とされ、武家では甲胄(カッチュウ)などを飾り、庭先に幟旗を立てて男子の成長を祝った。次第に町人も武者人形などを飾り、鯉幟(コイノボリ)を立てるようになった。 第二次世界大戦後は「こどもの日」として国民の祝日となった。 「端午の節句」,「端午の節(セチ)」,「あやめ(菖蒲)の節句」,「重五(チョウゴ)」,「端陽(タンヨウ)」,「夏節([中]Xiajie)(カセツ)」とも呼ぶ。龍) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)傷がついて値打ちの下がった商品。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)刀剣を赤熱して水につける。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)原水爆の被害を直接、またはその放射能の被害を受けること。る(第五福竜丸),くろいあめ(黒い雨),なつのはな(夏の花),はだしのげん(はだしのゲン) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)市街地に巻き立つ塵。
「巷塵(コウジン)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)損得についての計算。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)日光の輪王寺薬師堂の天井に描かれた鳴竜。
真下で両手を「パン」と打つと、「バァーン、ワァン、ワァン」と鳴り響き、あたかも絵の竜が鳴いているように聞こえる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)江戸時代の会津藩の藩校。
日本三大藩校の一つ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)祝い事などを行うのによい日。めでたい日。
「きちにち(吉日)」,「きつじつ(吉日)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)絞首刑の際、首に縄をかけられた死刑囚が立つ踏み板。約1.1メートル四方。
執行時に足元の板が開き、約4メートル下の階下部分に落ちて死刑囚の体重で縄が締まる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)見当をつけた所。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)那智山にある一つの滝の名。日本三名瀑一つ。落差133メートル。
飛滝神社(飛瀧神社)の神体で、古くから修験道の道場。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)音波が大気中を伝わる速度。
セ氏0度1気圧で毎秒331.45メートル。 温度が1度上がるごとに毎秒0.61メートルづつ増し、15度では毎秒約340メートル。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に浄土門で)阿弥陀仏(アミダ・ニョライ)を念ずる人の臨終(リンジュウ)(死)に来迎(ライゴウ)し、死者を極楽浄土に導き、弥陀の光の中に摂(オサ)め取ること。
「いんせつ(引接)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (状態・信念などを)保つ・維持する。 |
| 言葉 | (1)孔席暖まらず墨突黔まず | 詳しく調べる |
|---|---|
| 意味 | (班固『答賓戯<トウヒンギ>』)孔子と墨子の二人は、道を天下に広めるために家に落ちついていなかったから、孔子の座席は暖まることなく、また墨子の家の煙突は炊事の煙りで黒くなることがなかったという故事。
「孔席暖まるに暇(イトマ)あらず」,「墨突黔まず」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (白く泡立つ)瀑布(バクフ)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (相手の)杯(サカズキ)に酒をつぐこと。 ・ |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (神社・仏閣を)つくりかえること。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (聖堂・教会堂などと独立した)鐘(campana)をつるす塔。鐘塔(ショウトウ)・鐘楼(ショウロウ)。
「カンパニレ」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (英語で)かつら(鬘)。
「ウィッグ」,「ヘアウイッグ(hair wig)」,「ヘアウィッグ」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (表装で)ふつうの寸法に比べて丈がつまった中途半端な軸物など。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)ある人や物事を忌み嫌って寄せつけないこと。
「七里けっぱい」,「七里けんばい」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)いつもあること。また、いつもあるもの。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)うやうやしくつつしむさま。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)ちょっと外出しただけでも、つまらない出費があるということ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)つまらない、単純で低級なダジャレ。 |
| 言葉 | (1)ギブ・アンド・テーク | 詳しく調べる |
|---|---|
| 意味 | (転じて)なれあい・もちつもたれつの歩み寄り。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)ひつぎ(棺)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)一度してしまったことはも取り返しがつかないということ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)中身の悪さを隠して、外面だけを飾り、とりつくろうこと・中身をいつわること。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)別れた夫婦、特に妻から求めて家を出た夫婦は復縁することができないということ。が付く,焼け木杭に火が付く,焼木杭に火が付く)かえだにかえらず(落花枝に返らず)(3),そうこうのつま(糟糠の妻) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)双方が同じような事を繰り返し、いつまでも埒(ラチ)のあかないこと。きりがないこと・無駄なこと。
一種の悪循環。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)命がけで物事をすること、全力をつくしてがんばること。また、そのさま。
転化して「一生懸命(イッショウケンメイ)」とも、略して「懸命」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)宴席で一品づつ膳にのせて出される高級な日本料理。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)武士・戦士が、戦闘に際して身体を保護するために身につける防護服。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)物事の橋渡し・てびき・つて・たより。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)男女の仲をとりもつ人。仲人(ナコウド)。
「氷人」と合せて「月下氷人」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)真夜中・深夜。
「うしみつどき(丑三つ時,丑三時)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)級位ほもつ者の別称。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)見込む所・見込んだ所。図星(ズボシ)。
強調して「どつぼ(ドツボ,土壺)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (遊郭などで)当座の祝儀(シュウギ)として渡される紙纏頭(カミバナ)。
本来は、後日に現金を与える印(シルシ)であるが、そのつもりのないもの。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (鎖状につないだ)ヒナギク(雛菊)の花輪。
「デイジーチェイン」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (関東地方、特に鎌倉で)丘や小山の低く窪(クボ)んだ小さな谷・窪地(クボチ)。
奥まったところは斜面から湧き水が流れ出していて湿地になっている場合が多い。 「やつ(谷)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (革などに打つ)鋲(ビョウ)・飾り鋲。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | +2/3の電荷と電子の607倍の質量を持つ安定したクォーク |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | -1/3の電荷を持つクォークで、質量は電子の約1万倍 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 10の辺と10の角をもつ多角形 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 10人以下の単位(ユニット)を組み、福祉施設などでケアを行なう方式のこと6~9人を1ユニット(生活単位)とする家庭的な環境のなかで一人ひとりの個性や生活リズムに応じて暮らしていけるようにサポートする介護手法のこと。個室(寝室)があり、日中は共有のリビングで過ごす。いつも同じ顔ぶれで環境の変化が少ないことから、認知症グループホームの多くが採用している。特別養護老人ホームや老人保健施設、療養病床などで、10人以下のグループに分けてケアを行なう方式。特別養護老人ホームなどの高齢者施設の居室をいくつかのグループ(10人前後)に分けて、それぞれをひとつの生活単位とし、少人数の家庭的な雰囲気の中でケアを行うもの。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 11世紀のイングランド南中部の都市コベントリー(Coventry)の仕立屋。
領主が重税を課した時、ゴダイバ夫人(Lady Godiva)がやめるように説得すると、領主は冗談半分に夫人が裸で白馬に乗って町中を通ったらやめると言った。 夫人は町民に戸や窓を閉めるように頼んで夫の要求を実行すると、トムだけが夫人の姿をこっそりのぞき見して目がつぶれたという。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1258年イランに建国されたモンゴルの王国。
ジンギス汗の孫で、フビライの弟フラグ(Hulagu)(旭烈兀)がアッバス朝のカリフ政権を倒し、カスピ海南西のタブリースに都して建てた。モンゴル帝国の4汗国のうち、最も元朝に友好的であった。 シリアの領有をめぐってエジプトのイスラム帝国マムルーク朝と争ったので、初めイスラム教に反対しネストリウス派のキリスト教を支持して、ローマ教皇やキリスト教国に接近した。 しかし、13世紀末に即位した第7代ガザーン・ハンはイスラム教を国教と定め、文化の興隆につとめた。宰相ラシード・ウッディンのモンゴル族の歴史『集史』も編纂された。 14世紀になるとハン位争奪の内乱も起って衰退し、1393年ティムールの攻撃を受けたのち分裂して1411年滅亡した。 「イル・カン国(イル汗国,伊児汗国)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 12の正五角形の面をもつ十二面体 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1311年−1313年の議会で、テンプル騎士団員の犯罪について申し立て、新しい改革運動を計画し、聖職者の改革を起こした |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 13世紀初頭から16世紀前半にかけて、北インドのデリーを中心として続いた五つのイスラム王朝の総称。
<1>トルコ系の奴隷王朝(Slave Dynasty)(1206~1290)。 <2>ハルジー朝(Khalji Dynasty)(1290~1320)。 <3>トゥグルク朝(Tughluq Dynasty)(1320~1413)。ちょう(サイイド朝) <5>アフガン系のロディー朝(Lodi Dynasty)(1451~1526)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 13歳以上の男女に対して暴行・脅迫をもってわいせつな行為をする罪。
親告罪で、量刑は6ヶ月以上7年以下の懲役刑のみで、罰金刑の規定はない。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 14世紀の約70年間(7代)、ローマ教皇庁がフランス国王支配下のアビニョンに移された事件。
シエナの聖女カタリナ(Catharina de Siena)の尽力により、1377(<南>天授 3,<北>永和 3)教皇グレゴリウス九世(Gregori-us IX)がローマに帰還。 「アヴィニョンの捕囚」,「アビニョンの幽囚」,「教皇のバビロンの捕囚」,「教皇のバビロン捕囚」とも呼ぶ。(カタリナ),きょうかいだいぶんれつ(教会大分裂) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1545~1546(天文14~15)武蔵国河越で行われた後北条氏と上杉氏の合戦。
1537(天文 6)扇谷(オウギガヤツ)上杉朝定(トモサダ)は北条氏綱・氏康(ウジヤス)父子に本拠河越城を攻め落とされ、松山城に退く。1541(天文10)氏綱が没し、扇谷上杉朝政が攻めるが敗退。 勢力の回復をはかる朝定は山内上杉憲政(ノリマサ)(関東管領)・足利晴氏(ハルウジ)(古河公方)の援けを得て、1545(天文14.10.)福島(北条)綱成が守る3千の河越城を総勢8万余騎の大軍で包囲する。 翌年春、氏康が今川氏親と争っているのに乗じて朝定らは兵糧の尽きた落城寸前の川越城を攻める。氏康は8千騎を率いて援軍に駆けつけ、 4.20夜陰に乗じて襲撃し、城兵も降参を装って夜襲(河越の夜討)。 上杉・足利の連合軍は敗走し、混乱の中で朝定は戦死して、扇谷上杉は滅んだ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 15世紀にアルプスに住む修道僧が考えたといわれる外側に大きなバックルのついた靴。靴ひもでは無く、ベルトとバックルで甲の高さを調節できる機能的なデザインが特徴。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 15~18世紀、スペインなど西ヨーロッパ諸国で軍船・貿易船として用いられた典型的な外航用帆船。
3~4層の甲板を持つ大型帆船で、大航海時代に活躍した。 「ガリアン船」,「ガレオン船」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1651(慶安 4)発覚した由井正雪(ユイ・ショウセツ)・丸橋忠弥(マルバシ・チュウヤ)・河原十兵衛らによる江戸幕府の転覆を企てた事件。
1651(慶安 4. 4.20)第3代将軍徳川家光が没した時勢に乗じ、時勢に不満をもつ浪人を糾合して、江戸・駿府・京都・大坂で挙兵し、幕府転覆を企てたもの。 7月23日一味に加わっていた奥村八左衛門とその徒弟幸忠が訴え出たり、御弓師藤四郎が訴え出たりして未然に発覚。 江戸では丸橋忠弥らが、町奉行総動員による石谷貞清(イシガヤ・サダキヨ)・神尾(カンオ)元勝らに捕えられ、8月23日鈴ヶ森で磔刑にされる。 駿府に向かっていた由井正雪は、追討を命ぜられた新番組・駒井右京親昌(チカマサ)に駿府茶町の旅籠梅屋で包囲されて自害。 「慶安の変」,「慶安事件」,「由井正雪の乱」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | (1)シャクシャインの戦い | 詳しく調べる |
|---|---|
| 意味 | 1669(寛文 9)蝦夷地(エゾチ)(現:北海道)のアイヌ人が、交易独占を強化する松前藩の支配と収奪に抵抗して起した蜂起(ホウキ)。
東蝦夷地に拠点を持つアイヌ人首長シャクシャインが、東西両蝦夷地のアイヌ人に反和人・反松前藩の檄(ゲキ)をとばし、東は白糠(シラヌカ)から西は増毛(マシケ)までアイヌ人が一斉(イッセイ)に蜂起。蝦夷各地で商船などを襲い、商船の船頭や鷹待(タカマチ)(鷹匠)など日本人(和人)約390を殺害。 徳川幕府は松前氏の一族松前泰広(旗本)や津軽弘前藩に出兵を命じた。 アイヌ側は松前藩への襲撃も企てたが、国縫(クンヌイ)で防ぎ止められた。同年十月になって松前藩の和睦(ワボク)を装う奸計(カンケイ)にあってシャクシャインは殺害。1671(寛文11)までに蜂起は完全に鎮圧(チンアツ)された。 「シャクシャインの乱(沙牟奢允の乱)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1697年刊行のシャルル・ペロー(Charles Perrault)作『童話集』の一編。また、その主人公のあだ名。
主人公ウラル(Chevalier Raoul)は残忍無情な男で、次々に6人の妻を殺し、7人目の妻ファティマ(Fatima)を殺そうとするが、駆けつけた彼女の兄に殺される。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 16~17世紀以降のヨーロッパで、竜の飾りをつけたカブト(兜)を被(カブ)り、銃を持った騎馬兵。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1707.10.28(宝永 4.10. 4)北緯33.3°・東経135.9°を震源とする、推定マグニチュード8.4の大地震。
東海道から中国・九州におよぶ被害が出、死者約4.900人。 遠州灘沖と紀伊半島沖の二つの地震とも考えられている。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 17世紀から18世紀に流行した男性のためのかつら |
| 言葉 | (1)ウェストファリア公国 | 詳しく調べる |
|---|---|
| 意味 | 1809(文化 6)ティルジット条約によりナポレオン一世が建国した公国の一つ。ナポレオンの末弟ジェローム(Jerome)が君主となる。
エルベ川以西の前プロイセン領に建設、1814(文化11)ウィーン会議により消滅。わこうこく(ワルシャワ公国) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1868(慶応 4. 5.)戊辰戦争に際して、奥羽・北越の諸藩の間で新政府(官軍)に対抗するため結ばれた軍事同盟。
1868(慶応 4. 4.11)江戸開城後、会津藩・鶴岡藩ら幕末期に佐幕活動を行っていた諸藩の藩主はそれぞれ藩地に戻って謹慎していたが、3月に仙台に入っていた官軍側の奥羽鎮撫総督九条道孝・総督府参謀大山綱良(ツナヨシ)・同参謀世良修蔵らは会津藩・庄内藩の追討を目指し仙台藩・米沢藩らに討伐を命じる。 仙台藩・米沢藩が中心となって二本松藩など14藩の重臣が仙台藩白石城(シロイシジョウ)に集まり、官軍側に徳川慶喜(ヨシノブ)の寛大な処分と会津藩・庄内藩の赦免を嘆願したが拒否され、処分強硬派とされる世良修蔵を暗殺。5月31日奥羽25藩の重臣が再び白石城に集まり、会津征討中止の建白書を作成して連合、君側(クンソク)の奸(カン)である薩長軍(官軍)を討つとした奥羽列藩同盟が成立。さらに会津藩と盟約を結んでいた北越の長岡藩・新発田藩(シバタハン)ら6藩がこれに参加し31藩となり奥羽越列藩同盟が成立。 当初は仙台藩主を盟主に、のち1868. 7. 4(慶応 4. 5.15)の彰義隊戦争で敗れ北走した輪王寺宮(リンノウジノミヤ)公現(コウゲン)法親王(のち北白川宮能久<ヨシヒサ>親王)を推戴し、参謀には旧幕臣の小笠原長行(ナガミチ)らが入り、白石城に公議府、福島に軍事府を設置。 洋式軍備に優(マサ)っていた官軍が白河口・越後口から進攻すると秋田藩などが官軍側に協力をはじめ、7月に長岡藩が敗北して北陸が鎮定(北越戦争)し、白河・棚倉・二本松が攻略されると脱落する藩が相次ぎ、米沢藩・仙台藩も降伏し会津落城を前に同盟は自然瓦解。 9月22日会津藩が降伏し(会津戦争)、官軍により平定された。よし(大山 綱良) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1868(慶応 4.閏4.)古代官制にならって政体書(セイタイショ)により設置された中央官庁の総称。
議政官・神祇官・行政官・会計官・軍務官・外国官・刑法官の七つ。 1869(明治 2. 7.)官制の改革により2官6省(神祇官・太政官・大蔵省・兵部省・外務省・民部省・刑部省・宮内省)に改編。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1882. 7.(明治15)「高宗19」朝鮮の首都漢城(ソウル)で起きた軍人たちの暴動。
親日的な開化派の閔妃(ビンビ)政権の軍制改革に反対して、旧式軍制の軍人が起こしたもので、日本人の軍人教官を殺害。官庁や王宮(昌徳宮)を襲撃し、さらに漢城の日本公使館を焼き打ちする事件に発展。暴動に乗じた大院君(タイインクン)が王宮に迎えられ、閔妃は忠清北道忠州に逃れた。 日本は軍艦3隻と3,000人の兵を仁川に、アメリカも軍艦を派遣。清国は宗主国として属邦の保護を名目に軍艦3隻と4,500人の兵を派遣。清国軍により鎮圧、大院君を捕らえ河北省(He-bei Sheng)(カホクショウ)保定府に拉致(ラチ)幽閉、閔妃政権が復活した。 この結果、同年八月に済物浦(サイモッポ)条約が締結された。清国はそのまま漢城に軍を駐留。袁世凱(エン・セイガイ)を駐紮(チュウサツ)朝鮮総理交渉通商時宜として駐在させ事実上の国王代理として実権を握り朝鮮支配を強化した。 「壬午事変」,「壬午軍乱(ジンゴグンラン)([朝]Imogunran)」とも呼ぶ。(甲申の変),かんろみつやくじけん(韓露密約事件) |
| 言葉 | (1)ジキル博士とハイド氏 | 詳しく調べる |
|---|---|
| 意味 | 1886(明治19)刊行された、スチーブンソン(R.L.Steven-son)の怪奇小説。
温厚なジキル博士が、発明した薬によって悪の人格を持つハイド氏に変身し解毒剤で博士に戻り、自由に善悪二重の人格を使い分けるが、悪の力には勝てずに元に戻れなくなり悲惨な最期を遂げる話。 のち「ジキルとハイド(Jekyll and Hyde)」は二重人格者の代名詞となった。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 18世紀、19世紀末~20世紀初頭に着用されていたコート。後に昼の正礼装で着用された。ダブル前、4つまたは6つボタン、膝丈が特徴。結婚式でよく着られる。現在ではあまり着用されず、モーニングコートの方が一般的。英国では「フロックコート」だが、英国のエドワード皇太子(1816~1861)が米国訪れた際着用したことから米国では「プリンス・アルバート」と呼ばれている。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 18世紀初期、オーストリア継承戦争中のイギリスとフランスの植民地闘争の一つ(1702~1713)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1917年11月のレーニン支配下のボリシェヴィキによるクーデターで、1922年にボリシェヴィキの勝利に終わった内戦時代へとつながった |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1920(大正 9)アメリカの女性教育者パーカースト(Helen Parkhurst)(1887~1959)がマサチューセッツ州ドルトン市のハイスクールで試みた新しい教育方法。
基本教科ごとに実験室を設け、生徒は自分の興味と能力に応じて自分で学習目標を定めて個別学習を進めてゆくもの。教師は個人指導を重んじ、助言・相談の役をつとめ、生徒の能力によって進級させる。 「ダルトン・プラン」,「ドルトン・ラボラトリ・プラン(Dal-ton laboratory plan)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1925. 4.22(大正14)公布された思想・結社の弾圧法規。
国体の変革・私有財産制度の否認を目的とする結社活動および個人的行為に対する処罰を内容とする法律。〈制定〉 第一次世界大戦後の社会主義運動・農民運動・労働運動の発展に対処し、反体制運動(主として共産主義運動)の弾圧を目的に制定。 第1次加藤高明内閣(護憲三派内閣)が立案し、1925. 3.(大正14)普通選挙法と同時に制定・公布。「国体ヲ変革シ、私有財産制度ヲ否認セントスル」結社・運動を厳禁し、違反者には懲役10年以下の刑を科した。〈改訂など〉 田中義一内閣は改正案の議会承認を経ずに緊急勅令のかたちで1928. 6.29(昭和 3)改正を公布、即日施行。同年の三・一五事件で日本共産党に対する大量検挙に従い、刑をきびしくするように改訂され、死刑が付加された。 1936. 5.29(昭和11)思想犯保護観察法、公布。 1941. 3.10(昭和16)予防拘禁が追加された改正治安維持法が公布。反政府・反軍部に拡大解釈されて適用された。ぼうこうきん(予防拘禁),とくべつこうとうけいさつ(特別高等警察)〈廃止〉 GHQの司令により、1945.10.15(昭和20)勅令575号が公布施行されて廃止。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1925. 5.30(大正14)中国上海(シャンハイ)で起った反帝国主義の民族運動。
同年2月日本人が経営する上海の紡績工場で中国人労働者の労働争議が起き、ついに内外綿工場の争議で死傷者が出た。日本人の工場で始まったにもかかわらず、イギリス人署長が発砲命令を出したことから、 5.30これに抗議する学生の游行隊が共同租界に入りイギリス官憲と衝突、英仏陸戦隊が発砲して多数の死傷者が出た。 この事件を発端として各地に波及し、上海のみならず漢口・南京・天津など各地で反帝運動が行われた。 特に広東・香港の場合は「沙面事件(Shamian Shijian)」と呼ばれ、対英ゼネストに発展、同年6月から16ヶ月間にわたり外国人に対する食料・水道の供給を絶ち、中国人の使用を禁止した。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1930年代に各国で開発・製造され第二次世界大戦まで使用された、キャタピラを持つ小型の戦闘車両。
装備は機銃程度で、偵察や歩兵の支援を目的として開発された。 トラクターを改造したイギリス軍のカーデン・ロイドVI(Carden Loyd VI)に始り、旧日本軍の九二式軽装甲車・九四式・九七式、イタリア軍のCV29(Carro Veloce 29)・CV33・CV35、ポーランドのTK-3、チェコスロバキアのスコダ(Skoda)などが製造された。 既存の工場で製造が可能なことから各国で一時期ブームとなったが、次第に機動性のあるタイヤを持つ装甲車両に取って換わられ、製造されたものも牽引車両として使用されるにとどまった。 「豆戦車」,「豆タンク」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1933. 6. 7(昭和 8)大阪天六(現:北区天神橋6丁目)交差点で巡査が、信号無視の兵士をとがめた事件。
皇軍の威信を傷つけられたとする軍(大阪八連隊)と、当然の職務とする警察の対立に発展。府警トップの粟屋仙吉はクリスチャンで、納得できないことには譲歩しなかった。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1941年12月、当島は数百の米軍船舶が勇壮かつ死力を尽くす攻防を繰り広げたが、日本軍が占領した |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1946. 4.30(昭和21)結成された財界人の団体。会員資格は個人。
発足当時、経済政策や社会制度について提言を行なう資本家団体として注目される。 歴代代表幹事:初代諸井貫一・木川田一隆。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1953(昭和28)から翌年にかけての政府・与党自由党に対する海運・造船業界の贈収賄をめぐる疑獄事件。
1954. 2.23(昭和29)衆議院は自由党副幹事長の有田二郎の汚職容疑による逮捕許諾請求を期限付で許諾。つづいて衆議院・参議院で4議員の逮捕が許諾され、自由党政治家が取り調べを受けたが、第五次吉田茂内閣の犬養健法務大臣は 4.21検事総長に対し指揮権を発動。自由党幹事長佐藤栄作ら党幹部に対する逮捕要求が阻まれ、捜査は打ち切られて事件の真相は解明されずに終った。 4.22犬養は法務大臣を辞職し、吉田内閣から民心が離れていった。 |
| 61件目から90件目を表示 | < 前の30件 | | | 次の30件 > |