"十"がつく4文字の言葉
"十"がつく4文字の言葉の一覧を表示しています。 検索結果が多い場合は文字数で絞ることが可能です。 文字数は検索結果となる文字の文字数のボタンを押してください。| 1件目から30件目を表示 | 次の30件 > |
| 言葉 | 七十二候 |
|---|---|
| 読み | しちじゅうにこう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)俳諧で、七十二句から成る連句の形式。
懐紙3枚に、表八句裏十四句、二の表・二の裏・名残の表各十四句、名残の裏八句、計七十二句を書き連(ツラ)ねる。
(2)陰暦で、自然現象に基づいて一年を72に区分したもの。 五日を一候とし、初候・二候・三候の三候を一気とし、二気(六候)を一ヶ月とし、二十四気すなわち一年間を七十二分して、季候の変化を示す。
| 言葉 | 三十三身 |
|---|---|
| 読み | さんじゅうさんしん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)『法華経(ホケキョウ』普門品に説かれる、観世音(カンゼオン)菩薩(ボサツ)が衆生(シュジョウ)の教化(キョウケ)のため現れる三十三種の変化身(ヘンゲシン)の総称。
三聖身(サンショウシン)・六天身(ロクテンシン)・五人身(ゴニンシン)・四部衆身(シブシュウシン)・四婦女身(シブニョシン)・二童身(ニドウシン)・八部身(ハチブシン)・執金剛身(シュウコンゴウジン)の総称。
観世音菩薩は普現色身(フゲンシキシン)三昧力(ザンマイリキ)によって変現自在にその姿を変え、衆生の機根(キコン)に即して出現し、それぞれに応じた仕方で法を説くという。
「さんじゅうさんじん(三十三身)」とも呼ぶ。
| 言葉 | 三十二相 |
|---|---|
| 読み | さんじゅうにそう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)仏・如来の三十二の優れた身体的な特徴。釈尊を神格化した姿・形。〈『大智度論(巻四)』〉
< 1>足下安平立相(ソクゲアンピョウリュウソウ)。
< 2>足下二輪相(ソクゲニリンソウ)。
< 3>長指相(チョウシソウ)。
< 4>足跟広平相(ソクゲンコウビョウソウ)。
< 5>手足指縵網相(シュソクマンモウソウ)。
< 6>手足柔軟相(シュソクニュウナンソウ)。
< 7>足趺高満相(ソクフコウマンソウ)。
< 8>伊泥延(「足」偏+「專」)相(イデイエンセンソウ)。
< 9>正立手摩膝相(ショウリュウシュマシッソウ)。
<11>身広長等相(シンコウチョウトウソウ)。
<12>毛上向相(モウジョウコウソウ)。
<13>一一孔一毛相(イチイチクイチモウソウ)。
<14>金色相(コンジキソウ)。
<15>丈光相(ジョウコウソウ)。
<16>細薄皮相(サイハクヒソウ)。
<17>七処隆満相(シチショリュウマンソウ)。
<18>両腋下隆満相(リョウヤクゲリュウマンソウ)。
<19>上身如獅子相(ジョウシンニョシシソウ)。
<20>大直身相(タ゚イジキシンソウ)。
<21>肩円満相(ケンエンマンソウ)。
<22>四十歯相(シジュウシソウ)。
<23>歯斉相(シサイソウ)。
<24>牙白相(ゲバャクソウ)。
<25>獅子頬相(シシキョウソウ)。
<26>味中得上味相(ミチュウトクジョウミソウ)。
<27>大舌相(ダイゼツソウ)。
<28>梵声相(ボンジョウソウ)。
<29>真青眼相(シンショウゲンソウ)。
<30>牛眼瀟睫相(ギュウゴンショウソウ)。
<31>頂髻相(チョウケイソウ)。
<32>白毫相(ビャクゴウソウ)。
(2)(転じて)女性の容貌・容姿に備わるすべての美しさ。
| 言葉 | 三十八社 |
|---|---|
| 読み | さんじゅうはっしゃ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ | 駅 |
(1)福井県福井市にある福井鉄道福武線の駅名。
| 言葉 | 三十六計 |
|---|---|
| 読み | さんじゅうろっけい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 三十四身 |
|---|---|
| 読み | さんじゅうししん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)『法華経(ホケキョウ』妙音品に説かれる、妙音(ミョウオン)菩薩(ボサツ)が衆生(シュジョウ)の経典を説き示すため現れる三十四種の変化身(ヘンゲシン)の総称。
| 言葉 | 三十番神 |
|---|---|
| 読み | さんじゅうばんじん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)本地垂迹説によって、日本国土を一ヶ月三十日間、毎日交替で守護するという三十体の神。
平安初期に天台宗で最澄が法華経を守護する神として祀(マツ)ったのに始まり、平安中期には一般信仰となって流布していた。
鎌倉時代には禁闕守護・仁王経守護・如法経守護・吾国守護など各種の三十番神が生れた。
鎌倉末期、日蓮宗僧日像(ニチゾウ)(1269~1342)により神天上(ジンテンジョウ)法門の一環として日蓮宗に取り入れ、日蓮宗独自の神祇信仰となった。
室町中期には吉田兼倶(カネトモ)により吉田家相伝とされた。
| 言葉 | 不十分さ |
|---|---|
| 読み | ふじゅうぶんさ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)不十分である状態や場合
(2)十分な量や数に欠けていること
(3)the state or an instance of being imperfect
(4)lack of an adequate quantity or number; "the inadequacy of unemployment benefits"
| 言葉 | 不十分に |
|---|---|
| 読み | ふじゅうぶんに |
| 品詞 | 副詞 |
| カテゴリ |
(1)まばらであるか不十分な方法で
(2)不完全でまたは間違った方法で
(3)in an imperfect or faulty way; "The lobe was imperfectly developed"; "Miss Bennet would not play at all amiss if she practiced more"- Jane Austen
(4)in a sparse or scanty way; "a barely furnished room"
| 言葉 | 九十九島 |
|---|---|
| 読み | くじゅうくしま |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)長崎県北部、北松浦郡と佐世保市の西部の海上に散在する島々の総称。
北松浦郡西岸沖は北九十九島、佐世保市西岸沖は南九十九島と呼ばれる。
西海国立公園に含まれる。
(2)長崎県島原市南岸沖、島原湾の島々の総称。
| 言葉 | 九十九折 |
|---|---|
| 読み | つづらおり |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)馬術で、坂道を登るときなどに馬をジグザグに歩かせる乗り方。
(2)馬術で、馬が横歩(ヨコアユ)みするとき、乗り手がこれに逆らわず馬のするまま歩かせる乗り方。
(3)坂道や山道などが幾重にも曲りくねっていること。また、そのさま。 「羊腸(ヨウチョウ)」とも呼ぶ。
| 言葉 | 九十九湾 |
|---|---|
| 読み | つくもわん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)日本海の能登半島東岸、石川県鳳珠郡(ホウスグン)能登町(ノトチョウ)東部にある、富山湾の支湾。溺れ谷。
| 言葉 | 九十九髪 |
|---|---|
| 読み | つくもがみ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 二十の扉 |
|---|---|
| 読み | にじゅうのとびら |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)ラジオのクイズ番組。
| 言葉 | 二十三夜 |
|---|---|
| 読み | にじゅうさんや |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)陰暦二十三日の夜。殊に八月の二十三日の夜。また、その夜に月待ちをすること、その行事。
「二十三夜待(マチ)」,「二十三夜講(コウ)」とも呼ぶ。
| 言葉 | 二十世紀 |
|---|---|
| 読み | にじゅっせいき |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 二十二社 |
|---|---|
| 読み | にじゅうにしゃ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)朝廷の殊遇を受けた、大小神社の首班に列する神社の総称。上七社・中七社・下八社から成る。
国家の重大事・天変地異に際し奉幣使(ホウヘイシ)が立てられた。〈上七社〉
伊勢神社(内宮・外宮)・石清水神社・賀茂神社(下鴨神社・上賀茂神社)・松尾神社・平野神社・稲荷神社・春日神社。〈中七社〉
大原野神社・大神神社(オオミワジンジャ)・石上神社(イソノカミジンジャ)・大和神社(オオヤマトジンジャ)・広瀬神社・竜田神社・住吉神社。〈下八社〉
日吉神社(ヒエジンジャ)・梅宮神社・吉田神社・広田神社・祇園神社(八坂神社)・北野神社・丹生神社(ニウジンジャ)・貴船神社(キブネジンジャ)。
姉妹サイト紹介

| 言葉 | 二十八宿 |
|---|---|
| 読み | にじゅうはっしゅく |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)連句の様式の一つ。
初折(ショオリ)表六句・裏八句、名残(ナゴリ)の表八句・裏六句の二十八句から成る。
(2)日月・惑星・星座などの所在を示すため、黄道(コウドウ)に沿って天球を二十八に区分したもの。
(3)宿曜道(スクヨウドウ)で吉凶を占う法の一つ。
| 言葉 | 二十四軒 |
|---|---|
| 読み | にじゅうよんけん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ | 駅 |
(1)北海道札幌市西区にある札幌市営東西線の駅名。
| 言葉 | 二十日鼠 |
|---|---|
| 読み | はつかねずみ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)細く通常は毛のない尻尾を持つ細長い体に先のとがった鼻と小さな耳を持つ小型のネズミに通常似ている数々の小型のげっ歯類のどれか
(2)any of numerous small rodents typically resembling diminutive rats having pointed snouts and small ears on elongated bodies with slender usually hairless tails
| 言葉 | 二百十日 |
|---|---|
| 読み | にひゃくとおか |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)立春から数えて210日目。9月1日ころ。
| 言葉 | 五十三次 |
|---|---|
| 読み | ごじゅうさんつぎ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)東海道五十三次の略。
| 言葉 | 五十崎町 |
|---|---|
| 読み | いかざきちょう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)愛媛県中央部、喜多郡(キタグン)の町。
| 言葉 | 五十年祭 |
|---|---|
| 読み | |
| 品詞 | 形容詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 五十年祭 |
|---|---|
| 読み | |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 五十里湖 |
|---|---|
| 読み | いかりこ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)栃木県の北西部にある、五十里ダムで男鹿川(オジカガワ)を堰(セ)き止めて造られた人造湖。
堰堤(エンテイ)は重力式のコンクリート・ダムで、高さ112メートル、長さ267メートル。
| 言葉 | 五十鈴川 |
|---|---|
| 読み | いすずがわ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ | 駅 |
(1)三重県伊勢市にある近鉄鳥羽線の駅名。
姉妹サイト紹介
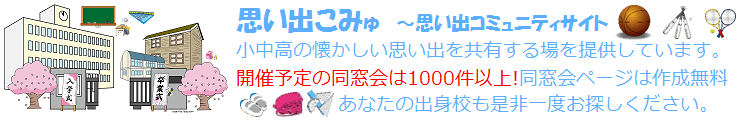
| 言葉 | 五教十宗 |
|---|---|
| 読み | ごきょうじっしゅう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)華厳宗(ケゴンシュウ)で、五教と十宗の総称。
| 言葉 | 五風十雨 |
|---|---|
| 読み | ごふうじゅうう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)天候が順調なこと。
「五日一風十日一雨(ゴジツイップウ・ジュウジツイチウ)」とも呼ぶ。
(2)(転じて)天下が穏やかに治まっていること。天下太平であること。 「五日一風十日一雨」とも呼ぶ。
(3)(転じて)農業に都合のよい気候であること。 「五日一風十日一雨」とも呼ぶ。
| 言葉 | 仏の十号 |
|---|---|
| 読み | ほとけのじゅうごう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)仏(ホトケ)の尊称。つぎの11をいう。
< 1>如来(ニョライ):真如(シンニョ)(真理)から来た人。
< 2>応供(オウグ):供養(クヨウ)を受けるにふさわしい、尊敬される人。
< 3>正遍知(ショウヘンチ):あまねくゆきわたる正しい知慧を具(ソナ)えた人。
< 4>明行足(ミョウギョウソク):明(知慧)と行(実行)が満ち足りている人。
< 5>善逝(ゼンゼイ):迷いを善(ヨ)く逝(サ)った人。
< 6>世間解(セケンゲ):人それぞれの境遇(キョウグウ)を理解している人。
< 7>無上士(ムジョウジ):無上の人格を成就(ジョウジュ)した人。
< 8>調御丈夫(ジョウゴジョウブ):どんな人をも思うままに教え導くことができる人。
< 9>天人師(テンニンシ):天上界・人間界の大導師(ダイドウシ)。
<10>仏(ブツ):仏陀(ブッダ)。覚(サト)った人。
<11>世尊(セソン):世に中で尊重(ソンチョウ)される人。
| 1件目から30件目を表示 | 次の30件 > |