"十"がつく読み方が9文字の言葉
"十"がつく読み方が9文字の言葉の一覧を表示しています。 検索結果が多い場合は文字数で絞ることが可能です。 文字数は検索結果となる文字の文字数のボタンを押してください。| 1件目から30件目を表示 | 次の30件 > |
| 言葉 | 三十三身 |
|---|---|
| 読み | さんじゅうさんしん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)『法華経(ホケキョウ』普門品に説かれる、観世音(カンゼオン)菩薩(ボサツ)が衆生(シュジョウ)の教化(キョウケ)のため現れる三十三種の変化身(ヘンゲシン)の総称。
三聖身(サンショウシン)・六天身(ロクテンシン)・五人身(ゴニンシン)・四部衆身(シブシュウシン)・四婦女身(シブニョシン)・二童身(ニドウシン)・八部身(ハチブシン)・執金剛身(シュウコンゴウジン)の総称。
観世音菩薩は普現色身(フゲンシキシン)三昧力(ザンマイリキ)によって変現自在にその姿を変え、衆生の機根(キコン)に即して出現し、それぞれに応じた仕方で法を説くという。
「さんじゅうさんじん(三十三身)」とも呼ぶ。
| 言葉 | 三十八社 |
|---|---|
| 読み | さんじゅうはっしゃ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ | 駅 |
(1)福井県福井市にある福井鉄道福武線の駅名。
| 言葉 | 三十六計 |
|---|---|
| 読み | さんじゅうろっけい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 三十番神 |
|---|---|
| 読み | さんじゅうばんじん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)本地垂迹説によって、日本国土を一ヶ月三十日間、毎日交替で守護するという三十体の神。
平安初期に天台宗で最澄が法華経を守護する神として祀(マツ)ったのに始まり、平安中期には一般信仰となって流布していた。
鎌倉時代には禁闕守護・仁王経守護・如法経守護・吾国守護など各種の三十番神が生れた。
鎌倉末期、日蓮宗僧日像(ニチゾウ)(1269~1342)により神天上(ジンテンジョウ)法門の一環として日蓮宗に取り入れ、日蓮宗独自の神祇信仰となった。
室町中期には吉田兼倶(カネトモ)により吉田家相伝とされた。
| 言葉 | 二十八宿 |
|---|---|
| 読み | にじゅうはっしゅく |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)連句の様式の一つ。
初折(ショオリ)表六句・裏八句、名残(ナゴリ)の表八句・裏六句の二十八句から成る。
(2)日月・惑星・星座などの所在を示すため、黄道(コウドウ)に沿って天球を二十八に区分したもの。
(3)宿曜道(スクヨウドウ)で吉凶を占う法の一つ。
| 言葉 | 五教十宗 |
|---|---|
| 読み | ごきょうじっしゅう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)華厳宗(ケゴンシュウ)で、五教と十宗の総称。
| 言葉 | 仏の十号 |
|---|---|
| 読み | ほとけのじゅうごう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)仏(ホトケ)の尊称。つぎの11をいう。
< 1>如来(ニョライ):真如(シンニョ)(真理)から来た人。
< 2>応供(オウグ):供養(クヨウ)を受けるにふさわしい、尊敬される人。
< 3>正遍知(ショウヘンチ):あまねくゆきわたる正しい知慧を具(ソナ)えた人。
< 4>明行足(ミョウギョウソク):明(知慧)と行(実行)が満ち足りている人。
< 5>善逝(ゼンゼイ):迷いを善(ヨ)く逝(サ)った人。
< 6>世間解(セケンゲ):人それぞれの境遇(キョウグウ)を理解している人。
< 7>無上士(ムジョウジ):無上の人格を成就(ジョウジュ)した人。
< 8>調御丈夫(ジョウゴジョウブ):どんな人をも思うままに教え導くことができる人。
< 9>天人師(テンニンシ):天上界・人間界の大導師(ダイドウシ)。
<10>仏(ブツ):仏陀(ブッダ)。覚(サト)った人。
<11>世尊(セソン):世に中で尊重(ソンチョウ)される人。
| 言葉 | 十三塚原 |
|---|---|
| 読み | じゅうさんつかばる |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)鹿児島県中部、霧島火山の南西方の姶良郡(アイラグン)溝辺町(ミゾベチョウ)・隼人町(ハヤトチョウ)に広がるシラス台地。標高約300メートル。
| 言葉 | 十三階段 |
|---|---|
| 読み | じゅうさんかいだん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ | 道具 |
(1)死刑が確定した人々が絞首刑を執行される木の枠
(2)an instrument of execution consisting of a wooden frame from which a condemned person is executed by hanging
| 言葉 | 十二月病 |
|---|---|
| 読み | じゅうにがつびょう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)クリスマス・イブ直前になると生じる精神的ストレスのこと。
| 言葉 | 十二神将 |
|---|---|
| 読み | じゅうにじんしょう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)薬師如来の眷属(ケンゾク)で、仏教の守護神。薬師如来の神力により『薬師経』を行ずる者を守護する12の夜叉(ヤシャ)大将。
薬師如来が発した十二の大願に応じて現れる薬師如来の分身ともされる。
「薬師十二神将」,「十二神明(シンメイ)」,「十二神明王」とも呼ぶ。
| 言葉 | 十八檀林 |
|---|---|
| 読み | じゅうはちだんりん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)江戸初期に定められた関東の浄土宗の18ヶ所の学問所。
< 1>光明寺:相模国鎌倉。
< 2>勝願寺:武蔵国鴻巣。
< 3>常福寺:常陸国瓜連。
< 4>増上寺:江戸府芝。
< 5>弘経寺:下総国飯沼。
< 6>東漸寺:下総国小金。
< 7>大巌寺:下総国生実。
< 8>蓮馨寺:武蔵国川越。
< 9>大善寺:武蔵国滝山。
<10>浄国寺:武蔵国岩槻。
<11>大念寺:常陸国江戸崎。
<12>善導寺:上野国館林。
<13>弘経寺:下総国結城。
<14>霊山寺:江戸府本所。
<15>幡随院:江戸府下谷(現:小金井市に移転)。
<16>伝通院:江戸府小石川。
<17>大光院:上野国新田。
<18>霊巌寺:江戸府深川。
「十八談林」,「関東十八檀林」とも呼ぶ。いん(幡随院),でんづういん(伝通院)
| 言葉 | 十六代様 |
|---|---|
| 読み | じゅうろくだいさま |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)大政奉還後の徳川の宗家、第16代将軍の徳川家達(イエサト)を遠まわしに指し示した呼称。
| 言葉 | 十六善神 |
|---|---|
| 読み | じゅうろくぜんしん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)『般若経』を受持(ジュジ)し読誦(ドクジュ)する者の守護を誓った16体の夜叉(ヤシャ)善神。
「釈迦十六善神」,「般若守護十六善神」とも呼ぶ。
| 言葉 | 十六大国 |
|---|---|
| 読み | じゅうろくだいこく |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)原始仏教聖典に現れる、釈迦(シャカ)在世時代の諸国(都市国家)。国)
コーサラ(Kosala)(拘薩羅)。
バツァ(Vatsa)(跋沙)。
アバンティ(Avanti)(阿般提)。
ブリジ(Vriji)(跋耆)。
ガンダーラ(Gandhara)(健駄邏)。
アシュマカ(Ashmaka)(阿濕波)。
カンボージャ(Kamboja)(甘蒲闍)。
クル(Kuru)(倶盧)。
パンチャーラ(Panchala)(般遮羅)。
シューラセーナ(Surasena)(蘇羅色那)。
チェーティ(Cheti)(車底)。
カーシ(Kasi)(迦尸)。
マツヤ(Matsya)(婆蹉)。
アンガ(Anga)(鴦伽)。
| 言葉 | 十六進法 |
|---|---|
| 読み | じゅうろくしんほう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)0~9とA~Fの16個の組み合せで全ての実数を表す記数法。
10~15は”A~F”で、16は”10”、31は”1F”、32は”20”と表記する。
十進法の”1,000”の表記は”X’3E8’”または”H’3E8’”、C言語では”0x3e8”。
主にコンピュータ上のデータの表記に用いられる。
「十六進数(16進数)(hexadecimal digit)」,「ヘキサデシマル(hexadecimal)」とも呼ぶ。進法)
| 言葉 | 十六銀行 |
|---|---|
| 読み | じゅうろくぎんこう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)岐阜県岐阜市に本店を置く地方銀行。
東海地方(愛知県・岐阜県・三重県)を基盤とする。
姉妹サイト紹介

| 言葉 | 十分な量 |
|---|---|
| 読み | じゅうぶんなりょう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 十大功労 |
|---|---|
| 読み | じゅうだいこうろう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)ヒイラギナンテン(柊南天)の漢名。
| 言葉 | 十月革命 |
|---|---|
| 読み | じゅうがつかくめい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)1917年11月のレーニン支配下のボリシェヴィキによるクーデターで、1922年にボリシェヴィキの勝利に終わった内戦時代へとつながった
(2)the coup d'etat by the Bolsheviks under Lenin in November 1917 that led to a period of civil war which ended in victory for the Bolsheviks in 1922
| 言葉 | 十条製紙 |
|---|---|
| 読み | じゅうじょうせいし |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)日本製紙の前身の一社。
| 言葉 | 十種競技 |
|---|---|
| 読み | じゅっしゅきょうぎ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 団十郎茶 |
|---|---|
| 読み | だんじゅうろうちゃ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | ルイ十七世 |
|---|---|
| 読み | るいじゅうななせい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)フランス王ルイ十六世と王妃マリー・アントワネット(Marie-Antoinette)の息子(1785. 3.27~1795. 6. 8)。
1792(寛政 4)国外逃亡を企(クワダ)てたとして両親とともに捕らえられて収監。
1795(寛政 7)監獄で結核により死亡。
| 言葉 | ルイ十三世 |
|---|---|
| 読み | るいじゅうさんせい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)フランス王(1601~1643)。ルイ十四世の父。(3)
| 言葉 | ルイ十八世 |
|---|---|
| 読み | るいじゅうはっせい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)フランス王(1755.11.17~1824. 9.16)。在位:1814~1815、1815~1824。
ルイ十五世の孫、ルイ十六世の弟、ルイ十七世の叔父。
1815(文化12)ナポレオンの百日天下で一時ベルギーに逃亡。
| 言葉 | ルイ十六世 |
|---|---|
| 読み | るいじゅうろくせい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)フランス王(1754~1793. 1.)。在位:1774~1792。ルイ十五世の孫。妃はマリー・アントワネット(Marie Antoinette)。
姉妹サイト紹介
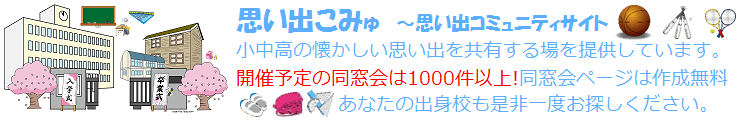
| 言葉 | ルイ十四世 |
|---|---|
| 読み | るいじゅうよんせい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)フランス王(1638. 9. 5~1715. 9. 1)。在位:1643~1715。
ルイ十三世とアンヌ・ドートリッシュ(Anne d’Autriche)の長男。ルイ十五世の祖父。
1685(貞享 2)ナントの勅令(L’Edit de Nantes)を撤回。
「太陽王(le Roi Soleil)」とも呼ぶ。どらごねいど(ドラゴネイド)(1)
| 言葉 | レオ十三世 |
|---|---|
| 読み | れおじゅうさんせい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)ローマ教皇(1810~1903)。在位:1878~1903。俗名は”Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci”。
1837(天保 8)司祭となる。社会問題・労働問題に関心を示し、学校制度の確立、貯蓄銀行・神学校の設立などに貢献。
教皇に即位後も社会政策を推進して、ビスマルクと和解して文化闘争を終結させるなど国際友好にも手腕を発揮し、イタリア王国と対抗。教会への国家権力の介入に反対するなど教会の近代的地位の確立に貢献。
著書は1885(明治18)『インモルタレ・デイ(Immortale Dei)(国家と教会の関係)』・1891(明治24)回勅(encyclical)『レールム・ノヴァルム(Rerum Novarum)』など。
| 言葉 | 二十七度線 |
|---|---|
| 読み | にじゅうななどせん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)アメリカ軍占領下の琉球(沖縄)と日本本土との間にあった境界線。
「にじゅうしちどせん(二十七度線,27度線)」とも呼ぶ。ん(三十八度線,38度線),じゅうななどせん(十七度線,17度線)
| 1件目から30件目を表示 | 次の30件 > |