「夏」に関係する名詞
「夏」に関係する名詞の一覧を表示しています。 検索結果が多い場合は文字数で絞ることが可能です。| 1件目から30件目を表示 | 次の30件 > |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([学]Epilobium pyrricholophum)フトモモ目(Myr-tales)アカバナ科(Onagraceae)アカバナ属(Epilobium)の多年草。
山野の湿地に自生。高さ20~50センチメートル。 葉は対生・卵状披針形で長さ約4センチメートル。秋、紅紫色に紅葉する。 夏、上方の葉腋に淡紫紅色の小さい四弁花を開花。 果実は細長く、種子は微細で冠毛があり風で飛散。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([学]Oratosquilla oratoria)シャコ科シャコ属(Ora-tosquilla)の甲殻類。
内湾の泥深い干潟に穴を掘って生息。 産卵期は初夏。 北海道以南から台湾に分布。 食用で、傷みやすく、市場には茹(ユ)でたものが流通。 寿司の種(タネ)になる。 「青竜(セイリュウ,セイリョウ)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([学]Phaseolus vulgaris)マメ目(Fabales)マメ科(Fabaceae)インゲンマメ属(Phaseolus)の一年生作物。熱帯アメリカ原産。
多くはつる性草本で、つるのない矮性(ワイセイ)のものや、直立する変種(ツルナシインゲン)ものや、種子の形・色も多彩で、品種がきわめて多い。 葉は互生し広卵形の小葉3枚からなる複葉。夏に開花し、花は白色または淡紫色の蝶形花で、葉腋(ヨウエキ)から出た総状花序の上に数個つく。秋に結実し、莢(サヤ)は線形で細長く、中に10個ほどの腎臓形の種子をもつ。 未熟果のサヤや種子を食用とする。茎葉は飼料となる。 マメ類では大豆(ダイズ)・落花生(ラッカセイ)に次ぎ、インド・ブラジル・中国など世界で広く栽培されている。 「インゲン(隠元)」,「インゲンササゲ(隠元ササゲ)」,「ゴガツササゲ(五月ササゲ)」,「さんどまめ(三度豆)」,「さいとう(菜豆)」とも呼ぶ。 未熟果の柔らかいサヤのまま煮(ニ)て食べるものを「さやいんげん(莢隠元)」、サヤの丸いものを「どじょういんげん(泥鰌隠元)」、サヤの平たいものを「モロッコインゲン」と呼ぶ。熟した種子を煮豆にするものは「金時(キントキ)」など。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([学]Sarcandra glabra)双子葉植物センリョウ目(Chloranthales)センリョウ科(Chloranthaceae)センリョウ属(Sarcandra)の常緑小低木。
高さ約50~70センチメートル。 茎は枝分れし、ふくれた節がある。葉は対生し卵状楕円形で、先はとがり縁(フチ)に粗い鋸歯(キョシ)があり、長さ6~15センチメートル。 夏、短い花茎を出し、淡黄緑色の細かい花を穂状につける。花被はなく、おしべ・めしべともに1個。果実は球形・肉質の核果で、径約5~6ミリメートル、冬に赤く熟し、黄熟する品種もある。 本州の関東以南、四国・九州・沖縄や東南アジアなどの暖地の山林で、樹下の湿った日陰に自生。また果実の鑑賞用として庭木・鉢植に、また果実のついた枝を正月用の飾りなどにする。 キミノセンリョウは果実が黄熟する品種で、観賞用に栽植される。 「クササンゴ(草珊瑚)」,「仙蓼(センリョウ)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([学]Vaccinium praestans)ツツジ目(Ericales)ツツジ科(Ericaceae)スノキ属(Vaccinium)(コケモモ属)の落葉低木。
本州中部以北の高山帯に広く分布し、高さは5~15センチ。長い地下茎を伸ばし、所々に茎を立てながら繁殖する。 夏に小さな淡紅色の鐘状花を2、3個つける。果実は球形で紅熟し、甘酸っぱく食用になる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([英]A Midsummer Night’s Dream)シェークスピア(William Shakespeare)の喜劇。5幕。
アセンズ([英]Athens)(アテナイ)の公爵シーシアス(Theseus)とアマゾン女王ヒッポリタ(Hippolyta)の婚礼4日前の夜、アゼンス郊外の森で、彼らと妖精の王オベロン(Oberon)とその妃ティタニア(Titania)、アテナイに住む二組の恋人が、オベロンの指示を勘違いした妖精パック(Puck)の惚れ薬によって大混乱になった挙句(アゲク)に、めでたく四組の結婚愛が成立するという話。 「夏の夜の夢」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (アラビア・シリア・アフリカなどの砂漠で)春夏に砂嵐(スナアラシ)を起こす熱風。
「シムーン(simoon)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (五行説で)五天帝の一神。火性・夏(朱夏)・南方を支配する。
「炎帝(Yandi)」,「火帝(Huodi)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)五節句の一つ、五月五日の節句。
日本では奈良時代に中国から祝う習慣が伝来し、ショウブ(菖蒲)やヨモギ(蓬)を軒に挿して邪気を払い、粽(チマキ)や柏餅(カシワモチ)を食べる風習ができた。 ショウブが「尚武(ショウブ)」に通じることから、江戸時代以後は男子の節句とされ、武家では甲胄(カッチュウ)などを飾り、庭先に幟旗を立てて男子の成長を祝った。次第に町人も武者人形などを飾り、鯉幟(コイノボリ)を立てるようになった。 第二次世界大戦後は「こどもの日」として国民の祝日となった。 「端午の節句」,「端午の節(セチ)」,「あやめ(菖蒲)の節句」,「重五(チョウゴ)」,「端陽(タンヨウ)」,「夏節([中]Xiajie)(カセツ)」とも呼ぶ。龍) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (英語で)真夏・盛夏・暑中。
北半球で7月初めから8月中ころ。 一説に7月3日から8月11日まで、また7月初めから9月初めまで。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (関東地方で)ブリ(鰤)の若魚。全長40センチメートルくらい。
夏に多くとれる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 11世紀オルドス地方にいたタングート(Tanguts)(党項)族の一氏族拓跋氏(Taba Shi)(タクバツシ)の建てた国(1038~1227)。
1038年、李元昊(Li Yuanhao)(リ・ゲンコウ)が帝を称して建国。首都は興慶(Xingqing)(コウケイ)。国号は大夏(Da Xia)と号したが、宋(Song)では西夏と呼ぶ。 1044年、宋と和議し西夏王に封ぜられる。 1124年以後は金(Jin)に服属し、1227年モンゴルに滅ぼされる。 東方の契丹人(Qidan Ren)(キッタンジン)の遼(Liao)(リョウ)と結んで宋朝(Song Chao)と対立し、東西交通路にあって経済的利益を占めた。 言語はチベット・ビルマ系に属し、固有の西夏文字を作成。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1614(慶長19.11.)大坂冬の陣と、翌年1615(慶長20. 5.)大坂夏の陣の総称。
方広寺鐘銘事件が冬の陣の口実に使われた。ちゃうすやま(茶臼山),さなだまる(真田丸) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1918(大正 7)夏から秋にかけて世界的に流行した悪性のインフルエンザ。H1N1型。
伝染力が強く、急性肺炎を併発し、死亡率が非常に高かった。死者2,500万と言われ、第一次世界大戦の死者よりも多かった。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1945年の夏のポツダム会議の場所 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1977. 4.26(昭和52)代表中山千夏で発足。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 『書経』周書の編名。古代中国、夏(カ)王朝の始祖禹(ウ)が尭(ギョウ)・舜(シュン)以来の思想を整理・集大成したといわれ、天の常道と治世の要道が書かれた天下の大法。
儒家の政治道徳の基本とされる書。 殷(イン)の箕子(キシ)を経て周の武王に伝えられたとされる。 |
姉妹サイト紹介

| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | さざ波織り。綿やレーヨン織物を薬品で表面加工し、局部的に縮らせたもの。さらりとした夏向きの生地。
「リプル」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | それは、太陽が北の冬至点に見える最北端と、白夜が北の夏至点に見られる最南端を示している |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アオイ目(Malvales)アオイ科(Malvaceae)シナノキ亜科(Grewioideae)ツナソ属(Corchorus)の一年草。夏野菜の一種。中近東・北アフリカに自生。
草丈は2メートル弱。葉脇にヒゲがある。 5月ころに種を撒(マ)き、7~8月に黄色い花を開く。 若い葉を食用にする。葉を細かく刻むとトロミが出る。 スープの具・和え物・炒め物などにする。 「シマツナソ(縞綱麻)」,「タイワンツナソ(台湾綱麻)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アオイ目(Malvales)アオイ科(Malvaceae)フヨウ属(Hi-biscus)の常緑低木。
中国南部の原産で鑑賞用に温室などで栽培される。 夏から秋にかけ、大形でムクゲに似た漏斗(ロウト)状の五弁花をつける。花の色は品種により赤・桃・白・黄・橙など。 沖縄では 漢名は「扶桑(フソウ)」。 園芸品種は「ハイビスカス(hibiscus)」と呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アオイ目(Malvales)フタバガキ科(Dipterocarpaceae)サラノキ属(Shorea)の常緑高木。インド原産。
高さ30メートルにもなる。葉は長い卵形で、薄黄色の小花を無数に開く。材は堅く良質の建築用とし、種からは油をとる。 「サラソウジュ(沙羅双樹)」とも、単に「沙羅」とも呼ぶ。ばき(ナツツバキ,夏椿) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アカザ目(Centrospermae)アカザ科(Chenopodiaceae)ホウキギ属(Kochia)の一年草。西アジア~中央アジア原産。
高さ約1メートル。茎は赤色を帯び、細かく多数に枝分かれし、狭披針形の葉を密に互生する。 夏に葉腋に穂状に黄緑色の小花を開き、秋に草全体が紅葉する。 各地に自生し、また栽培する。 緑色の小球形の実は「とんぶり(トンブリ)」と呼び、食用・薬用(強壮・利尿)にする。 茎や枝を干して草箒(クサボウキ)を作る。 「ホウキギ(箒木)」,「ハハキギ(箒木)」,「コキア(Kochia)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アカザ目(Centrospermae)ヒユ科(Amaranthaceae)ヒユ属(Amaranthus)の一年草。インド原産。
葉は卵形。夏から秋にかけ、黄緑色の小花の集まった穂を球状につける。 若葉を食用にする。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アデノウイルスに感染して、咽頭炎・気管支炎・結膜炎などを起こす疾患。
おもに夏季にプールなどで感染し、目が充血し、のどが痛み、4・5日39~40度の高熱が続く。 略称は「PCF」で、俗に「プール熱(pool fever)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アメリカの舞台・映画女優(1909.11. 9~2003. 6.29)。コネティカット州ハートフォード(Hartford)生れ。
晩年、パーキンソン病などを患う。 主演作品は1933(昭和 8)『若草物語(Morning Glory)』・1940(昭和15)『フィラデルフィア物語(The Philadelphia Story)』・1942(昭和17)『火の女(Woman of the Year)』・1949(昭和24)『アダム氏とマダム(Adam’s Rib)』・1951(昭和26)『アフリカの女王(The African Queen)』・1955(昭和30)『旅情(Summer-time)』・1959(昭和34)『去年の夏 突然に(Suddenly, Last Summer)』・1962(昭和37)『夜への長い旅路(Long Day’s Jour-ney Into Night)』・1967(昭和42)『招かれざる客(Guess Who’s Coming to Dinner)』・1968(昭和43)『冬のライオン(The Lion in Winter)』・1981(昭和56)『黄昏(タソガレ)(On Golden Pond)』など。 「ヘプバーン」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | イギリスの夏時間の略称。
GMT(グリニッジ標準時)より1時間進めた時刻。 |
姉妹サイト紹介
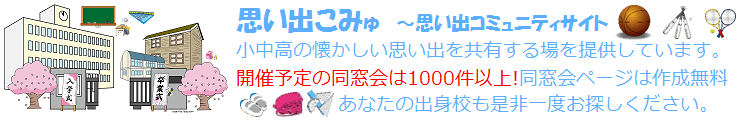
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | イトバショウ(糸芭蕉)の茎の繊維から採った糸で織った平織りの布。
淡茶無地または濃茶絣(コイチャガスリ)で、張りがあって肌につかないので、夏の単衣(ヒトエ)・座蒲団地・蚊帳(カヤ)・ふすま張地などに用いられる。 沖縄および奄美大島の特産。 「芭蕉織(オリ)」,「蕉紗(ショウシャ)」,「蕉布(ショウフ)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | イネ目(Poales)イネ科(Poaceae)ライムギ属(Secale)の一年生または二年生作物。
製粉して黒パンにしたり、ウィスキー・ウォッカの原料とする。 「クロムギ(黒麦)」,「ナツコムギ(夏小麦)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | インド南西端、ケララ州(Kerala State)で伝説上の王マハーバリ(Mahabali)を称える夏祭り。
8~9月ころ、マラーヤラム暦(Malayalam calendar)の第一月チンガム(Chingam)に開催される。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ウシ目(偶蹄目)(Artiodactyla)ウシ科(Bovidae)の哺乳類。
シカ(鹿)と異なり、角は短く、先が枝分かれしない。 春から夏にかけて出産し、母親は翌春まで子とともに生活する。 単に「カモシカ(羚羊,氈鹿)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ウナギ目(Anguilliformes)ハモ科(Muraenesocidae)の海魚。
体形はウナギ(鰻)に似て細長く、全長約2メートル。背部は灰褐色で、腹部は白色。体は滑らかでウロコ(鱗)がない。吻(フン)はとがり、口は大きく歯が発達して鋭く、性質は荒い。 本州中部以南の沿岸、太平洋・アフリカ東岸にまで広く分布。水深50メートル以浅の砂泥底や岩礁の間に棲(ス)む。 小骨が多いので骨切りをし、吸い物・蒲焼(カバヤ)き・湯引(ユビキ)などにする。旬(シュン)は夏。 地方名は「ハム(鱧)」,「バッタモ」,「ジャハム」,「ウニハモ」など。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ウリ目(Cucurbitales)ウリ科(Cucurbitaceae)トウガン属(Benincasa)のツル性(蔓性)一年草果菜。
果実は夏が旬(シュン)。 「とうが(冬瓜)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | オモダカ目(Alismatales)サトイモ科(Araceae)サトイモ属(Colocasia)の一年生作物。熱帯アジア原産の多年草。
晩夏から秋に球茎(芋)を収穫。軟らかい子芋・孫芋を食用にする。また、若い葉柄も食用にする。〈品種〉 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | オモダカ目(Alismatales)サトイモ科(Araceae)ハンゲ属(Pinellia)の多年草。
春、地下の小型の球茎(キュウケイ)から長柄の葉を1~2個出し、葉は三小葉からなり、葉柄にはムカゴができる。 初夏、花茎の上端に緑色の円筒状の仏炎苞(ブツエンホウ)を生じ、内側には肉穂花序をつける。 日本全土・東アジアの畑地に生(ハ)える雑草。 球茎(キュウケイ)を漢方薬にする。 「ハンゲ(半夏)」,「ヘソクリ(綜麻繰,臍繰)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | カジカ目(Cottiformes)アイナメ科(Hexagrammidae)の浅海魚。
体長約40センチ。体色は黄色、褐色などさまざま。 磯釣(イソヅリ)にする。脂身が少ない白身の魚で美味。旬は春から初夏。 「アブラメ(油女,油魚)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | カッコウ目(Cuculiformes)カッコウ科(Cuculidae)カッコウ属(Cuculus)の鳥。
カッコウによく似るがやや小形で全長約30センチメートル。背面は灰青色で尾は灰黒色、腹面は黄白色の地にはっきりとした黒い横縞があり、カッコウの横縞より太い。 センダイムシクイやアオジなど他の鳥の巣に托卵(タクラン)する。 アジアに広く生息し、初夏に夏鳥として日本・台湾・中国南部の低山帯に渡来し、冬はインドネシアなどの南方に渡る。 「ポポッ、ポポポン」と空筒(カラヅツ)を打つような低い鳴き声で、「ポンポンドリ」とも呼ぶ。〈亜種(subspecies)〉 Himalayan Cuckoo:Cuculus saturatus。 Oriental Cuckoo:Cuculus optatus。 Sunda Cuckoo:Cuculus lepidus。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | カレイ目(Pleuronectiformes)カレイ科(Pleuronectidae)の海産の硬骨魚。
全長20~30センチメートル。 体形は扁平(ヘンペイ)で楕円形、口が小さい。両眼は体の右側に位置し、有眼側は暗褐色で黒褐色斑が散在し、無眼側は白色。 北海道南部以南から東シナ海の沿岸に生息する。 旬(シュン)は夏。 「マコ(真子)」,「シロシタガレイ(城下鰈)」,「アマテガレイ(アマテ鰈)」,「アマテ」,「アマガレイ」,「ホソクチ(細口)」,「モク」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | キク目(Asterales)キク科(Asteraceae)アザミ属(Cir-sium)の総称。種類は多く約200種、日本には約60種。北半球の温暖~寒帯、海岸~高山に広く分布する。ほとんどは多年草だが二年草もある。
高さは0.5~1メートル。葉は大形で深い切り込みがある鋸歯(キョシ)または羽状に裂け、鋭い刺(トゲ)が多く、裏面に毛を密生するものもある。多くのものは秋に開花し、小さな管状花が多数集まった半球形の頭花で、通常紅紫色・淡紅色まれに白色、横または下向きに咲くものが多い。 ノアザミは本州以南に分布し、頭花は直立で春~夏に咲く。花屋で売られているドイツアザミはノアザミの改良されたもの。 オニアザミはトゲアザミとも呼ばれ、中部地方北部・東北地方に分布し、濃紫色の頭花はうなだれ、初夏~秋に咲く。 サワアザミはオンナアザミとも呼ばれ、山の沢沿いの湿った土地に生え、1~2メートルにもなる。 フジアザミは山地の川原や崖に生え、大形で8~10月に10センチ近くの花を咲かせる。富士山の近くに多いのでこの名がある。 ハマアザミは海岸の砂地に生え、頭花は直立し、7~9月に咲き、葉に強い光沢がある。根はゴボウのような形と香味からハマゴボウとも呼ばれる。 ナンブアザミは中部地方以北の山地に生え、夏~晩秋に咲く。 一般に根の食べられるものが多く、モリアザミは畑地に栽培されている。味噌漬けや醤油漬けになって観光地で売られているヤマゴボウは、このモリアザミの根で、本来のヤマゴボウの根は有毒で商陸(ショウリク)と呼ばれる生薬に使われている。 アザミゴボウはヨーロッパ産で、牧場のキャベツとも呼ばれる。 タイアザミの根は煎じて強壮薬・解薬・利尿薬となる。 「刺草(シソウ)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | キク目(Asterales)キク科(Asteraceae)イズハハコ属(Conyza)の越年草。南アメリカ原産。
秋に芽生え、ロゼットで越冬して春から初夏に開花する。 日本には明治中ころに渡来した帰化植物で、日本各地の路傍に自生している普通の雑草。 |
| 言葉 | (1)ハヤチネウスユキソウ | 詳しく調べる |
|---|---|
| 意味 | キク目(Asterales)キク科(Asteraceae)ウスユキソウ属(Leontopodium)の多年草。
岩手県の早池峰山、北海道の大平山(オオヒラヤマ)の高山帯の岩地に自生。 高さ10~20センチメートルで、全体に白い綿毛がある。夏に黄色の筒状花をつけ、エーデルワイスに似る。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | キク目(Asterales)キク科(Asteraceae)ノゲシ属(Son-chus)の二年草。
山野に自生。茎は中空、葉は互生で不規則に裂け、アザミに似ている。春夏のころ、茎の頂に分枝してタンポポに似た黄色頭状花を開く。 「けしあざみ(ケシアザミ,芥子薊,苦菜)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | キク目(Asterales)キク科(Asteraceae)ヒマワリ属(Hel-ianthus)の一年草。メキシコ原産。
高さは2~3メートルになる。夏から秋に直径20センチメートルに達する大型の花が咲く。花の中心部は茶色、周囲は黄色。 種子は食用または油を採る。 「ひぐるま」,「日輪草(ニチリンソウ)」,「サンフラワー([英]sunflow-er)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | キク目(Asterales)キク科(Asteraceae)ムカシヨモギ属(Erigeron)の越年草(二年草)。
都会地の道端や荒れ地に群生する普通の雑草。 高さ1~1.5メートル。全体に粗毛があり、茎は直立し、夏から秋にかけて茎頂に径3ミリメートルくらいの白色の頭状花を多数つける。 若芽は食用となる。 北アメリカ原産の帰化植物で、世界中の熱帯・温帯に生息する。 日本には、明治維新ころに渡来して短期間で各地に広がったため、「御維新草(ゴイシングサ)」,「明治草(メイジソウ)」,「世代り草(ヨガワリグサ)」,「官軍草(カングンソウ)」,「西郷草(サイゴウグサ)」とも、また鉄道路線の雑草として「テツドウグサ(鉄道草)」とも呼ぶ。 |
| 1件目から30件目を表示 | 次の30件 > |