「く」に関係する名詞
「く」に関係する名詞の一覧を表示しています。 検索結果が多い場合は文字数で絞ることが可能です。| 91件目から120件目を表示 | < 前の30件 | | | 次の30件 > |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (”much”の最上級)最も多い、最も多くの。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (すらすらと読めるように)原稿などを前もって読んでおくこと。
読み間違えや読みよどむことがなくなる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (へたばって)動けなくなる。座り込む。
「へたる」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (みすぼらしく)期待外れな。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (よく尾を上下に振る習性から)セキレイの別称。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (イギリスで)頭にターバンを巻くインド人やイラク人・アラブ人への別称。
「タオルヘッド(towelhead)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (イスラム教で)寄進、とくに寄進地。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (イタリア語で)おたふく風邪・耳下腺炎(ジカセンエン)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (イタリア語で)覗く人。のぞき魔・デバカメ(出歯亀)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (カトリック教会で)司祭がミサなどのとき着用する、白麻の足までとどく長衣。
アミクトス(amictus)の上に着る。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (ゴルフで)ハンディキャップを差し引く前の、ラウンド終了時の総打数(スコア)。
「グロススコア(gross score)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (スパイや密売人などが)互いに会わずに秘密の物品を受け渡すこと。また、その受け渡し場所。
公衆トイレの貯水槽などがよく使われる。物を置いたときはトイレ前の草を結んだり小石を置いたりなどで情報を伝え、受け取ると草をほどいたり小石を除いたりする。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (タバコなどを)軽く叩(タタ)いて詰める。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (ドイツ語で)くじら座。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (フェンシングで)前進・前へ歩く。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (フェンシングで)突け。
アロンジェブラ(allongez le bras)(腕を伸ばし剣を突き出した姿勢)から大きく踏み出すこと。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (フランス語で)けばけばしく飾った、ど派手な。 |
姉妹サイト紹介

| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (プログラム開発で)ダミーのサブルーチン。デバッグ(debug)に使用する。
大半は呼び出し時の引数の値に関係なく、定められた復帰値を返すだけの簡単なルーチン。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (一般に)暖かくなって、冬の間使用していた炉や暖房器具の使用をやめ、ふたをしたり仕舞(シマ)ったりすること。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (中国・日本で)(1)を原料とした、細長い乾麺(干麺)。
熱湯につけて戻し、焼きそばのように野菜・肉と炒(イタ)めたり、あん掛けにしたり、スープの具にもする。 中国南部・台湾で多く食べられている。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (主に北海道・東北地方で)ばからしい・あほらしい・あほくさい。
「はんかくせぇ」と言うことが多い。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (乾燥などで)木材の中央部分が高く湾曲すること。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (人が物を)注意深く見続けること。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (人と人が)互いに、鋭くにらみ付け合うこと。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (人を)だます・あざむく。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (位相が近く)波動が互いに干渉し合う、可干渉性の、干渉性を持つ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (佐渡地方で)花嫁が婿方に着くとすぐ村人に出す酒。
単に「あしあらい(足洗い,足洗)」とも呼ぶ。 |
姉妹サイト紹介
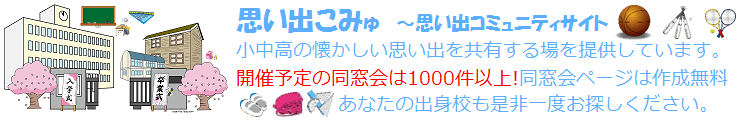
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (刺激や感動などで)目眩(メマ)いがする。目眩いでくらくらして倒れそうになる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (動作・行為が)のろまである、のろくさい。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (北米インディアンの)枝を編んでつくった円錐形の小屋。 |
| 言葉 | (1)アルスロンガ・ビタブレビス | 詳しく調べる (2)アルス・ロンガ・ビタ・ブレビス | 詳しく調べる |
|---|---|
| 意味 | (原意)一芸に達するには長く、人生は短い。
「学ぶべき技術や芸は多くまた奥深く、とても時間が足りない」の意味。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (古代ギリシア・ローマの)兵士をすきまなく方形に配列する陣立(ジンダテ)。
「方陣(ホウジン)」,「密集軍(ミッシュウグン)」とも呼ぶ。やりぶすま(槍衾) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (古代中国および日本の律令法で)妻を離婚できる七つの条件。
これらの内、一つでもあれば離縁(リエン)をしてもよいとされた。 <1>夫の両親に従順でない。 <2>子を産めない。 <3>おしゃべりである。 <4>盗みをする。 <5>品行がみだらである。 <6>嫉妬(シット)深い。 <7>直りにくい病気がある。 「七出(シチシュツ)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (同業他社の)人材を引き抜く。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (同音の反復で)「常(トコ)しく」,「求(ト)む」に掛かる枕詞。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (和菓子で)主に餡(アン)類を用い、水分が多く軟らかい菓子の総称。
餅菓子・蒸し菓子・饅頭(マンジュウ)・練り切り・羊羹(ヨウカン)など。 「和生菓子」,「和生(ワナマ)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (地名・場所に付けて)中央から遠く離れた、場末(バスエ)または遠隔の地を強調する言い方。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (女性が)なまめかしく色っぽいさま。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (子供用の)袖なし羽織(ハオリ)。
多く綿入れた防寒用。 「ちゃんちゃん」とも呼ぶ。れきいわい(還暦祝い,還暦祝) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (定期路線の)バスの女性車掌。
古くは「女車掌(オンナシャショウ)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (対馬地方で)埋葬の際、墓場へ持って行く酒。
単に「あしあらい(足洗い,足洗)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (対馬地方などで)葬式から帰る人の穢(ケガ)れを払うため、座敷口に用意しておく清めの水。
単に「あしあらい(足洗い,足洗)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (怒り・いらだち・嫌悪などを表して)クソ・くそったれ・チクショウ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (性質・特徴・状態などが)気に入らせる・魅力的にする・好ましくさせる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (想像上の)白い羽毛に似た生き物。
空から飛んできて、化粧箱に入れておくと白粉(オシロイ)を食べて成長するという。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (数々の)辛(ツラ)く苦しい経験をする。大いに苦労する。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (新刊の)書籍の外箱やカバー(表紙)の下の方に巻く帯状の紙。
内容や著者の紹介や著名人の批評などが印刷されたもの。 俗称は「こしまき(腰巻,腰巻き)」。 |
| 言葉 | (1)トレーニング・パンツ | 詳しく調べる |
|---|---|
| 意味 | (日本で)スポーツの練習に用いる足首まである長いパンツ。多くは白色。
和略語で「トレパン」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (日本では少年に限らず)出家して未だ正式の僧になっていない見習僧。
「さみ(沙弥)」,「童子([梵]kumara)」とも呼ぶ。門),びく(比丘) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (望ましくなく忌避したいものの場合)たいへんだ、とんでもない、恐ろしい、困った、つらい、情けない、たいへん悲しい、不快だ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (柔らかく仕立てた)婦人服。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (死んで成仏するのではなく)生きたまま肉身の姿で悟りを開いて仏となること。
結果、身体はミイラとしてこの世に残る。神社) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (比喩的に)明るく希望にみちている状態。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (法身の光明が)あまねく世界を照らすこと。
「へんしょう(遍照)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (灯台などの)光の届く範囲。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (物事を決めるため)くじを引くこと。抽籤(チュウセン)。
「くじとり(くじ取り,籤取り,籤取)」とも呼ぶ。籤),とみくじ(富くじ,富籤,富鬮) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)すぐに使えるように製造された黒色の液。
筆で字を書くほか、製図・漫画などではペン先につけて使用する。 |
| 言葉 | (1)セーフティー・レバー | 詳しく調べる |
|---|---|
| 意味 | (特に)オートマチック・ピストル(自動式拳銃)のスライド(遊底)横に着いている安全装置。
これを安全側に倒しておくと引き金を引いても撃鉄が降りず、弾丸は発射されない。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)原水爆の被害を直接、またはその放射能の被害を受けること。る(第五福竜丸),くろいあめ(黒い雨),なつのはな(夏の花),はだしのげん(はだしのゲン) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)塩を強くした塩鮭(シオザケ)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)文章の修飾がうるわしく加えられていること。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)根が丸く、皮は赤く、中身は白いもの。
サラダなど生食に適する。 「ラディッシュ」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)気温の日較差。
晴れの日は雨や曇りの日より大きく、また内陸ほど大きくなる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)燻製のニシン(鰊)(herring)。
イギリスでは朝食によく食べられる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)経済状態が悪くなること。落ち目になること。没落すること。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)薄く切ったトウフ(豆腐)の水をきり、油で揚げた食品。
「あぶらげ(油揚げ,油揚)」,「あげどうふ(揚げ豆腐,揚豆腐)」とも、単に「あげ(揚げ,揚)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)那智山にある一つの滝の名。日本三名瀑一つ。落差133メートル。
飛滝神社(飛瀧神社)の神体で、古くから修験道の道場。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に浄土門で)阿弥陀如来(アミダ・ニョライ)を念じて浄土(ジョウド)に往生(オウジョウ)しようと願う人の臨終に、阿弥陀如来と諸菩薩が現れて極楽浄土に迎え導くこと。
「らいこう(来迎)」とも呼ぶ。ん(紫雲)(2),はっけん(発遣,撥遣)(2) |
| 言葉 | (1)孔席暖まらず墨突黔まず | 詳しく調べる |
|---|---|
| 意味 | (班固『答賓戯<トウヒンギ>』)孔子と墨子の二人は、道を天下に広めるために家に落ちついていなかったから、孔子の座席は暖まることなく、また墨子の家の煙突は炊事の煙りで黒くなることがなかったという故事。
「孔席暖まるに暇(イトマ)あらず」,「墨突黔まず」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (生れを同じくする)カースト集団。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (白く泡立つ)瀑布(バクフ)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (目と耳の両方とも不自由な人が用いる)聞く人に話す人の手を触れさせて、決められている字母を指の形で表し、語や文を綴(ツヅ)って意思を伝達する会話法。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (相撲用語)取り組み中、力士の体勢がくずれて倒れかけてはいるが、体の重心は失っていない状態。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (笛などの)清く美しい音(ネ)。また、声。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (群馬県で)カシ(樫)で作られた風除(ヨ)けの垣根(カキネ)。
上州空っ風(カラッカゼ)と呼ばれる冬から春の季節風を防ぐため、宅地の北側や西側に設けるもの。 カシが用いられるのは、高くまた冬でも葉が落ちないことから。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (芸者・遊女・女給などが)客がなくて暇(ヒマ)であること。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (英語で)大釜(オオガマ)。
深く、取っ手と蓋(フタ)がある。脚付きもある。 「コールドロン」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (英語で)長く深い切り傷。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (血統に関係なく)同じなかまに属すこと。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (西アフリカ原住民の)物神(ブッシン)。呪物(ジュブツ)・護符(ゴフ)・お守り・魔除け。ー教),まくんば(マクンバ) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)(4)を結う年齢くらいの小児。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)([英]stereotype)物事の形式が型にはまっていて、変化が乏しく新鮮味がないこと。また、その決まりきったやり方。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)いくら続けても役に立たない、無駄な努力。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)いまだ世間に知られていない、在野に隠れている俊傑・大人物。
「がりゅう(臥竜,臥龍)」,「ふくりょう(伏竜,伏龍)」,「ふくりゅう(伏竜,伏龍)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)いまだ世間に知られていない、在野に隠れている俊傑・大人物。
「ふくりゅう(伏竜,伏龍)」,「がりょう(臥竜,臥龍)」,「がりゅう(臥竜,臥龍)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)くたびれた、つかれた。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)ごくまれなこと・めったにないこと。 |
| 言葉 | (1)ハンプティーダンプティー | 詳しく調べる (2)ハンプティー・ダンプティー | 詳しく調べる |
|---|---|
| 意味 | (転じて)ずんぐりむっくりの人。転ぶと起き上がれない人。
「ハンプティダンプティ」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)その年ごろの子供。3歳から10歳くらいの子供。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)だぶだぶして、何でも入るような大きな袋。多くは布製のもの。
「ずた袋」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | (1)ちゃんちゃら可笑しい | 詳しく調べる |
|---|---|
| 意味 | (転じて)ばかばかしくて、相手にもしたくない。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)ふくらませるため中に入れる詰め物。
主に平仮名で「あんこ」と表記されることが多い。 「パディング([英]padding)」とも、洋服の場合は「パッド([英]pad)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)やせて顔色が青白く、元気のない人。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)シミのように本にかじりつくばかりで、その活用を知らない人の蔑称(ベッショウ)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)トンボを捕えること。その遊び。
トンボの眼に人差し指を向け、くるくる回しながら近づして羽を指に挟む。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)中身の悪さを隠して、外面だけを飾り、とりつくろうこと・中身をいつわること。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)仏像の標準の高さ。
また、仏像の高さの単位で、2倍・5倍・10倍、または1/2・1/4・1/10などに造られる。 ただし、多くは結跏趺坐(ケッカフザ)の姿に造るので座高が八~九尺となり、この場合は「半丈六」と呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)他人の文章などをそっくり真似(マネ)ること。
俗に「ぱくり」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)企業などの組織または個人が、考え方などに柔軟性(ジュウナンセイ)を失って、とりまく情況の変化に適応(テキオウ)できなくなること。また、その状態。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)余計な世話をやくこと・でしゃばること。また、その人。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)別れた夫婦、特に妻から求めて家を出た夫婦は復縁することができないということ。が付く,焼け木杭に火が付く,焼木杭に火が付く)かえだにかえらず(落花枝に返らず)(3),そうこうのつま(糟糠の妻) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)効果のないことを承知で対処する、当座しのぎの行為や、その要員。
まったく望みのない場合は不要だが、将来なにかしらの対処が期待できる、または将来を判断できないときに行う。多くは後者で、無益な犠牲となる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)十メートルくらい離れていれば美人に見える女性。
「十メーター美人」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)命がけで物事をすること、全力をつくしてがんばること。また、そのさま。
転化して「一生懸命(イッショウケンメイ)」とも、略して「懸命」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)多くの人の目・多くの人の見る目。
「衆目(シュウモク)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)大学病院の教授・大臣・高官・議員・重役などが多数のお供(トモ)を従えて歩くことを皮肉って言う言葉。名旅行) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)富くじ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)忙しくて家にいる暇(ヒマ)がないこと。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)日常よく食べていたものや、よくやっていたスポーツ・趣味、生活圏としていた場所などから遠ざかっていること。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)東京山の手の有閑階級の婦人語。
現在は「ざあます」の方が多く使用される。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)欲得ずくの愛情。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)物が円形を描くように、同一方向に巡(メグ)り巻くさま。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)短い間隔をおいて、いくつか続くこと。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)育ちかよく、世間(セケン)知らずの青年。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)自由を束縛(ソクバク)するもの。
「くびっかせ(首っ枷,頸っ枷)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | (1)アルスロンガ・ビタブレビス | 詳しく調べる (2)アルス・ロンガ・ビタ・ブレビス | 詳しく調べる |
|---|---|
| 意味 | (転じて)芸術(作品)は長く、人生は短い。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)若い女性に親切を装って家まで送り届けると言って近づき、途中で乱暴しようとたくらんでいる男。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)言語や風俗などが、日本とも中国(朝鮮)とものわからないもの、わからないこと。
「筑羅が沖」,「筑羅の沖」,「ちくらてくら(筑羅手暗)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)贈り物として携えてゆくその地の産物。土産(ドサン)。
「わらづと(藁苞)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)道などが、曲がりくねっているさま。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて、人が)若く大成すること。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて、知られていない・知ってはいけない・知られてはならない)暗黒面・物事のくらい面。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (遊里で)一人の遊女が、一夜のうちに、かけもちまたは順次に替えて多くの客の相方となること。また、その客。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (酸素・空気を供給する)人工呼吸器・人工呼吸装置。
患者の肺に酸素または空気を人為的に送り込んで呼吸を補助する、または強制的に呼吸させる装置。 胸郭(キョウカク)に外から陰圧を加える鉄の肺型と、気道に陽圧を加えて肺を内からふくらませる方式とがある。 簡単な吸入器は「インハレーター(inhalator)」と呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (金持ちの子供などが)大切に保護されて、世間の波にもまれることもなく、苦労を知らずに育ったこと。また、そのような人。
特に、精神的にひよわな人や病弱な人などに用いる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (銃口・砲口などの)使用しない時に詰めておく木栓。
「スパイク([英]spike)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (長い髪をまとめる)輪ゴムを布でくるんだ飾りバンド。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (間投詞的に)えい、くそ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (関東地方で)クロマグロの30~60センチメートルくらいの幼魚。
「メジマグロ(めじ鮪)」,「メジカ(めじか)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (関東地方で)ブリ(鰤)の若魚。全長40センチメートルくらい。
夏に多くとれる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (関西地方で)小さく砕(クダ)いた氷。
「ぶっかき(打っ欠き)」,「かきごおり(かき氷,欠氷,欠き氷)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (陶磁器の焼き物で)素地の上に白色など良質の粘土を水で溶いて化粧掛けをすること。
質の悪い素地を隠したりするほか、焼く前に化粧掛けを削って色の異なる下地を出して模様や絵を描いたりする。 「化粧土(ケショウツチ)」とも呼ぶ。ぐらふぃてぃー(グラフィティー)(1) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (韓国・朝鮮語で)頭で押す・角で突く。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (韓愈『争臣論』)中国の戦国時代の墨子(ボクシ)は、自分の教えを天下に広めるため各地を奔走(ホンソウ)していたため、家で炊事をすることが少なく竈(カマド)の煙出しが黒くならなかったという故事。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (頭の回転・感受性が)間が抜けている、阿呆(アホ)くさい。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (馬が牽<ヒ>く)台の低い荷車([英]dray)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (駅や商店街などの近くに設けた)自転車置き場。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (高エネルギー物理学で)光速に近く加速した自由電子から高強度の放射光を発生させる装置。
NSを交互に変えた磁石を多数並べた中に加速した自由電子を通すことで、自由電子が幾度も蛇行して放射光を発生するもの。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1000円で満足いくまで飲むこと。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 10世紀に設立されたいくつかのギリシアの東方正教会の修道院の用地であるギリシャ北東部の自治区 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1185(元暦 2. 3.24)長門壇ノ浦で行われた源平最後の合戦。
平氏は平宗盛が安徳天皇および神器を奉じて率い、源氏は源義経を総大将として激戦。 平氏は敗れ、知盛ら一族の多くが戦死し、二位尼は安徳天皇を抱いて入水、宗盛・建礼門院らは捕らわれて、平氏一門は滅亡。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 123年の休止の後、1980年に激しく噴火した |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 12月から2月にかけて、アフリカ内陸のサハラ(Sahara)地方から大西洋岸へ吹く、乾燥して焼け付くような砂混じりの熱風。
「ハルマッタン」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 12~16世紀ころ、沖縄や奄美大島など南西諸島で造られた石垣囲いの遺跡。
立地場所・規模・構造などは多様で、現在のところグスクの性格の定説はない。多くは高所に造られ、按司(アジ)の住居、戦闘のための山城や、祭祀用の小型のものなどがある。 「ぐしく(グシク)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1457年蝦夷地のアイヌ人の蜂起(ホウキ)。
北海道東部に勢力をふるっていたアイヌの首長コシャマインが、渡島半島の南部を征服していた安東氏と対立し、1456(康正 2)反乱を起こし、多くの和人の館を攻め落とす。 翌年、蛎崎(カキザキ)氏の客将武田信広が平定。信広は功により蛎崎氏の家督を受け継ぐ。 「コシャマインの乱(胡奢魔尹の乱)」とも呼ぶ。牟奢允の戦い) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1545~1546(天文14~15)武蔵国河越で行われた後北条氏と上杉氏の合戦。
1537(天文 6)扇谷(オウギガヤツ)上杉朝定(トモサダ)は北条氏綱・氏康(ウジヤス)父子に本拠河越城を攻め落とされ、松山城に退く。1541(天文10)氏綱が没し、扇谷上杉朝政が攻めるが敗退。 勢力の回復をはかる朝定は山内上杉憲政(ノリマサ)(関東管領)・足利晴氏(ハルウジ)(古河公方)の援けを得て、1545(天文14.10.)福島(北条)綱成が守る3千の河越城を総勢8万余騎の大軍で包囲する。 翌年春、氏康が今川氏親と争っているのに乗じて朝定らは兵糧の尽きた落城寸前の川越城を攻める。氏康は8千騎を率いて援軍に駆けつけ、 4.20夜陰に乗じて襲撃し、城兵も降参を装って夜襲(河越の夜討)。 上杉・足利の連合軍は敗走し、混乱の中で朝定は戦死して、扇谷上杉は滅んだ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 15世紀にアルプスに住む修道僧が考えたといわれる外側に大きなバックルのついた靴。靴ひもでは無く、ベルトとバックルで甲の高さを調節できる機能的なデザインが特徴。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 15世紀中頃(明代)の西モンゴルのオイラート部族長(?~1454)。
父トゴン(Toghon Tayisi)の跡を継ぎ、元の子孫トクダ・ブハ(Toghto Bukha)を擁して、中央アジアから朝鮮に接する大版図(ダイハント)を築く。南下して明に侵入し、1449年土木堡(Tumu-bao)(河北省)で明軍を破り正統帝(Zhengtong Di)(英宗)を捕え(土木の変)、有利な講和を結ぼうとしたが、弟の景泰帝(Jing-tai Di)(景宗)が即位し于謙(Yu Qian)が北京城を死守したため、翌年正統帝を送還。 1451年トクダ・ブハを殺して大元天聖大可汗(Dayuan Tian-sheng Dakehan)と号した。 のち内訌(ナイコウ)のため部下に殺された。 「エセン(也先)」,「エセンタイジ(Esen Taiji)(也先台吉)」とも呼ぶ。変) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1611(慶長16.12. 2)三陸北部沖以南の日本海溝寄りを震源地とする推定マグニチュード8.1の地震による津波。
午前9時ころと午後2時ころの2回の大きな地震があり、2回目の地震に伴う津波が大きかった。 津波で東北地方を中心に約5千人が死亡。 「慶長奥州津波」とも呼ぶ。くつなみ(昭和三陸津波) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1657(明暦 3. 1.18~20)江戸市街の約6割を焼き尽した大火事。
火元は本郷丸山町の本妙寺で、施餓鬼(セガキ)に焼いた振袖(フリソデ)が空中に舞い上がり本堂に燃え移ったためといわれる。 江戸町奉行石谷貞清(イシガヤ・サダキヨ)、伝馬町牢屋敷の囚人を解き放つ。 江戸城本丸なども焼失し西丸が残るのみであり、大名屋敷も多くが焼失した。 大雪も襲来して餓死する者も多く、死者は10万余人で、本所に回向院(エコウイン)を建てて無縁仏の霊を祀る。 幕府は市街の復興に際し、「寛永の町割り」と呼ばれた配置を廃し、大名屋敷や寺社を郊外に移し市街地を本所・深川に拡大、火除明地(ヒヨケアキチ)を設けて道幅を広げ家屋の規模を定め、大橋(両国橋)を設けるなどの防災措置(ソチ)をとった。 1658(万治元)定火消(ジョウビケシ)(幕府方消防隊)四組を設ける。 「振袖火事(フリソデカジ)」,「丸山火事」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 16~17世紀、ヨーロッパで流行した男子用半ズボン。
腿(モモ)までの長さで、詰め物で大きくふくらませていた。カボッカーズ),ちょうちんぶるまー(ちょうちんブルマー,提灯ブルマー) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1807(文化 4)ティルジット条約によりナポレオンが建国した公国の一つ。
おもにプロイセンが領有した旧ポーランド領に建設。ザクセン王フリードリヒ・アウグスト(Friedrich August)が大公となる。 1809(文化 6)オーストリアと戦い、オーストリア領ポーランドも回復。 1814(文化11)ウィーン会議によりプロイセン・ロシアなどに再分割されて消滅。とふぁりあこうこく(ウェストファリア公国) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1808(文化 5. 8.)イギリス軍艦フェートン号(the Phae-ton)がオランダ国旗を掲げて長崎港に不法侵入した事件。
同艦に赴(オモ)いた長崎奉行所役人・通詞・オランダ商館員を捕(トラ)らえて薪水・食糧などを強要し、引き換えに人質を解放して出港・退去した。 ナポレオン戦争でイギリスとオランダが敵対関係になっていたことから、フェートン号は長崎に入港する予定のオランダ商船拿捕(ダホ)のため待ち構えていたが、商船が察知して現れなかったため薪水・食糧が少なくなっていたもの。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1834(天保 5)横山丸三(マルミツ)が、天海(テンカイ)の天源術(テンゲンジュツ)を基に創始した開運の教義。
人は受胎した年月日のそれぞれの干支(三輪)や人相・骨相などに応じて各自宿命を負っているが、修行によって生来の気質(悪癖)を矯正することにより、心身・気血の運行がよくなり、宿命を打破して開運・幸福に至らしめるという。 単に「淘宮」とも、「淘道」とも呼ぶ。いしんはちじ(生辰八字) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1857. 5.(安政 4)に起きたインド最初の反英戦争。
19世紀初頭以来、インド人の反英意識が高まり、これがセポイにも影響。イギリス軍の弾薬筒に牛・豚の脂を使用しているとのうわさが流れたのが誘因となって、北インドのメールト(Meerut)のセポイが武装反乱を起してデリーを占領。数ヶ月後には農民・封建土侯も合流し北インド全域に拡大。ムガール帝国の皇帝を擁立したが、人望がなかっため反乱軍の内部が分裂、イギリス本国から派遣された軍隊の出動によって1859. 7.(安政 6)ようやく鎮定された。 この結果、ムガール皇帝が廃されてムガール帝国は滅亡し、インド統治権が東インド会社の手からイギリス本国政府の直接支配に移された。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1868(慶応 4.閏4.)古代官制にならって政体書(セイタイショ)により設置された七官(シチカン)の一つ。神社・祭祀(サイシ)行政をつかさどった中央官庁。
幕藩体制の支配機構の一環をなしていた仏教を排斥する方針をとった。神仏判然を令し、天皇を崇拝する神道国教化を画し、はげしい排仏毀釈(ハイブツキシャク)に発展した。1871(明治 4)寺請け制にかわる氏子調べを発布したが、実効がとぼしく2年余で廃止された。 新政府の基礎が確立されるにしたがい、祭政一致のイデオロギーが後退し、1871(明治 4)神祇省に格下げされ、1872(明治 5)神祇省が廃止、教部省が設置され事務の一部は式部寮にも移管。 さらに1877(明治10)内務省に合併された。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1868. 3.(慶応 4)(明治元年)神仏分離令が出されると、各地で仏像・仏具の破壊や経文を焼くなどの廃仏毀釈運動が起きた。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1871. 9.13(明治 4. 7.29)日本と清国で調印された最初の条約。
日本の開国以来、日清間の交流が盛んになったため、日本側から発議。日本政府は欧米列強にならって清国と不平等条約を結ぶ方針で、1871. 6.(明治 4. 4.)大蔵卿伊達宗城(ムネナリ)を欽差全権大臣・外務大丞柳原前光および権大丞津田真道を副使に任命し、使節一行は 7.24(陰暦 6. 7)天津(Tianjin)に到着。 日本側は不平等の条約案を提議したが、清国欽差全権大臣李鴻章(Li Hongzhang)(リ・コウショウ)は自国の提議した対等の条約案を基本にすることを強硬に主張した。伊達全権は日本案を撤回し商議して、天津の山西会館で調印した。 この修好条規は、日本にとって最初の完全な対等条約となった。内容は両国の修好と相互援助、両国民の貿易許可、領事裁判権の相互承認など全文18条から成る。 しかし、政府の指令に背き締結したこと、両国の開港場での刀剣の携帯を禁止していたことは1876(明治 9)廃刀令以前であり不満が多く、一方米仏などアジアの植民地化を推し進める列強にとっては日清の攻守同盟と受け取られ相互援助の条項の削除を希望されるなどで批准されなかった。 そこで間もなく柳原前光を少弁務使として清国に派遣し条約の改訂を交渉したが、李鴻章は日本の不信を痛感しこれに応ぜず、公式に発効しないまま日時が経過し日清戦争に至った。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1874(明治 7)江藤新平が中心となり、島義勇(ヨシタケ)の率いる憂国党と結んで佐賀で蜂起(ホウキ)した反政府士族の反乱。
前年旧士族階級の家禄を確保しようとする征韓論争に敗れて下野した参議の一人江藤新平は、家禄奉還制度が公布されるにいたって蜂起、一連の士族の反乱の最初となった。 征韓・旧制度復古・攘夷をスローガンとしたが、同じく征韓論で下野した旧参議西郷隆盛らの応援もなく政府軍に鎮圧され、江藤は土佐で、島は鹿児島で逮捕処刑された。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1875. 9.(明治 8)江華島事件の結果、締結された条約。
1876. 2.27(明治 9)調印、日本天皇の批准は 3.22。 朝鮮の開国、元山・仁川が開港、京城に日本公使館を置くことが定められた。 「江華条約(the Kanghwa Treaty)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1878(明治11)ヨーロッパ列強とトルコの代表がバルカン半島の国際関係調整のため開催した国際会議。
ベルリンにイギリス・ロシア・ドイツ・オーストリア・フランス・イタリア・トルコなどの代表が会し、露土戦争の結果成立したサンステファノ条約を修正し、議長ビスマルクのたくみな調停でベルリン条約が成立。 ロシアのバルカン南下政策は阻止された。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1878. 3.23(明治11)近衛砲兵第1大隊の兵士260余名がおこした反乱事件。
西南戦争の恩賞が下士・兵卒になく減給まであったが、その不公平を訴えても将校が取り上げず、竹橋兵営の兵士は三添卯之助・小島万助らに指導され、大隊長・週番士官を殺害して蜂起(ホウキ)。大砲を引き出し、参議大隈重信の屋敷に発砲。直ちに鎮圧されて死刑53名・准流刑118名。 事件後、軍人に対し陸軍卿山県有朋の名で軍人訓誡(クンカイ)が発布され、「軍人勅諭(チョクユ)」の先駆となる。 「竹橋騒動」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1882. 7.(明治15)「高宗19」朝鮮の首都漢城(ソウル)で起きた軍人たちの暴動。
親日的な開化派の閔妃(ビンビ)政権の軍制改革に反対して、旧式軍制の軍人が起こしたもので、日本人の軍人教官を殺害。官庁や王宮(昌徳宮)を襲撃し、さらに漢城の日本公使館を焼き打ちする事件に発展。暴動に乗じた大院君(タイインクン)が王宮に迎えられ、閔妃は忠清北道忠州に逃れた。 日本は軍艦3隻と3,000人の兵を仁川に、アメリカも軍艦を派遣。清国は宗主国として属邦の保護を名目に軍艦3隻と4,500人の兵を派遣。清国軍により鎮圧、大院君を捕らえ河北省(He-bei Sheng)(カホクショウ)保定府に拉致(ラチ)幽閉、閔妃政権が復活した。 この結果、同年八月に済物浦(サイモッポ)条約が締結された。清国はそのまま漢城に軍を駐留。袁世凱(エン・セイガイ)を駐紮(チュウサツ)朝鮮総理交渉通商時宜として駐在させ事実上の国王代理として実権を握り朝鮮支配を強化した。 「壬午事変」,「壬午軍乱(ジンゴグンラン)([朝]Imogunran)」とも呼ぶ。(甲申の変),かんろみつやくじけん(韓露密約事件) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1886(明治19)帝国大学令に基づく旧制の国立総合大学。
略称は「帝大」。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1891.10.28(明治24)濃尾地方(岐阜県・愛知県)に発生した大地震。
マグニチュード8.4。死者7,273人、負傷者約1万7,000人。建物全壊142,177、半壊80,184、山くずれ1万余。 岐阜県南西部の本巣郡(モトスグン)根尾村(ネオムラ)(現:本巣市)付近が震源となって、根尾谷断層(ネオダニダンソウ)が生じた。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1894. 8.~1895. 3.(明治27~28)日本と清国との間で行われた戦役。正称は「明治二十七八年戦役」。
1894. 2.(明治27)韓国の東学党の乱(甲午農民戦争)で李朝は清朝に鎮圧を要請したが、清の出兵に応じて日本も派兵。反乱平定後に日・清が対立。 1894. 7.(明治27)日本艦隊が豊島沖で清国艦隊を攻撃して勝利。 1894. 8. 1(明治27)日清相互が宣戦布告。9月、黄海(Huang Hai)(コウカイ)で日本連合艦隊と清国北洋艦隊が戦い、清国は5艦を失って、以後日本が制海権を握る(黄海海戦)。11月、旅順(Lyushu)(リョジュン)占領。翌2月、威海衛(Weihaiwei)(イカイエイ)占領、北洋艦隊降伏。 1895. 3.(明治28)清国講和全権李鴻章(Li Hongzhang)(リ・コウショウ)が来日し、30日休戦条約が調印、 4.17日清講和条約(下関条約)が調印、 5. 8批准書の交換。じょうやく(日英通商航海条約),ねむれるしし(眠れる獅子)(1),こうか(黄禍) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 18世紀から広く使われていた、細い丸材を用いた背の高い木製の椅子(イス)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1916(大正 5)本多光太郎・高木弘が発明した特殊鋼。
鉄にコバルト・クロム・タングステン・炭素を含ませた磁石鋼で、保磁力の非常に強く、当時は世界的な発明であった。 第一世界大戦で優良な鉄鋼の輸入が中で住友財閥から出資を得て完成したもの。 「KS磁石鋼(KS magnetic steel)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1919(大正 8)創設された文部省所管の美術行政機関。
おもな事業は帝国美術院展覧会(帝展)を開くことで、これにより在野の団体を官展に吸収しようとしたが失敗。 1937(昭和12)官制を改め帝国芸術院を創立。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1919. 3. 1(大正 8)から約3ヶ月続いた朝鮮民族の日本支配に対する三・一独立運動の最中、同年4月、上海に亡命した金九(Kim Ku)(キム・グ)たちにより樹立。
財政難や内紛により弱体化し、1926(大正15)拠点を杭州市に移す。 1927(昭和 2)金九が国務総理となる。1928(昭和 3)韓国独立党が組織される。 1940(昭和15)韓国光復軍が組織され、1941(昭和16)大日本帝国に宣戦布告するが一度も交戦することはなかった。 李承晩(リ・ショウバン)が国務総理となるが、間もなく派閥抗争で失脚。 サンフランシスコ平和条約の際に韓国は戦勝国としての参加を希望したが、連合国が臨時政府を承認しておらず、また日本軍と交戦した事実もなかったことから米英などから拒絶されている。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1919.12.31(大正 8)阿片局主事の小畠庄二郎(オバタ・ショウジロウ)が関東州内の普蘭(フラン)店に行くと称し、阿片入りのトランクを持って無検査で長春行きの列車に乗ったが、発車間際にトランクを奉天(ホウテン)送りに変更させる。そしてトランクの合鍵を同じ列車に乗った前樺太長官の平岡定太郎(ジョウタロウ)に渡し、その現場を巡査に捕り押えられる。
翌年、野党により択殖局長官古賀廉造(レンゾウ)とその腹心関東庁民政局長中野有光(アリミツ)による阿片の密輸出ではないかと追及される。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1920(大正 9)インドで発見された二人の少女、アマラ(Amala)(~1921. 9.21)とカマラ(Kamala)(~1929.11.14)。
保護時、アマラは1歳半くらい、カマラは8歳くらい。裸で、話を理解できず、食事も手を使わずに皿から直接食べていた。 のち、カマラは少しの会話をしたり、服も着るようになった。 牧師ジョセフ・シング(Joseph Amrito Lal Singh)(~1941)が報告。 人間らしさは先天的・遺伝的なものではなく、人間社会に暮らして初めて形成されることを知る出来事であった。 オオカミに育てられていたすることは疑問視されている。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1920年代にアメリカ合衆国の経済や社会が大きく揺れ動いた時代の表現。
第一次世界大戦終結で経済は停滞し、禁酒法でギャングは横行。1929.10.(昭和 4)にはウォール街の株価が大暴落し世界恐慌となった。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1922. 2. 6(大正11)ワシントンで締結された中国に関する条約。
イギリス・アメリカ・フランス・イタリア・日本・オランダ・ベルギー・ポルトガル・中国が調印。 一国が中国での利益独占を防止するため、中国の主権尊重・領土保全・門戸開放・機会均等などを規定。 「くこくじょうやく(九国条約)」,「中国九ヶ国条約」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1925. 4.22(大正14)公布された思想・結社の弾圧法規。
国体の変革・私有財産制度の否認を目的とする結社活動および個人的行為に対する処罰を内容とする法律。〈制定〉 第一次世界大戦後の社会主義運動・農民運動・労働運動の発展に対処し、反体制運動(主として共産主義運動)の弾圧を目的に制定。 第1次加藤高明内閣(護憲三派内閣)が立案し、1925. 3.(大正14)普通選挙法と同時に制定・公布。「国体ヲ変革シ、私有財産制度ヲ否認セントスル」結社・運動を厳禁し、違反者には懲役10年以下の刑を科した。〈改訂など〉 田中義一内閣は改正案の議会承認を経ずに緊急勅令のかたちで1928. 6.29(昭和 3)改正を公布、即日施行。同年の三・一五事件で日本共産党に対する大量検挙に従い、刑をきびしくするように改訂され、死刑が付加された。 1936. 5.29(昭和11)思想犯保護観察法、公布。 1941. 3.10(昭和16)予防拘禁が追加された改正治安維持法が公布。反政府・反軍部に拡大解釈されて適用された。ぼうこうきん(予防拘禁),とくべつこうとうけいさつ(特別高等警察)〈廃止〉 GHQの司令により、1945.10.15(昭和20)勅令575号が公布施行されて廃止。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1929. 4.16(昭和 4)治安維持法適用により行われた日本共産党員大量検挙事件。
前年の三・一五事件でもれた幹部を追跡し、田中義一内閣によって1道3府16県の全国規模で一斉に行われ、約6百名を検挙。引き続き市川正一・鍋山貞親・佐野学ら幹部を逮捕。起訴者は339名。 「よんいちろくじけん(四・一六事件)」とも呼ぶ。(三・一五事件) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1931(昭和 6)井上中将が出動する際、自害した夫人のこと。
大阪三七連隊が満州出動の際、井上中将夫人が「心残りなく戦って下さい」という遺書をしたため、一尺二寸の短刀で自害し、「軍国の妻の鑑(カガミ)」と謳(ウタ)われた。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1932. 1.28(昭和 7)。5月まで続く。
抗日運動の弾圧を目的に軍隊を上陸させたが、強力な抵抗に屈して失敗。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1933. 3. 3(昭和 8)三陸沖地震で発生した津波。
綾里湾に25メートルの津波が襲来(シュウライ)。りくつなみ(慶長三陸津波) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1936. 2.26(昭和11)陸軍の皇道派青年将校らが国家改造を図って東京で起したクーデタ事件。
前日から雪が降るなか、皇道派青年将校らは歩兵第一・第三・近衛第一師団歩兵第三各連隊千4百余名の部隊を出動させて首相官邸・国会・参謀本部・陸軍省・警視庁などを占拠(センキョ)する一方、牧野伸顕・斎藤実(マコト)内大臣・岡田啓介・高橋是清大蔵大臣・渡辺錠太郎(ジョウタロウ)教育総監ら重臣を殺害、鈴木貫太郎(カンタロウ)侍従長に重傷を負わせる。 翌日戒厳令東京市に公布、九段の軍人会館に厳戒司令部が設置され、陸軍中将香椎浩平(カシイ・コウヘイ)が司令官となる。陸軍当局は収拾策を持たなかったが、海軍側の強硬鎮圧方針や昭和天皇の意向・財界の不支持をみてとり、蜂起部隊を叛乱軍と規定して武力鎮圧に乗り出し、下士官以下は帰順し 2.29無血で鎮定。 首謀者とその理論的指導者の北一輝(キタ・イッキ)は死刑となる。厳戒令は叛乱軍将校の死刑執行直後の 7.18まで続く。 事件後、岡田啓介内閣が倒れ、3月近衛文麿が組閣を辞退、5月広田弘毅の挙国一致内閣が成立。軍部大臣現役武官制が復活公布され、政治の中枢への軍部介入が一段と強化された。う(日本改造法案大綱),ていじんじけん(帝人事件),しゃかいたいしゅうとう(社会大衆党) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1938. 5.21(昭和13)未明、岡山県の山奥の集落で発生した30人殺害事件。
苫田郡(トマタグン)西加茂村(ニシカモソン)大字行重(ユキシケ)字貝尾部落に住む都井睦雄(トイ・ムツオ)(1917. 3. 5~1938. 5.21)が20歳の徴兵検査で肺結核によって丙種合格となり、回りから冷たくされ犯行を計画。後日、猟銃・日本刀などを用意して決行。犯行後に自殺。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1940年代後半に死海の近くの洞窟で発見された(旧約聖書をほとんどすべて含む)巻物の集まり |
| 91件目から120件目を表示 | < 前の30件 | | | 次の30件 > |