"明"がつく3文字の言葉
"明"がつく3文字の言葉の一覧を表示しています。 検索結果が多い場合は文字数で絞ることが可能です。 文字数は検索結果となる文字の文字数のボタンを押してください。| 1件目から30件目を表示 | 次の30件 > |
| 言葉 | 下神明 |
|---|---|
| 読み | しもしんめい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ | 駅 |
(1)東京都品川区にある東急大井町線の駅名。
| 言葉 | 不分明 |
|---|---|
| 読み | ふぶんめい |
| 品詞 | 形容詞 |
| カテゴリ |
(1)正確に制限、決定または区別されない
(2)明確に理解されないか、または表現されない
(3)明快さまたは特異性が不足しているさま
(4)スタイルまたは表現での困難さによって強調される
(5)not precisely limited, determined, or distinguished
| 言葉 | 不明朗 |
|---|---|
| 読み | ふめいろう |
| 品詞 | 形容詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 不明瞭 |
|---|---|
| 読み | ふめいりょう |
| 品詞 | 形容詞 |
| カテゴリ |
(1)明確に定義されていない、または感知するあるいは理解することが容易ではない
(2)明快さまたは特異性が不足しているさま
(3)心には、明確ではない
(4)不完全に示されるか、または記述されている
(5)一般的なパターンで構成されていない
| 言葉 | 不明瞭 |
|---|---|
| 読み | ふめいりょう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)複数の意味を持つために不明瞭であること
(2)未解決の、未決定の、または偶然の
(3)不明瞭であり、鮮明な輪郭のない性質
(4)十分な光がないため不明瞭ではっきりしない状態
(5)不明瞭で、難解で、理解しにくい性質
| 言葉 | 不透明 |
|---|---|
| 読み | ふとうめい |
| 品詞 | 形容詞 |
| カテゴリ |
(1)視界を通さない
(2)確かな形または制限を欠くさま
(3)光、放射エネルギーを送らない、あるいは反射しない
(4)not transmitting or reflecting light or radiant energy; impenetrable to sight; "opaque windows of the jail"; "opaque to X-rays"
| 言葉 | 不透明 |
|---|---|
| 読み | ふとうめい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)度が不透明である品質
(2)何かが光の通過を減少させる度合い
(3)不透明な性質
(4)the quality of being opaque to a degree
(5)the quality of being cloudy
| 言葉 | 不透明 |
|---|---|
| 読み | ふとうめい |
| 品詞 | 副詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 不鮮明 |
|---|---|
| 読み | ふせんめい |
| 品詞 | 形容詞 |
| カテゴリ |
(1)一般的なパターンで構成されていない
(2)アウトラインが不明瞭、あるいはかすんでいる
(3)どんな固有のまたは客観的な意味も持っていないさま
(4)明快さまたは特異性が不足しているさま
(5)明確に定義されていない、または感知するあるいは理解することが容易ではない
| 言葉 | 光明寺 |
|---|---|
| 読み | こうみょうじ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ | 駅 |
(1)福井県永平寺町にあるえちぜん鉄道勝山永平寺線の駅名。
| 言葉 | 光明星 |
|---|---|
| 読み | こうみょうせい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 光明池 |
|---|---|
| 読み | こうみょういけ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ | 駅 |
(1)大阪府堺市南区にある大阪府都市開発泉北高速鉄道線の駅名。
| 言葉 | 公文明 |
|---|---|
| 読み | くもんみょう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ | 駅 |
(1)香川県三木町にある高松琴平電気鉄道長尾線の駅名。
| 言葉 | 公明さ |
|---|---|
| 読み | こうめいさ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 公明党 |
|---|---|
| 読み | こうめいとう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)創価学会を母体に発足した政党。
党本部は東京都新宿区南元町(ミナミモトマチ)。〈歴代代表〉
神崎武法:1998.11.~。
太田昭宏:2006. 9.30~。
| 言葉 | 円明園 |
|---|---|
| 読み | えんめいえん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)中国、北京の西北郊にあった清朝の離宮。
暢春園(Changchun Yuan)(チョウシュンエン)(のち静明園
中国最初のバロック様式を加えた大噴水をもつ宮殿で、世界一の名園といわれる。
| 言葉 | 円明寺 |
|---|---|
| 読み | えんみょうじ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)京都府京都市右京区花園仁和寺付近、仁和寺の西南方にあった寺。四円寺(シエンジ)の一つ。
姉妹サイト紹介

| 言葉 | 半透明 |
|---|---|
| 読み | はんとうめい |
| 品詞 | 形容詞 |
| カテゴリ |
(1)光を散慢に通過させる
(2)allowing light to pass through diffusely; "translucent amber"; "semitransparent curtains at the windows"
| 言葉 | 半透明 |
|---|---|
| 読み | はんとうめい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 史思明 |
|---|---|
| 読み | ししめい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)中国唐代の武将(?~ 761)。安史の乱の主謀者。
営州(Yingzhou)(今の遼寧省)出身のトルコ(突厥)系の胡人で、同郷の安禄山(An Lushan)(アン・ロクザン)の親友。
6ヶ国語を使い貿易官となり、のち軍人となる。
755年禄山が挙兵すると河北を攻略し、禄山の死後、唐に帰順して河北節度使となる。
758年唐に対して反乱を起こし洛陽(Luoyang)を陥れ、 759年安禄山の子の慶緒(Qingxu)を殺して大聖燕王(Dasheng Huan-wang)と称したが、やがて子の史朝義(Shi Chaoyi)に殺された。の亂)
| 言葉 | 四明公 |
|---|---|
| 読み | しめいこう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)(『真誥(シンコウ)』闡幽微)四方の鬼を主領する東明公・西明公・南明公・北明公の総称。
| 言葉 | 四明山 |
|---|---|
| 読み | しめいざん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 四明岳 |
|---|---|
| 読み | しめいがたけ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 夜明け |
|---|---|
| 読み | よあけ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)開店時間
(2)日の出
(3)the first light of day
(4)an opening time period; "it was the dawn of the Roman Empire"
| 言葉 | 大明寺 |
|---|---|
| 読み | だいみんじ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)中国東部、江蘇省(Jiangsu Sheng)(コウソショウ)揚州市(Yangzhou Shi)にある仏教寺院。
鑑真紀念堂がある。
| 言葉 | 大明日 |
|---|---|
| 読み | だいみょうにち |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)暦注の一つ。陰陽道(オンミョウドウ)で、万事に大吉であるとする日。
単に「大明(ダイミョウ)」とも呼ぶ。
| 言葉 | 天明町 |
|---|---|
| 読み | てんめいまち |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)熊本県飽託郡(ホウタクグン)にあった町。熊本市の南部、島原湾に臨む。〈面積〉
19.28平方キロメートル。〈人口〉
1970(昭和45)1万0,921人。
姉妹サイト紹介
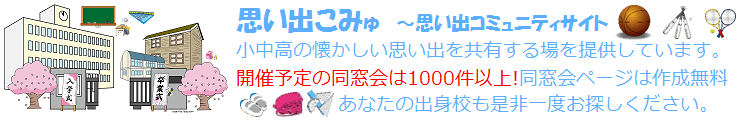
| 言葉 | 孔明灯 |
|---|---|
| 読み | こうめいとう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)中国の三国時代の軍師、諸葛亮(ショカツ・リョウ)孔明が夜間連絡のために発明したという熱気球の一種。
春節(旧正月)・結婚式などのお祝いの夜、紙風船にロウソクを入れ、その熱気で空に飛ばすもの。
「天灯(tiandeng)」とも呼ぶ。
| 言葉 | 岱明町 |
|---|---|
| 読み | たいめいまち |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)熊本県北部、玉名郡(タマナグン)の町。東部を玉名市、北西部を荒尾市に接し、南西部は有明海(アリアケカイ)に面する。〈面積〉
22.81平方キロメートル。〈人口〉
2000(平成12)1万4,609人。
| 言葉 | 川明き |
|---|---|
| 読み | かわあき |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)川で魚を獲(ト)ることが解禁されること。
陰暦六月一日の京都鴨川のアユ漁解禁が有名。
「かわあけ(川明け,川明)」とも呼ぶ。
(2)江戸時代、川止めになっていた河川の水が引き、旅人などの川越(カワゴ)しが許可になること。川止めが解(ト)けること。 「かわあけ(川明け,川明)」とも呼ぶ。
| 1件目から30件目を表示 | 次の30件 > |