「守護」に関係する言葉
「守護」に関係する言葉の一覧を表示しています。 検索結果が多い場合は文字数で絞ることが可能です。| 1件目から30件目を表示 | 次の30件 > |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 『法華経』「陀羅尼品」に説く法華経の守護神。
尼藍婆(ニランバ)・毘藍婆(ビランバ)・曲歯(キョクシ)・華歯(ケシ)・黒歯(コクシ)・多髪(タホツ)・無厭足(ムエンソク)・持瓔珞(ジヨウラク)・皐諦(コウタイ)・奪一切衆生精気(ダツイッサイシュジョウセイキ)の総称。 鬼子母神の娘といわれ、始め人の精気を奪う鬼女であったが、仏法に接し、鬼子母神らとともに、法華行者を守る神女となった。 「十羅刹女神(ニョシン)」,「普賢十羅刹」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | もとはバラモン教のマヘーシュヴァラ(Mahesvara)神で、仏法の守護神として取り入れられた六天身の一つ。
「摩醯首羅(マケイシュラ)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | もとはバラモン教の神々であったが、仏教に取り入れられてその守護神となったもの。
梵王(ボンオウ)身・帝釈(タイシャク)身・自在天(ジザイテン)身・大自在天(ダイジザイテン)身・天大将軍(テンダイショウグン)身・毘沙門(ビシャモン)身の総称。 <1>梵王身:バラモン教の創造神ブラフマン(梵天)のこと。 <2>帝釈身:バラモン教の主神インドラのこと。 <3>自在天身:バラモン教のマヘーシュヴァラ神のこと。 <4>大自在天身:同上。訳経者が異称を別神としたものらしい。 <5>天大将軍身:バラモン教で、天上の諸王を助ける大将軍。 <6>毘沙門身:バラモン教の北方の王。四天王の一つ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | もとインド舎衛城(シャエジョウ)の祇園精舎(ギオンショウジャ)の守護神。また東方浄瑠璃世界(ジョウルリセカイ)の薬師如来の垂迹(スイジャク)(化身)といわれる。
武荅王(ムトウオウ)の太子で、頭上に牛の角または牛の頭を持ち、形は人間に似て夜叉(ヤシャ)の如く忿怒相に表される。沙竭羅竜王(サカラリュウオウ)の女を后として八王子を生む。 猛威のある御霊的神格から日本では素戔嗚尊(スサノオノミコト)に習合され、除疫神として京都の八坂神社(祇園社)などに祀(マツ)られ尊崇された。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アイルランドの守護聖人( 389?~ 461?)。
ブリタニア(ブリテン島)生れで、アイルランドで伝道してキリスト教化の基礎を築く。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アテーナ(守護神である女神)から名付けられた |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | イングランドの守護聖人 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | キリスト十二使徒の一人(?~AD. 60ころ)。
ペテロ(シモン)([英]Simon Peter)の兄弟。 スコットランドの守護聖人。 祭日は11月30日。 「聖アンドルー」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | キリスト教の殉教者で旅人の守護聖人(3世紀) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | シチリア(Sicilia)で殉教した聖処女(AD. 283ころ~ 304ころ)。
イタリアの都市ナポリの守護神。 祝祭日は12月13日。 英語読みで「サンタルシア(Santa Lucia)」とも、「シラクサのルチア(Lucia da Siracusa)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | トールの妻で家庭の守護神 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | バラモン教の天上の諸王を助ける大将軍で、仏法の守護神に取り入れられた六天身の一つ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ベトナムの首都ハノイ北部のバーディン地区(Quan Ba Dinh)にあった城(11~18世紀)。〈昇龍四鎮〉
城の四方の守護神殿。 東:白馬(Bach Ma)を祀(マツ)る神殿はバックマー(Bach Ma)神殿。Bach Ma:White Horse。 西:リンラン大王(Linh Lang Dai Vuong)を祀るヴォイフック(Voi Phuc)神殿。Voi Phuc:kneeling elephant。 南:高山大王(Cao Son Dai Vuong)を祀るキムリエン(Kim Lien)神殿。Kim Lien:Golden lotus。 北:玄天鎮撫(Huyen Thien Tran Vu)を祀るクアンタイン(Quan Thanh)神殿。Quan Thanh:Holy Mandarin。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 三宝(サンボウ)を護持する国王を守護する大力のある五菩薩。菩薩であっても忿怒(フンヌ)尊の性格を持つ。
<1>金剛吼(コンゴウク)。 <2>竜王吼。 <3>無畏(ムイ)十力吼。 <4>雷電吼。 <5>無量力吼。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 中世、守護の代官。
守護の有力な家臣が任命され、守護に代って任国で守護の職務を行った。 2ヶ国以上を兼ねた守護や、鎌倉や京都にいて在国しない守護が設置。 室町中期以降、在地の武士である国人(コクジン)が被官(ヒカン)し、実力で主家(シュケ)に代って大名になるものが現れた。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 中国大陸南部の福建省(Fujian Sheng)(フッケンショウ)を中心とする沿海地域の漁民や台湾・東南アジアの華僑、ベトナム人に信仰されている道教の女性神。船乗りの守護神、安産の神。
旧暦九月九日に媽祖が昇天したとされ、マカオ(澳門)にある媽祖廟の天后宮で中国仏教協会による式典が行われる。 「マーツー(媽祖,馬祖)」,「ばそ(媽祖,馬祖)」,「阿媽(A Ma)」,「天妃(Tianfei)」,「天后(Tianhou)」,「天后聖母(Shengmu)」,「天后娘娘(Niangniang)」,「聖母娘娘」,「天上(Tianshang)聖母」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 九州と朝鮮の間にある島。浅茅湾(アソウワン)により南北2島(上島・下島)に分かれる。
古くから大陸交通の要地。 鎌倉時代、宗氏が守護代として支配。 江戸時代、宗氏の対馬藩(府中藩)が支配。 長崎県の対馬市を構成。〈面積〉 1961(昭和36)698平方キロメートル。 |
姉妹サイト紹介

| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 京都守護の別称。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 仏教の守護神の一つ。
大力を有し、悪を排し善を守護する。 ビシュヌ(毘紐天<ビチュウテン>)と同一視される。 「那羅延天」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 仏教守護神の天部(テンブ)の一分類。上下・日月・四方・四維(シイ)の方角の魔を封ずる守護神。
密教興隆に伴い、主に古来の婆羅門(バラモン)神が仏教に流入同化されたもの。 < 1>伊舎那天(イシャナテン)、東北。 < 2>帝釈天(タイシャクテン)、東。 < 3>火天(カテン)、東南。 < 4>閻魔天(エンマテン)・焔摩天、南。 < 5>羅刹天(ラセツテン)、西南。 < 6>水天(スイテン)、西。 < 7>風天(フウテン)、西北。 < 8>多聞天(タモンテン)・毘沙門天(ビシャモンテン)、北。 以上の「八天」に、後に以下の諸天が加わり、「十二天」となった。 < 9>梵天(ボンテン)、上。 <10>地天(ジテン)、下。 <11>日天(ニッテン)、日。 <12>月天(ガッテン)、月。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 仏法を守護するインドの四柱の神の総称。
帝釈天(タイシャクテン)の家来で、須弥山(シュミセン)に住み、四方を守る、持国天(東方を守護)・増長天(南方を守護)・広目天(西方を守護)・多聞天(タモンテン)(北方を守護)の4神。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 仏法守護神の八部衆(ハチブシュウ)の一つ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 兵隊を取締り、捕虜を守護する憲兵隊の一員 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 十二天の一つ、火を司る神・火神。もと古代インドの火神。
体は赤色、髪は白色、4本の腕に仙杖(センジョウ)・水瓶(スイビョウ)・三角印・数珠(ジュズ)を持ち、老いた苦行仙(クギョウセン)の姿で火焔のなかに坐し、通常青い羊を乗り物とする。 胎蔵界曼荼羅では外金剛部院に配されて東南方を守護する。 密教の護摩(ゴマ)修法(シュホウ)では、護摩壇を築いて火天を祀(マツ)り、護摩を焚いて祈祷する。その火は煩悩(ボンノウ)を焼き滅ぼす智恵の象徴とされる。 眷属(ケンゾク)に火天后・火天妃を持つ。 「火仙(カセン)」,「火光尊(カコウソン)」,「アグニ(阿耆尼,阿哦那)」,「阿耆尼(アギニ)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 古代ローマの家庭の守護神。
もとは耕作地の神。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 古代神話で結婚の守護神で豊穣の女神 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 四天王の一つ、六天身の一つ。日本では七福神の一人。
インドの神で、須彌山(シュミセン)の中腹の天敬城に住み北方をかため、憤怒の相を現わし、身に七宝で飾った甲冑(カッチュウ)をつけ、仏法を守護する武神。多くの夜叉(ヤシャ)・羅刹(ラセツ)を統率する。 「毘沙門」,「毘沙門天王」,「多聞(タモン)」,「多聞天」,「多聞天王(テンノウ)」,「大悲多聞天王」,「施財天(セザイテン)」とも呼ぶ。 |
姉妹サイト紹介
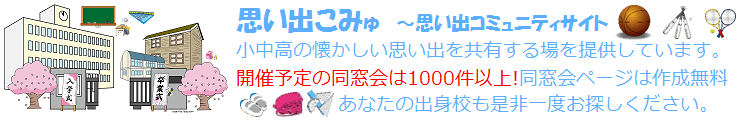
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 四天王の一つ。西方を守護するインドの神。
龍と冨單那(フタンナ)を足の下に踏み従えている。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 国家・民族・家(家族・親族)・個人・職業・寺院などを、災(ワザワ)いから守護する神。
「しゅごしん(守護神)」,「守り神(マモリガミ)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 埼玉県日高市(ヒダカシ)新堀(ニイホリ)の高麗郷(コマゴウ)にある、渡来人の高麗(コマ)一族の菩提寺。高麗山聖天院勝楽寺。
高麗王若光(コマノコキシジャッコウ)の菩提を弔うため、王の侍念僧勝楽と弟子が開く。本尊は王の守護仏であった聖天尊(歓喜天)。 最初、法相宗であったが貞和年間(1345~1350)真言宗となり、現在は新義真言宗。 奈良時代の創建で、現在の建物は四百年ほど前のもの。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 大蛇(ダイジャ)の形をした鬼神。のち仏法の守護神となり。八部衆(ハチブシュウ)の一神。
「摩呼洛伽(マコラガ)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 天界に住む神々の総称。仏教の守護神。
密教の神々で、そのほとんどが『胎蔵界曼荼羅(タイゾウカイマンダラ)』の外金剛部院に描かれている。その数200尊以上に及び、<1>天竜八部衆(ハチブシュウ)・<2>十二天・<3>星宿(セイシュク)に大別される。 「諸天(ショテン)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 奈良時代から戦国時代まで存在した、田地を中心とした私的所有地。〈墾田地系荘園(初期荘園)〉
743(天平15)墾田永世私財法により墾田の私有が認められると、初期荘園が発生し寺院などが公民を雇って墾田を開墾・耕作させた。また墾田を買収して集められた荘園もあった。〈寄進地系荘園〉 10世紀になると、国司や郡司の収奪から逃れるために在地の有力者は自分の土地を名義上、中央の権門・寺社にその荘園として寄進し、自らはその荘官となり権門・寺社を本所・領家と仰ぎながら実質的権益を留保した。寄進者は権門・寺社の保護の代償として、年貢・公事(クジ)・夫役(ブヤク)など一定の貢納物や労働力を提供した。寄進先は摂関家や院・皇室・大貴族に集中し、摂関政治や院政の経済的基盤となった。〈荘園整理令〉 10世紀初頭の醍醐天皇から12世紀前半の白河・鳥羽院政期にかけて荘園整理令がしばしば出されたが効果がなく、逆に11世紀半ばには全国的に荘園が増加し荘園制が発展した。〈荘園の消滅〉 鎌倉時代以降は武士が台頭し守護・地頭に侵略されて次第に衰退、16世紀末の太閤検地によって消滅した。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 子供たちの伝説的な守護聖人 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 室町中期、李氏朝鮮が対馬(ツシマ)に来襲した事件。
1392(<南>元中 9,<北>明徳 3)建国以来、倭寇(ワコウ)に悩まされていた朝鮮は対馬を倭寇の本拠地と目(モク)し、1419(応永26)太宗(第3代)の軍勢、兵船227・1万7,000人の大軍で襲撃。対馬守護宗貞盛(ソウ・サダモリ)の防戦にあい、まもなく撤退した。 のち、使者の相互派遣によって誤解が解け、1423(応永30)修好を回復。日朝貿易も宗氏の統制のもとに復活した。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 室町幕府の重職である管領に任じられる有力守護。
細川・畠山・斯波(シバ)の3家が交代で任じられた。 「さんかんりょう(三管領)」,「三管(サンカン)」,「三職(サンショク)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 室町時代後期、任国の強めて封建領主化した守護。
鎌倉末期から守護は職権を利用して任国内の武士をしだいに支配下に組み入れ、南北朝内乱期に半済(ハンゼイ)や守護請(シュゴウケ)などで荘園・国衙(コクガ)領を侵し、一国または数ヶ国を領して大名化したもの。 しかし、旧来の荘園所職(ショシキ)や幕府権力に依存し、国内武士への支配力の弱さから、応仁の乱(1467~1477)以後は没落して、守護代や国人(コクジン)が成長した戦国大名にとって代られた。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 宮内省内に皇室の守護神として祀(マツ)られていた神。
「そのかみ(園神)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 密教の『守護国界主陀羅尼経』で、法・報・応の三身(サンジン)に配したもの。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 寺の建立以前からその地に祀(マツ)られていて、のちその寺の守護神となった神。
寺を建立する地には、それ以前になんらかの神が祀られていることが多く、寺の鬼門などを守護する形式をとって寺(仏教)は進出を果たした。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 愛知県(旧:尾張国)清須市にあった城。
1405(応永12)尾張国・遠江国・越前国守護の斯波義重(シバ・ヨシシゲ)(1371~1418)が築城。 1476(文明 8)守護所の下津城が戦乱で焼失し、斯波氏の居城となる。 織田信秀(1510~1551)(織田信長の父)が守護代として居所とする。 1555(天文24. 4.)織田信長(1534~1582)が入城。 1576(天正 4. 2.)織田信長、安土城に移る。 1610(慶長15)徳川義直(1600~1650)が名古屋城を築城して廃城となる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 手に金剛杵(コンゴウショ)(vajra)を執って仏法を守護する神。
もとバラモン教の神で、仏法の守護神となったもの。 「しゅこんごうじん(執金剛神)」,「しっこんごうじん(執金剛神)」,「執金剛」,「金剛神」,「金剛手」,「執金剛身(シュウコンゴウジン)」,「執金剛夜叉(ヤシャ)」,「執金剛力士(リキシ)」,「金剛力士」,「密迹(ミッシャク)金剛」,「密迹力士」,「金剛」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 旧国名。山陽道八ヶ国の一国。現在の山口県の東部。国府は防府。
中世の守護は北条氏一門、次いで大内氏が支配。 のち近世(江戸時代)にかけて毛利氏の藩となる。 「ぼうしゅう(防州)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 本地垂迹説によって、日本国土を一ヶ月三十日間、毎日交替で守護するという三十体の神。
平安初期に天台宗で最澄が法華経を守護する神として祀(マツ)ったのに始まり、平安中期には一般信仰となって流布していた。 鎌倉時代には禁闕守護・仁王経守護・如法経守護・吾国守護など各種の三十番神が生れた。 鎌倉末期、日蓮宗僧日像(ニチゾウ)(1269~1342)により神天上(ジンテンジョウ)法門の一環として日蓮宗に取り入れ、日蓮宗独自の神祇信仰となった。 室町中期には吉田兼倶(カネトモ)により吉田家相伝とされた。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 東北地方、特に岩手県を中心に伝承されている、旧家に住むと信じられている家神。
髪を垂らして赤ら顔の童子(ドウジ)の姿をした精霊または妖怪で、その家の繁栄を守護するといわれるが、よくイタズラ(悪戯)をし、家人から嫌われて居なくなると家が衰えるという。 「座敷ぼっこ」,「くらわらし(蔵童,倉童)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 江戸幕末、京都守護職のもとで京都の治安に当たった浪士の警備隊。
1862(文久 2)幕府は清川八郎の建議を入れ、京都警護のため武芸に堪能な浪士を集めて浪士組を組織。翌1864(文久 4. 1.)上洛し間もなく隊長格の清川は尊皇攘夷を主張して一部を除いた隊士を率い東下し暗殺される。 京都に残った一派は同年1864(元治元. 3.)京都守護職松平容保(カタモリ)(会津藩主)の下で新撰組を再組織、隊長は芹沢鴨(セリザワ・カモ)。同年5月の池田屋事件に参加。同年9月、内紛で芹沢は斬られ、近藤勇(イサミ)・土方歳三(ヒジカタ・トシゾウ)が隊長・副長として実権を握り、尊攘・討幕派の志士の弾圧に活躍。 1868(慶応 4. 1. 3)鳥羽・伏見の戦に参加し敗れて四散。一部江戸に帰って甲州に出陣し新政府軍と戦って敗走し解隊。 |
| 1件目から30件目を表示 | 次の30件 > |