「糸」に関係する言葉
「糸」に関係する言葉の一覧を表示しています。 検索結果が多い場合は文字数で絞ることが可能です。| 1件目から30件目を表示 | 次の30件 > |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (guernsey)毛糸編みの厚いジャケット。特に船員用の青いもの。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([英]count)糸の太さを表す単位。
イギリス式で綿糸の場合、1ポンド(約454グラム)で1綛(カセ)を一番手、2綛を二番手、3綛を三番手、10綛を十番手と呼び、番手が大きいほど糸は細くなる。 綛は長さの単位で840ヤード、約768メートル。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (『淮南子(Huainanzi)(エナンジ)』説林)中国の戦国時代、墨子(Mozi)(ボクシ)が白い練り糸が黄色にも黒色にも染まるという話を聞いて泣いたという故事。
「墨子染(セン)を悲しむ」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)ツムギアリ属(Oecophylla)のアリの属名・総称。
樹上の枝先に葉をそのまま数枚寄せ集めて幼虫の吐き出す糸を使ってつなぎ合せて巣を作る。1つの群れで、その木の別の枝先や隣接する木の枝先などに数個~数十個の巣を作って生活する。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)布端に施した房(フサ)飾り。
布端の横糸を1センチメートルほど抜いたり、糸や毛糸を束ねて縫い付けたりしたもの。 肩掛け・テーブル掛け・幕の裾(スソ)などに用いる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1900(明治33)津田米次郎(ヨネジロウ)が開発した絹糸の力織機。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 2つの娘細胞の中に分離を引き起こす有糸核分裂に続く細胞質の細胞の分裂から成る有機的な過程 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 8本の脚、2本の毒牙、および2本の触角を持ち、通常は体の後部に糸を吐き出す2つの器官がある捕食性のクモ形類動物 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 「布地」の意。広義では、織物、編み物、不織布、狭義では、織物をいう。織り、編み、フェルト、レースで作られた布地や原料の繊維の総称。キャンパス生地:亜麻糸、綿糸、絹糸あるいは、それらの混織で、丈夫な厚手の粗布。クロスやカーテンに多く使用される。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | あなたが針と糸で取り組んでいる針仕事 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ある種の昆虫の繭の細い糸から作られる織物 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | きらきら光る金属箔を織り込んだ糸 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ざらめ糖(トウ)を綿状にした菓子。
ざらめ糖をやや濃い目に溶かした液を加熱した高速回転する円筒に入れて煮立たせ、円筒の細かな穴から吹き出させて、ふわふわとした極細い糸状にしたもの。食紅でピンク色にすることが多い。 吹き出たときに割り箸(バシ)に巻き取って、祭りや縁日などの出店(デミセ)で実演販売される。 割り箸を手に持って口にするとすぐに溶けてしまう食感を楽しむ。 「綿菓子(ワタガシ)」,「電気飴」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | たった1つの糸または2つの織物をとらえるゆるい縫い |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | つり針と糸で釣る(通常竿と一緒に) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | まっすぐで針穴のない編み針を使用して、または機械で、編み糸を一続きのつながった輪に絡み合わせて作成する手芸品 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アカマンボウ目(Lampridiformes)リュウグウノツカイ科(Regalecidae)リュウグウノツカイ属(Regalecus)の深海魚。
体長は5~10メートル。体形は側扁し、細長い。体色は銀白色でヒレは赤い。背ビレはトサカ状に伸び、腹ビレは糸状に長く伸びる。 全世界の水深200~1,000メートルに生息する。 |
姉妹サイト紹介

| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アサ(麻)の繊維を縒(ヨ)り合せて糸にすること。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アシ(葦、ヨシとも)の茎(クキ)を糸で編み列ねた簀(ス)。
窓などに垂(タ)らしたり、戸口に立て掛けたりして、日除(ヒヨ)けや目隠しに用いる。 「よしすだれ(葦簾,葭簾)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アンゴラヤギの絹のような毛から作られた糸で織った織物 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | イガイ目(Mytilida)イガイ科(Mytilidae)イガイ属(Myt-ilus)の海産の二枚貝。
岩礁などに足糸(ソクシ)で着生する。 「セトガイ(瀬戸貝)」,「カラスガイ(烏貝)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | イグサ(藺草)の茎を麻糸で織(オ)った蓙(ゴザ)。
畳床(タタミドコ)の上面に貼(ハ)って縫(ヌ)いつけるもの。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | イトトンボ(糸蜻蛉)の別称。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | イネ目(Poales)イネ科(Poaceae)のシバ属(Zoysia)の多年草。
葉は細く糸状で、内側にU字形に巻き、細長い溝のようになっている。 九州南部・沖縄県、台湾・華南・東南アジアに自生。 「チョウセンシバ(朝鮮芝)」,「イトシバ(糸芝)」,「ヒメシバ(姫芝)」,「ハリシバ(針芝)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | イネ目(Poales)イネ科(Poaceae)シバ属(Zoysia)の多年草。
コウライシバ(Zoysia pacifica)と同様に、葉は細く糸状で、内側にU字形に巻き、細長い溝のようになっている。 また普通のシバ(Zoysia japonica)やコウライシバに比べ、葉は細く密に生(ハ)える。 「チュウシバ(中芝)」,「ヒメコウライシバ(姫高麗芝)」,「チョウセンシバ(朝鮮芝)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | オ(麻・苧)を績(ウ)むこと。
アサ(麻)・カラムシ(苧)の茎から採(ト)った繊維を縒(ヨ)り合せて糸にすること。 「おみ(麻績)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | キチンと、キチンを熱濃アルカリ処理(N-脱アセチル化)して得られるキトサンの総称。
キチンは水に溶けず腐敗しやすいので、従来は利用されていなかったが、天然素材として応用され始めている。 健康食品として摂取されるほか、生体吸収性からは人工皮膚・外科用縫合糸として、抗菌・抗カビ性からは食品保存料・抗菌性繊維製品などとして、また粒状多孔性ゲル形成からイオン交換用材などに多方面に利用されている。 |
姉妹サイト紹介
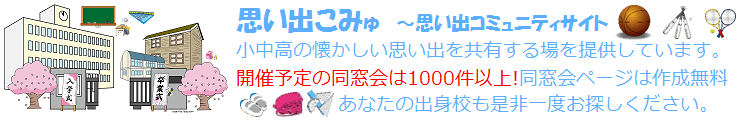
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | キンポウゲ目(Ranunculales)キンポウゲ科(Ranuncula-ceae)バイカモ属(Batrachium)の水生多年草(沈水植物)。
山地の清流中に自生。 葉は糸状に分裂し、夏に水中に長い花柄を出し、梅の花に似た白い五弁花を1週間ほど開く。水中花からは葉の光合成でできた比較的大きな酸素の泡が放出される。 「ウメバチモ(梅鉢藻)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | クレープ(crepe)とは撚りの強い糸を利用して織られた織物。表面に細かいしわやしぼ(波状の凹凸)が出るのが特徴で、表面の繊細な風合いがあり、吸水性・速乾性がある。シルク、レーヨン、綿、化繊で作られることが多い。クレープ・ジョーゼット、クレープ・デ・シン、楊柳(ようりゅう)クレープ、縮緬(ちりめん)等様々な種類がある。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | コケ、シダ、カビなどの根の役目を果たす様々な細長い糸状体の総称 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | シナノキ(科木)の樹皮から製した粗布。
樹皮のを晒(サラ)し、靱皮繊維(ジンピセンイ)を細く割いて糸にし、布に織ったもの。 布目は粗(アラ)く艶があり、色はやや赤黒く、水湿に堪える。 蚊帳(カヤ)や米穀用の科袋(シナブクロ)・船舶用の縄などに用いられた。 信濃国(現:長野県)で産したものは特に「信濃布(シナノヌノ)」と呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | シミ目(総尾目)(Thysanura)シミ科(Lepismatidae)に属する昆虫の総称。
原始的な昆虫で、翅(ハネ)はなく変態もしない。体は扁平(ヘンペイ)で細長く、一面に銀白色の鱗片(リンペン)でおおわれ、長い糸状の触角を持ち、尾端に二本の尾角と一本の尾毛がある。 温帯に広く分布し、約400種が知られる。主に屋内の乾燥した暗所を好み、本や衣類などのセルロース質や糊を食害する。洞穴や落葉の下に棲む種類やアリやシロアリと共生する種類もある。 日本全土や中国・東南アジアには体長10ミリメートル前後のヤマトシミが、朝鮮ではチョウセンシミ、ヨーロッパや北アメリカにはセイヨウシミがいる。 「しみむし」,「雲母虫(キララムシ)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | (1)リュウキュウイトバショウ | 詳しく調べる |
|---|---|
| 意味 | ショウガ目(Zingiberales)バショウ科(Musaceae)バショウ属(Musa)の大形多年草。
茎から繊維を採り、紡(ツム)いで芭蕉布(バショウフ)を織(オ)る。 「リュウキュウバショウ(琉球芭蕉)」,「イトバショウ(糸芭蕉)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | スコットランドのアウター・ヘブリディーズ諸島でつくられる手織りの最高級のツイード素材。スコットランドの羊毛の新毛で紡いだ紡毛糸を使用。手織機で綾織や杉綾に織ったもの。名前自体がハリス・ツイード協会の商標でもあり、球形の上に十字がついた「ハリス・ツイード」の商標マークが付けられている。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | スコットランド産羊毛の、太い紡毛糸を毛染めして手織りにした平織り、綾織の総称。ざっくりとした素朴な味わいのある厚手の紡毛織物。現在では、太番手の紡毛糸で織った平織り、綾織、杉綾の地厚で丈夫な織物を指す。ブリティッシュトラッドで、スーツ、コート、ジャケットなどカントリー調の服に使われる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | スズメ目(Passeriformes)ヒタキ科(Muscicapidae)カササギヒタキ亜科(Monarchidae)の鳥。
体はスズメよりやや大きく、翼長約8~9センチメートル。雄は頭と胸部が紫黒色、背面が赤紫色で、腹面は白い。目の周囲に美しい水色の縁取りがあり、尾羽が極めて長く30センチメートルを超え優美。雌は地味で、頭と胸部が黒色、背面が赤褐色で、尾は短い。 日本や台湾などで繁殖する夏鳥で、冬はインドシナやマレー半島など東南アジアに渡る。日本では本州以南の山地の暗い林に、樹の股(マタ)にコケ・樹皮・クモの糸などを使った円錐形の巣をつくる。 主として昆虫を捕食する。 鳴き声が「月(ツキ)日(ヒ)星(ホシ)ホイホイホイ」と聞こえるといわれ、「三光鳥」の名がついた。 単に「三光」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | タイガー商会が販売するジャイロ効果を利用したコマ(独楽)。登録商標。
ジャイロスコープ(gyroscope)(回転儀)に似て、直交する二つの輪の中心に、軸のある円盤の軸を上下から支えて固定し、タコ糸で回すもの。傾いてもジャイロ効果で回り続ける。 一般名は「ジャイロゴマ(gyro top)」。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | チェック模様を作るために、横糸とそり糸が交互に絡み会う基礎的な織り方 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | チョウ目(鱗翅目)(Lepidoptera)ヤママユ科(Saturniidae)のテグスガ(天蚕糸蛾)からとれる糸。
主に釣り糸の鉤素(ハリス)に用いる。 |
| 1件目から30件目を表示 | 次の30件 > |