「白」に関係する言葉
「白」に関係する言葉の一覧を表示しています。 検索結果が多い場合は文字数で絞ることが可能です。| 1件目から30件目を表示 | 次の30件 > |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (1)に似た帽子。
板前などの白い被(カブ)り物。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (1)の技法で染めた布。
「いたじめしぼり(板締め絞り)」,「いたじめかすり(板締め飛白,板締め絣)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (Brazil nuts)(1)の種子。長さ約4センチメートル。半月形で黄白色。食用。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (Chromis notata)(1)のスズメダイ属(Chromis)の海魚。
全長は約18センチメートル。体形はタイ(鯛)に似て側扁し、体色は全体に黒褐色で、背部後方の側面に白色の斑紋が左右一つづつある。 本州秋田県・千葉県以南や東シナ海の岩礁・サンゴ礁域に生息。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([中]Minjiao)白蓮教(Bailianjiao)の別称。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([学]Carcharhinus plumbeus)メジロザメ科メジロザメ属(Carcharhinus)のサメ。
体長2.4メートルほど。 目は白い瞬膜が発達。 「ヤジブカ」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([学]Gypsophila paniculata)ナデシコ目(Caryophyl-lales)ナデシコ科(Caryophyllaceae)カスミソウ属(Gypsophila)の鑑賞用植物。
普通の一年生ものはコーカサス・小アジア原産。多年生の宿根霞草は地中海沿岸に分布。 良く分枝・群生し、5~6月白・紅などの小花が咲きそろい、霞がかかったように見える。切花用で、カーネーションやバラの添花に多く利用される。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([学]Ipheion uniflorum)ユリ目(Liliales)ユリ科(Liliaceae)ハナニラ属(Ipheion)の多年草。南アメリカ原産。
葉は緑色扁平で幅狭く、傷付けるとニラに似た臭気がある。 観賞用に秋植の球根類として栽培される。 春、高さ約15センチメートルの花茎に、直径約3センチメートルの白色または薄紫色の六弁花を星型に開く。 「ブロディア(brodiea,brodiaea)」,「ベツレヘムの星(star-of-Bethlehem)」,「セイヨウアマナ(西洋甘菜)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([学]Lapsana apogonoides)キク目(Asterales)キク科(Asteraceae)ヤブタビラコ属(Lapsana)の二年草(越年草)。
田の畦(アゼ)などに生える雑草の一つ。 名称のように冬季は根出葉がロゼット状に地面に平らに広がっている。 早春、高さ約10~15センチメートルの花茎を数本出し、黄色の舌状花だけから成る頭花を開く。 茎・葉からは白い汁が出る。 若葉は食用となる。 「カワラケナ(土器菜)」とも呼ぶ。 「ホトケノザ(仏の座)」とも呼び、春の七草の一つ。 「コオニタビラコ(小鬼田平子)」とも呼ぶが、「オニタビラコ(鬼田平子)」はオニタビラコ属(Youngia)で別属。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([学]Lindera obtusiloba)クスノキ目(Laurales)クスノキ科(Lauraceae)クロモジ属(Lindera)の落葉低木。
本州の関東以西・四国・九州、東アジアの山地に自生。 高さ約3メートルに達し、枝を折れば芳香がする。 葉は楕円形または円形で、長さ5~15センチ。やや厚く、普通上半が浅く三裂し、裏面に淡褐色の長毛が密生する。 雌雄異株。 3~4月ころ、葉に先だって淡黄色の小さな六弁花がかたまって咲く。雄花のおしべは9本。 秋、径約1センチメートルで球形の液果を結び、9~10月赤く熟す。 庭木・生花とする。 「鬱金花(ウコンバナ)」,「白萵苣(シロヂシャ)」とも呼ぶ。 漢名は「三椏烏薬」。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([学]Microtus montebelli)(特に)ニホンハタネズミ。
体長約10センチメートル。背は茶褐色で、腹は灰白色。 草地や畑に穴を掘って棲(ス)み、農作物・苗木などの根を食べ害をなす。時に大発生し、森林の樹木に大害を及ぼす。 本州・佐渡島・九州に生息。〈ハタネズミ亜科〉 ヤチネズミ属(Clethrionomys)。 ニイガタヤチネズミ属(Aschizomys)。 カゲネズミ属(Eothenomys)。 ハタネズミ属(Microtus)。 マスクラット属(Ondatra)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([学]Phaseolus vulgaris)マメ目(Fabales)マメ科(Fabaceae)インゲンマメ属(Phaseolus)の一年生作物。熱帯アメリカ原産。
多くはつる性草本で、つるのない矮性(ワイセイ)のものや、直立する変種(ツルナシインゲン)ものや、種子の形・色も多彩で、品種がきわめて多い。 葉は互生し広卵形の小葉3枚からなる複葉。夏に開花し、花は白色または淡紫色の蝶形花で、葉腋(ヨウエキ)から出た総状花序の上に数個つく。秋に結実し、莢(サヤ)は線形で細長く、中に10個ほどの腎臓形の種子をもつ。 未熟果のサヤや種子を食用とする。茎葉は飼料となる。 マメ類では大豆(ダイズ)・落花生(ラッカセイ)に次ぎ、インド・ブラジル・中国など世界で広く栽培されている。 「インゲン(隠元)」,「インゲンササゲ(隠元ササゲ)」,「ゴガツササゲ(五月ササゲ)」,「さんどまめ(三度豆)」,「さいとう(菜豆)」とも呼ぶ。 未熟果の柔らかいサヤのまま煮(ニ)て食べるものを「さやいんげん(莢隠元)」、サヤの丸いものを「どじょういんげん(泥鰌隠元)」、サヤの平たいものを「モロッコインゲン」と呼ぶ。熟した種子を煮豆にするものは「金時(キントキ)」など。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([学]Pterocarpus indicus)マメ目(Fabales)マメ科(Fabaceae)シタン属(Pterocarpus)の常緑高木。インド南部原産。
心材は暗赤色で、辺材は白色。木質は緻密で堅く重い。また、木目が美しく、磨くと光沢が出る。床柱や高級家具・仏壇などに用いる。 「インドシタン」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([英]ginkgo nut)イチョウの実(ミ)・種子。
実の外種皮は黄色・多肉で強い悪臭がある。内種皮は白色で硬く、稜線がある。 内種皮を割って中身を食用にする。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([英]Japanese lizard)(特に)日本特産種のカナヘビ。
全長約20センチメートルで非常に細長く、尾の長さは体長の半分を超え、一見はヘビには見える。 体色は褐色で、側面に黒色の帯状斑紋があり、腹面は淡黄または白色。 本州・四国・九州・北海道に広く分布。 「ニホンカナヘビ」,「かなちょろ」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([英]omission)印刷物で、明記をはばかる字の箇所に「空白」または「○(まる)」・「×(ばつ)」などの記号を字の数だけ入れて表すこと。また、その記号。
検閲(ケンエツ)の対応策などとして行われる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([英]willow catkins)白い綿毛をもったヤナギ(柳)の種子。
春に熟した実から飛び散る。 |
姉妹サイト紹介

| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (『法華経』序品)釈迦(シャカ)が法華経を説かれるときに現れた「此土(シド)の六瑞(ロクズイ)」の一つとして空から降ったという四種の蓮華(レンゲ)の花。
<1>白蓮華 :曼荼羅華(マンダラゲ)。 <2>大白蓮華:摩訶(マカ)曼荼羅華。 <3>紅蓮華 :曼珠沙華(マンジュシャゲ)。 <4>大紅蓮華:摩訶曼珠沙華。 「しか(四華,四花)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (『淮南子(Huainanzi)(エナンジ)』説林)中国の戦国時代、墨子(Mozi)(ボクシ)が白い練り糸が黄色にも黒色にも染まるという話を聞いて泣いたという故事。
「墨子染(セン)を悲しむ」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (イスラム教で)信仰告白。五行の一つ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (カトリック教会で)司祭がミサなどのとき着用する、白麻の足までとどく長衣。
アミクトス(amictus)の上に着る。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (トルコ語で)バカ・白痴(ハクチ)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (フランス語で)バカ・白痴(ハクチ)。
「イディオット([フ]idiote)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (フランス語で)ユリ(百合)の花([英]flower of the lily)。
特に、白いジャーマンアイリス([学]Iris germanica)の花とされる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (中南米でインディオと白人、特にスペイン系白人との)混血・混血児。
「ミュラート」とも呼ぶ。むらーと(ムラート) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (五行説で)黄帝(Huangdi)・赤帝(Chidi)・白帝(Baidi)・青帝(Qingdi)・黒帝(Heidi)の総称。
「五方上帝(wufang shangdi)」とも呼ぶ。(1)〈別称〉 黄帝:土帝。 赤帝:炎帝・火帝。 白帝:金帝。 青帝:蒼帝(ソウテイ)・木帝・東帝。 黒帝:玄帝・水帝。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (急流などの)白く泡立った水。
「ホワイトウオーター」とも呼ぶ。 |
姉妹サイト紹介
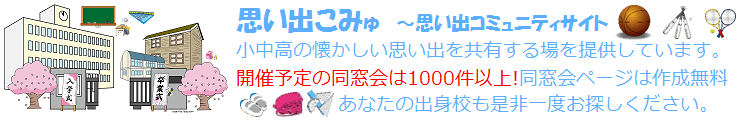
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (想像上の)白い羽毛に似た生き物。
空から飛んできて、化粧箱に入れておくと白粉(オシロイ)を食べて成長するという。 |
| 言葉 | (1)トレーニング・パンツ | 詳しく調べる |
|---|---|
| 意味 | (日本で)スポーツの練習に用いる足首まである長いパンツ。多くは白色。
和略語で「トレパン」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)中国の首都北京の天壇公園にある祈年殿。
明の嘉靖帝が北京の正陽門外に、白大理石造りの3層の円壇を築き、壇上に祈年殿と石階石欄を備える。 円形・三層屋根の祈年殿は木造で、高さ約38メートル、直径約32メートル。 円形・一層屋根の皇穹宇(コウキュウウ)も木造で、直径約16メートル。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)根が丸く、皮は赤く、中身は白いもの。
サラダなど生食に適する。 「ラディッシュ」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (白く輝いて)美しい銀・良質の銀。
「なんてい(南挺,軟挺)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (白人とインディアンとの)混血・混血児。軽蔑的。てぃす(メティス)(2) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (神の乗る)白いゾウ・白象。
「アイラーバタ([梵]Airavata)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (英語で)白内障(ハクナイショウ)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (警察関係で)自白を指す隠語。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)やせて顔色が青白く、元気のない人。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)旧友同士が相手の気持ちを理解しなかったときに謝罪として用いる言葉。
「白頭新(アラ)たなるが如し」とも言う。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (転じて)表面が滑らかで白いこと。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (遊郭などで)芸人・遊女などに当座の祝儀(シュウギ)として渡す白い懐紙(カイシ)。後日に現金を与えるという印(シルシ)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1156(保元元. 7.)皇位継承をめぐり崇徳上皇と後白河天皇が対立し、さらに摂関争いが結び付いて起きた内乱。
上皇方には左大臣藤原頼長(ヨリナガ)・源為義(タメヨシ)・源為朝(タメトモ)・平忠正。 天皇方には関白藤原忠通(タダミチ)・源義朝(ヨシトモ)・平清盛(キヨモリ)。 天皇方の勝利となり、上皇は讃岐へ配流、頼長は戦死、為義らは斬られる。 この乱は武家の実力が勝敗の趨勢を握っていたため、武家の中央政界への進出の契機となる。 |
| 言葉 | (2)シャクシャインの戦い | 詳しく調べる |
|---|---|
| 意味 | 1669(寛文 9)蝦夷地(エゾチ)(現:北海道)のアイヌ人が、交易独占を強化する松前藩の支配と収奪に抵抗して起した蜂起(ホウキ)。
東蝦夷地に拠点を持つアイヌ人首長シャクシャインが、東西両蝦夷地のアイヌ人に反和人・反松前藩の檄(ゲキ)をとばし、東は白糠(シラヌカ)から西は増毛(マシケ)までアイヌ人が一斉(イッセイ)に蜂起。蝦夷各地で商船などを襲い、商船の船頭や鷹待(タカマチ)(鷹匠)など日本人(和人)約390を殺害。 徳川幕府は松前氏の一族松前泰広(旗本)や津軽弘前藩に出兵を命じた。 アイヌ側は松前藩への襲撃も企てたが、国縫(クンヌイ)で防ぎ止められた。同年十月になって松前藩の和睦(ワボク)を装う奸計(カンケイ)にあってシャクシャインは殺害。1671(寛文11)までに蜂起は完全に鎮圧(チンアツ)された。 「シャクシャインの乱(沙牟奢允の乱)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1776年、アメリカ合衆国独立当時の東部13州植民地(the Thirteen Colonies)のこと。
国旗の13本の紅白の横縞に表されている。 「建国十三州」,「十三植民地」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1900(明治33)台湾に建立された官幣大社。
祭神は大国魂命(オオクニタマノミコト)・大巳貴命(オオナムチノミコト)・少彦名命(スクナヒコナノコミト)と、台湾出兵して病没した近衛師団長の北白川宮能久(ヨシヒサ)親王。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1917(大正 6)ロシア革命およびその後の内乱期に、ソビエト政権の赤衛軍に対抗して政権を奪回するため各地で蜂起した帝政派などの反革命軍。
「白軍(White Army)」とも呼ぶ。 |
| 1件目から30件目を表示 | 次の30件 > |