"帝"がつく言葉
"帝"がつく言葉の一覧を表示しています。 検索結果が多い場合は文字数で絞ることが可能です。 文字数は検索結果となる文字の文字数のボタンを押してください。| 31件目から60件目を表示 | < 前の30件 | | | 次の30件 > |
| 言葉 | 万暦帝 |
|---|---|
| 読み | ばんれきてい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)明朝の第十四代の皇帝・神宗(Shenzong)(シンソウ)(1563~1620)。在位:1572~1620。隆慶帝(Longqing Di)(穆宗<ボクソウ>)の第三子。
10歳で即位し、前帝の遺命で吏部尚書の張居正(Zhang Ju-zheng)(チョウ・キョセイ)(1525~1582)が国政を補佐し、冗官整理・土地調査・財政改革などによる財政再建や黄河の治水事業などが行われ、国防の強化で北虜南倭(ホクリョ・ナンワ)も抑えることに成功。
張居正の没後、帝の親政は放漫に流れて各地に内乱が起こる。また「万暦の三大征」と呼ばれる、1592<万暦20>寧夏(Ningxia)(ネイカ)のモンゴル傭兵長ボハイ(博拜
一方、宦官(カンガン)を重用して鉱山の開発など新規事業による課税から民衆の生活は困窮。宮廷では宦官を批判する東林党(Donglin Dang)(トウリントウ)と非東林党の党争が対立激化。東北方面の満州族の後金(清<シン>)が興起し、国勢は衰えた。
| 言葉 | 乾隆帝 |
|---|---|
| 読み | けんりゅうてい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)中国清朝の第六代皇帝(1711~1799)。在位:1735~1795。名は愛新覺羅弘厲(Aisingiorro Hongli)、諱(イミナ)は弘暦(Hong-li)、廟号(ビョウゴウ)は高宗(Gao Zong)、諡号(シゴウ)は純皇帝(Chun Huandi)。雍正帝(Yongzheng Di)の第四子。
| 言葉 | 五天帝 |
|---|---|
| 読み | ごてんてい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)(五行説で)黄帝(Huangdi)・赤帝(Chidi)・白帝(Baidi)・青帝(Qingdi)・黒帝(Heidi)の総称。
「五方上帝(wufang shangdi)」とも呼ぶ。(1)〈別称〉
黄帝:土帝。
赤帝:炎帝・火帝。
白帝:金帝。
青帝:蒼帝(ソウテイ)・木帝・東帝。
黒帝:玄帝・水帝。
| 言葉 | 五賢帝 |
|---|---|
| 読み | ごけんてい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)古代ローマ帝国の最盛期を現出させた5人の優れた皇帝の総称。
1~2世紀(AD. 96~ 180)相次ぎ、在位した。
<1>ネルウァ(ネルワ)(Marcus Cocceius Nerva): 96~ 98。
<2>トラヤヌス(Marcus Ulpius Crinitus Trajanus): 98~ 117。
<3>ハドリアヌス(Publius Aelius Hadrianus): 117~ 138。
<4>アントニヌス・ピウス(Titus Aelius Antonius Pius): 138~ 161。
<5>マルクス・アウレリウス・アントニヌス(Marcus Aelius Antonius): 161~ 180。
| 言葉 | 光緒帝 |
|---|---|
| 読み | こうしょてい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)中国清朝の第11代皇帝(1871~1908)。在位1875~1908。名は載(三水+「恬」)(サイテン)、廟号(ビヨウゴウ)は徳宗。
「こうちょてい(光緒帝)」とも呼ぶ。
| 言葉 | 刹帝利 |
|---|---|
| 読み | さつていり |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 同治帝 |
|---|---|
| 読み | どうちてい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)中国の清朝(Qing Zhao)の第10代皇帝(1856~1875)。在位:1861~1874。廟号(ビョウゴウ)は穆宗(Mu Zong)(ボクソウ)。父は第9代咸豊帝(カンポウテイ)(Xianfeng Di)(文宗)、母は西太后(Xi Taihou)(セイタイコウ)。
5歳で即位。生母の西太后が実権を握る。
| 言葉 | 始皇帝 |
|---|---|
| 読み | しこうてい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)秦(Qin)の第一世皇帝(BC. 259~BC. 210)。姓は贏(Ying)(エイ)、名は政(Zheng)(セイ)。荘襄王(Zhuangxiang Wang)(ソウジョウオウ)の子、扶蘇(Fusu)(フソ)・二世皇帝胡亥(Huhai)(コガイ)の父、三世皇帝子嬰(Ziying)(シエイ)の祖父、祖母は夏太后(Xia Taihou)。
BC. 221、中国を統一し、皇帝に即位。郡県制を実施。
匈奴(キョウド)を北に追い払い、万里の長城を増築。咸陽宮(Xianyang Gong)(カンヨウキュウ)・阿房宮(Afang Gong)(アボウキュウ)などを造営。
BC. 213~BC. 212、焚書坑儒を行う。韋)
| 言葉 | 孝成帝 |
|---|---|
| 読み | こうせいてい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)前漢の第12代皇帝。在位:BC. 33~BC, 7。
諱(イミナ)は「劉(「敖」冠+「馬」)(Liu Ao)(リュウ・ゴウ)」、諡号(シゴウ)は「統宗(Tong Zong)」。
「成帝(Cheng Di)」とも呼ぶ。
| 言葉 | 宋帝王 |
|---|---|
| 読み | そうたいおう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)十王の第三。
| 言葉 | 宣統帝 |
|---|---|
| 読み | せんとうてい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)清朝最後の皇帝(1906~1967)。在位:1908~1912。
| 言葉 | 崇禎帝 |
|---|---|
| 読み | すうていてい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)中国、明朝最後の第17代皇帝(1610~1644)。
在位1628~1644。廟号(ビョウゴウ)は毅宗(Yizong)(キソウ)、荘烈帝(Zhuanglie Di)とも呼ぶ。
宦官(カンガン)魏忠賢(Wei Zhongxian)(ギ・チュウケン)らを退け、徐光啓(Xu Guangqi)(ジョ・コウケイ)を用いて内政を改革し明朝の復興を図ったが、清の南下と戦いその軍費の増大による農民反乱や山西を中心とする流賊の乱に苦しみ、李自成(Li Zicheng)(リ・ジセイ)の北京攻略の際に悲劇的な遺書を残して縊死(イシ)。
| 言葉 | 帝キネ |
|---|---|
| 読み | ていきね |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)帝国キネマの略称。
| 言葉 | 帝国党 |
|---|---|
| 読み | ていこくとう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)国民協会が1899(明治32)解散され、同年佐々友房を中心に再編された政党。
| 言葉 | 帝國黨 |
|---|---|
| 読み | ていこくとう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)国民協会が1899(明治32)解散され、同年佐々友房を中心に再編された政党。
| 言葉 | 帝塚山 |
|---|---|
| 読み | てづかやま |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ | 駅 |
(1)大阪府大阪市住吉区にある南海高野線の駅名。
| 言葉 | 帝王蝶 |
|---|---|
| 読み | ていおうちょう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)オオカバマダラの別称。
姉妹サイト紹介

| 言葉 | 帝都座 |
|---|---|
| 読み | ていとざ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)東京市四谷区の追分停留所近くにあった、日活系映画館。
| 言葉 | 帝釈天 |
|---|---|
| 読み | たいしゃくてん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)須弥山(シュミセン)の頂(イタダキ)トウ(立心偏+「刀」)利天(トウリテン)に住み仏法を護(マモ)る神。
十二天の一神で東方の守護神。四天王(持国天・増長天・広目天・多聞天)を家来とする。
ヒンズー教のインドラ(Indra)に相当。
| 言葉 | 帝釈山 |
|---|---|
| 読み | たいしゃくさん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)栃木県と福島県にまたがる山。標高2,060メートル。
| 言葉 | 康煕帝 |
|---|---|
| 読み | こうきてい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)清朝の第4代皇帝(1654~1722)。在位:1661~1722。
名は愛新覺羅玄燁(Aisingiorro Xuanye)、廟号(ビョウゴウ)は聖祖(Shengzu)(セイソ)。
順治帝(Shunzhi Di)(世祖)の第三子。
三藩の乱(1673~1681)を平定し、台湾を征討(1683)。
ロシアの東侵を阻止し、外モンゴル・青海・チベットを平定。
| 言葉 | 永楽帝 |
|---|---|
| 読み | えいらくてい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)明朝の第三代の皇帝・成祖(Chengzu)(1360~1424)。在位:1402~1424。
名は朱棣(Zhu Di)(シュ・テイ)。洪武帝(Hongwu Di)(太祖)の第四子。
初め燕王(エンオウ)に封ぜられて山西省(Shangxi Sheng)にありモンゴルに備え、諸王中最も有力であった。
洪武帝の孫第二代建文帝(Jianwen Di)(恵帝)(甥)の時、諸王の勢力を削減する動きの中、靖難(セイナン)の師と称して北平で叛し(靖難の変)、京師(南京)を陥(オトシイ)れ自ら即位(1402)。1421年北平(燕京)に遷都して京師(通称北京)とした。
内政に意を致して官吏の冗員の整理や租税の減免を行い刑罰を厳格にした。
また対外的には、もとの元の一族が漠北に拠って勢力を回復したので黒竜江(コクリュウコウ)下流まで親征、さらに西北蒙古の瓦刺(ウエラ)(オイラート)部を討ち、満蒙・河西・青海を服属させた。南方には安南(ベトナム)を討って交阯(コウシ)布政司を設け、宦官鄭和(Zheng He)(テイ・ワ)を南海諸国からアフリカ沿岸まで派遣し、真臘(シンロウ)(カンボジア)・暹羅(シャム)(タイ)・爪哇(ジャワ)(インドネシア)などをも来貢させた。
5度目のモンゴル親征の帰途、内モンゴルの楡木川(Yumu-chuan)(ユボクセン)で病没。
『永楽大典』・『四書大全』・『五経大全』の編纂など文化事業も業績を示した。
| 言葉 | 白帝城 |
|---|---|
| 読み | はくていじょう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)愛知県犬山城の別称。
(2)中国中央部、中央直轄市重慶(Chongqing)北東部の奉節県(Fengjie Xian)(ホウセツケン)東部の白帝鎮(Zhen)にある古城。 李白(Li Bai)(リ・ハク)の七言絶句『早発白帝城(つとに白帝城を発す)』などに歌われている。
| 言葉 | 訶梨帝 |
|---|---|
| 読み | かりてい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)鬼子母神(キシモジン)。
| 言葉 | 赤帝子 |
|---|---|
| 読み | せきていし |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)漢の高祖劉邦(リュウ・ホウ)の別称。
| 言葉 | 道武帝 |
|---|---|
| 読み | どうぶてい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)北魏(Bei Wei)(ホクギ)(後魏)の初代皇帝( 371~ 409)。在位: 386~ 409。名は拓跋珪(Taba Gui)(タクバツ・ケイ)、廟号(ビョウゴウ)は太祖(Taizu)、諡(オクリナ)が道武帝。
383年、前泰が(三水偏+「肥」)水(ヒスイ)(Feishui)の戦いで東晋に敗れたのに乗じて鮮卑拓跋部を統一再興。 386年、都を内モンゴルの盛楽(Chengle)に定め、代王の位につき魏を建国。ついで 388年魏王と称す。さらに勢力を華北にのばし、 398年平城(Pingcheng)(山西省大同
従来の部族組織を解体し、制度・文物を中国風に整え、国家の基礎を固める。
晩年、狂疾を発し、次子紹(Shao)に殺された。
| 言葉 | 関帝廟 |
|---|---|
| 読み | かんていびょう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)中国の英雄関羽(Guan Yu)(カン・ウ)の霊を祀(マツ)る廟。
中国各地や華僑の間で、武神・財神として広く信仰されている。
「武廟(Wumiao)(ブビョウ)」,「老爺廟(Laoyemiao)(ロウヤビョウ)」とも呼ぶ。
姉妹サイト紹介
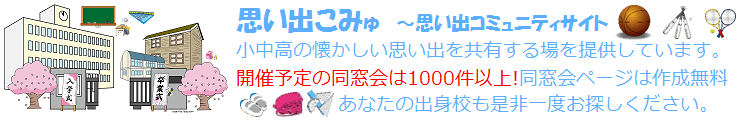
| 言葉 | 雍正帝 |
|---|---|
| 読み | ようせいてい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)清朝の第五代皇帝(1678~1735)。在位:1722~1735。
姓は愛新覺羅([満州語]Aisingioro)、諱(イミナ)は胤禛(Yin-zhen)(インシン)、廟号(ビョウゴウ)は世宗、諡号(シゴウ)は憲皇帝。康煕帝の第四子。
独裁専制政治を行い、外征をあまり行なわずに内治に専心し、官吏の綱紀を正し、軍機処(Junjichu)の創設、地丁銀(チテイギン)の普及させ財政を充実。
ロシアとの間にキャフタ条約(1727)を結び、国境貿易を開いた。
キリスト教に対しては厳禁の方針をとり、宣教師をマカオに追放した。
| 言葉 | マリ帝国 |
|---|---|
| 読み | まりていこく |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)13~15世紀ころ、アフリカ北西部を支配した黒人イスラム教国。
場所は現在の西スーダンの大部分。
黄金と塩の交易で栄える。
「マリ王国(Kingdom of Mali)」とも呼ぶ。帝国)
| 言葉 | 京王帝都 |
|---|---|
| 読み | けいおうていと |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)京王帝都電鉄の略称。
| 31件目から60件目を表示 | < 前の30件 | | | 次の30件 > |