「人形」に関係する言葉
「人形」に関係する言葉の一覧を表示しています。 検索結果が多い場合は文字数で絞ることが可能です。| 1件目から30件目を表示 | 次の30件 > |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([英]straw effigy)(特に)丑(ウシ)の時参りで、相手の人形(ヒトガタ)として金鎚(カナヅチ)で五寸釘を打ち込む人形。(1) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([英]straw figure)藁をたばねて作った人形。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (スペイン語で)人形。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (フランス語で)人形。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (射撃練習用)標的人形. |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | (特に)五節句の一つ、五月五日の節句。
日本では奈良時代に中国から祝う習慣が伝来し、ショウブ(菖蒲)やヨモギ(蓬)を軒に挿して邪気を払い、粽(チマキ)や柏餅(カシワモチ)を食べる風習ができた。 ショウブが「尚武(ショウブ)」に通じることから、江戸時代以後は男子の節句とされ、武家では甲胄(カッチュウ)などを飾り、庭先に幟旗を立てて男子の成長を祝った。次第に町人も武者人形などを飾り、鯉幟(コイノボリ)を立てるようになった。 第二次世界大戦後は「こどもの日」として国民の祝日となった。 「端午の節句」,「端午の節(セチ)」,「あやめ(菖蒲)の節句」,「重五(チョウゴ)」,「端陽(タンヨウ)」,「夏節([中]Xiajie)(カセツ)」とも呼ぶ。龍) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1927. 3.27(昭和 2)アメリカの児童から日本の子供たちに贈られた約1万2千体の人形。
カリフォルニアの日本人移民排斥運動など日米関係の悪化を憂慮して、親日家の宣教師シドニー・ルイス・ギューリック(Dr. Sidney Lewis Gulick)(1860~)が提唱し、アメリカ国内の約260万人の募金で日本の子供たちに贈ったもの。日本全国の小学校に配られた。 第二次世界大戦中に大半は焼却などで破棄されたが、戦後に約300体弱が発見されている。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | あやつり人形。
フランス語で「マリオネット(marionette)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アメリカ合衆国ニューヨーク州(New York State)西部のロチェスター(Rochester)にある、装飾美術品服飾品・人形・ミニチュアなどを展示する博物館。
おもちゃコレクションで知られる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アメリカ玩具大手マテル社(Mattel Inc.)が製造・販売する女の子の着せ替え人形。
日本では(株)バンダイが販売。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アーケード・ゲームの一種。
幾つか開いた穴から、モグラを模(カタド)った人形が順不同で次から次と顔を出しては引っ込め、それを手に持ったハンマーで叩くもの。 顔を出している間に叩くと加点される。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | インドネシアの影絵人形芝居。
主に透かし彫りした水牛の革の人形を使用する。 「ワヤン・クリ(wajang kulit)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ウラン(U)のリン酸塩の水和物(CaU[PO4]2・1-2H2O)の鉱物。
鳥取県・岡山県の県境の人形峠で産出。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | キリスト教の祝日。
東方の三博士(Magi)がベツレヘムに幼子(オサナゴ)キリストを訪れたクリスマス後の12日目(Twelfth Day)の1月6日を記念する。 異邦人である三博士の来訪により、救いがユダヤ人の外に広がったことを祝う。 フランスでは陶製の人形の入った菓子ガレットを焼いて祝う。 「公現日」,「主顕日」,「顕現日」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ハスブロ社(Hasbro Inc.)製のアメリカ兵の姿をした人形。
各部隊のモデルがある。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | モミジの葉の形をした人形焼きの一種。
広島名物。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ローマ神話の恋愛の神キューピッド(Cupid)を愛らしくデザインしたセルロイド製の人形。
赤ん坊のように大きな頭で目が大きく裸体。頭のてっぺんは頭髪がうずを巻いてとがっている。 「キューピー人形(Kewpie doll)」とも呼ぶ。 |
姉妹サイト紹介

| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 三月三日の節供に飾る雛(ヒナ)人形のうち、官女の姿をした三体一組の人形。
ひな飾りで内裏(ダイリ)びなの下に飾り、内裏びなの世話をする役。ひな段に向かい右から長柄銚子(チョウシ)持ち、三方(サンポウ)持ち、加えの銚子持ちの順。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 丸みのある底にオモリ(錘)に入れた人形。
何度倒してもオモリの重力ですぐに立ち上がるもの。 縁起物(エンギモノ)のダルマ(達磨)の人形が多い。 「おきあがりこぼうし(起き上り小法師,起上小法師)」,「ふとうおう(不倒翁)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 人または動物の空洞の頭部と布でできた体のある人形 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 人家の門口(カドグチ)で、芸能を演じたり、音曲を奏したり、経を読んだりして金品を貰(モラ)い歩くこと。また、その人。
万歳(マンザイ)・厄払(ヤクバラ)い・人形回し・浄瑠璃(ジョウルリ)・門説経などが行われた。 「化他(ケタ)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 人形師によって糸で上から操作される人の小さな人形 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 人形浄瑠璃の舞台の手摺り(横板)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 依代(ヨリシロ)となる人間。神霊がよりつく人間。
祈祷師(キトウシ)が神霊を招いて乗り移らせ、託宣(タクセン)をのべさせるための童子や婦女で、神が「依りますところ」の意味。 人形を用いることもあり、この場合は後に川に流す。 「寄人(ヨリビト)」,「物憑(モノツ)き」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 危険な場面などで俳優の代りに使う、トリック撮影用の替玉人形。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 唐子人形の略称。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 埼玉県東部の市。
武者人形・浮世人形が特産。 坂東三十三所の十二番札所、慈恩寺(ジオンジ)の慈恩寺観音がある。 |
姉妹サイト紹介
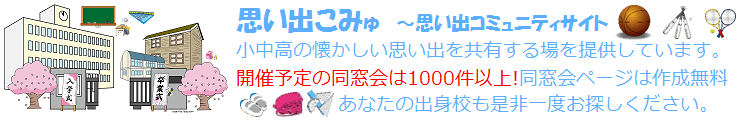
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 大手玩具メーカー。
着せ替え人形の「リカちゃん人形」やミニカーの「チョロQ」などを販売。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 天皇と皇后に似せた男女一対の雛人形。
「内裏」,「きんり(禁裏,禁裡)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 安珍(アンチン)・清姫(キヨヒメ)の日高川伝説(道成寺伝説)を脚色した人形浄瑠璃。桜木親王と藤原忠文の皇位争いや、伊予掾藤原純友の反逆をからませた時代物。竹田小出雲・近松半二らの合作。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 布地体および空の頭を持つ操り人形 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 押し固めた雪でつくった人形 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 持ち帰り寿司チェーン店。
本社は東京都中央区日本橋人形町。 ちらし鮨(ズシ)・巻き鮨や薄焼き玉子で包んだ巾着鮨(キンチャクズシ)などが主力商品。 吉野家ホールディングス(HD)の傘下。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 指人形劇。
「ギニョル」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 文楽などの操り人形で、人形の手首や指を操作する棒。また、紐(ヒモ)を含むその仕掛け。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 服を展示するのに用いる等身大の人形 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 木製の玩具(オモチャ)の一種。また、その遊び。
厚みのある円形の木片を数個重ねた上に達磨人形を置いたもの。その人形を落とさないようにして、下段の木片の横を木槌(キヅチ)で素早く叩(タタ)いてはずし、それを繰り返して段々に低くし、最後は人形のみにする遊び。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 東京都中央区日本橋小伝馬町にある東京地下鉄(東京メトロ)日比谷線の駅。
秋葉原(アキハバラ)駅(千代田区)と人形町(ニンギョウチョウ)駅の間。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 東北地方の郷土人形。
伝統こけしには、宮城県の鳴子(ナルコ)(鳴子町)・作並(サクナミ)(仙台市)・遠刈田(トウガツタ)(蔵王町)・弥治郎(ヤジロウ)(白石市福岡八宮)、山形県の肘折(ヒジオリ)(大蔵村)、福島県の土湯(ツチユ)(福島市)などの系統がある。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 歌手・小林幸子さんの巨大人形のこと。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 歌舞伎・人形浄瑠璃で、病人の役が病人であることを示すため、扮装として結ぶ鉢巻。
男女の別なく、頭の左側に結び、若い役では紫、老人役では黒の鉢巻を用いる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 江戸中期、大坂にあった操座(アヤツリザ)(人形浄瑠璃の劇場)。
1684(貞享元)ころ、初代竹本義太夫(ギダユウ)(1651~1714)らが大坂道頓堀戎橋(エビスバシ)南詰めに創設。作者の近松門左衛門(1653~1724)、三味線の竹沢権右衛門、人形遣の吉田三郎兵衛・辰松八郎兵衛らを迎え、『出世景清』などを上演。 1705(宝永 2)竹田出雲(?~1747)に経営(座元)を任せ、近松が座付作者、義太夫自身が専属太夫となる。 1724(享保 9)近松の没後、並木千柳・三好松洛らが合作制で『仮名手本忠臣蔵』などを上演。 東の豊竹座(トヨタケザ)と競演し、「西の芝居」と称されて操(アヤツリ)全盛を極め、両座で歌舞伎を圧倒したこともあった。 その後、内部的な破綻(ハタン)から衰えて、1767(明和 4)廃座。 |
| 1件目から30件目を表示 | 次の30件 > |