「ルナ」に関係する言葉
「ルナ」に関係する言葉の一覧を表示しています。 検索結果が多い場合は文字数で絞ることが可能です。| 1件目から30件目を表示 | 次の30件 > |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ([学]Phaseolus vulgaris)マメ目(Fabales)マメ科(Fabaceae)インゲンマメ属(Phaseolus)の一年生作物。熱帯アメリカ原産。
多くはつる性草本で、つるのない矮性(ワイセイ)のものや、直立する変種(ツルナシインゲン)ものや、種子の形・色も多彩で、品種がきわめて多い。 葉は互生し広卵形の小葉3枚からなる複葉。夏に開花し、花は白色または淡紫色の蝶形花で、葉腋(ヨウエキ)から出た総状花序の上に数個つく。秋に結実し、莢(サヤ)は線形で細長く、中に10個ほどの腎臓形の種子をもつ。 未熟果のサヤや種子を食用とする。茎葉は飼料となる。 マメ類では大豆(ダイズ)・落花生(ラッカセイ)に次ぎ、インド・ブラジル・中国など世界で広く栽培されている。 「インゲン(隠元)」,「インゲンササゲ(隠元ササゲ)」,「ゴガツササゲ(五月ササゲ)」,「さんどまめ(三度豆)」,「さいとう(菜豆)」とも呼ぶ。 未熟果の柔らかいサヤのまま煮(ニ)て食べるものを「さやいんげん(莢隠元)」、サヤの丸いものを「どじょういんげん(泥鰌隠元)」、サヤの平たいものを「モロッコインゲン」と呼ぶ。熟した種子を煮豆にするものは「金時(キントキ)」など。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1887(明治20)エジプトのアマルナで発見された、楔形文字で書かれた約360の粘土板文書。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | 1957. 4.(昭和32)西ドイツの原子力科学者18人がゲッティンゲンで出した原子力平和利用の宣言。
西ドイツの核武装計画に反対し、原子力兵器の製造・実験への不参加と原子力平和利用への協力とを誓う。 「ゲッチンゲン宣言」とも呼ぶ。〈ゲッティンゲンの18人(Goettinger Achtzehn)〉 マックス・フォン・ラウエ(Max von Laue)(1879~1960)。 オットー・ハーン(Otto Hahn)(1879~1968)。 マックス・ボルン(Max Born)(1882~1970)。 フリードリヒ・アドルフ・パネット(Friedrich Adolf Paneth)(1887~1958)。 バルター・ゲーラッハ(Walter Gerlach)(1889~1979)。 ヨセフ・マッタウチ(Josef Mattauch)(1895~1976)。 ベルナー・カール・ハイゼンベルク(Werner Karl Heisenberg)(1901~1976)。 ハンス・コパーマン(Hans Kopfermann)(1901~1976)。 フリッツ・シュトラスマン(Fritz Strassmann)(1902~1980)。 ルドルフ・フライシュマン(Rudolf Fleischmann)(1903~2002)。 フリッツ・アーノルド・ボップ(Fritz Arnold Bopp)(1909~1987)。 オットー・ハクセル(Otto Haxel)(1909~1998)。 カール・オイゲン・ユリウス・ビルツ(Karl Eugen Julius Wirtz)(1910~1994)。 ベルヘルム・バルハー(Wilhelm Walcher)(1910~2005)。 ハインツ・マイアー・ライプニッツ(Heinz Maier-Leibnitz)(1911~2000)。 カール・フリードリヒ・フォン・バイツゼッカー(Carl Fried-rich von Weizsaecker)(1912~)。 ボルフガング・パウル(Wolfgang Paul)(1913~1993)。 ボルフガング・リーツラー(Wolfgang Rietzler)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アカザ目(Centrospermae)アカザ科(Chenopodiaceae)オカヒジキ属(Salsola)の一年草。
「ミルナ(海松菜)」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アメリカ合衆国南西部、ニューメキシコ州(New Mexico State)中北西部にあるベルナリーリョ郡(Bernalillo County)の郡都。
北緯35.12°、西経106.62°の地。 エネルギー省のサンディア国立研究所(SNL)がある。 「アルバカーキ」,「アルブケルケ」とも呼ぶ。〈人口〉 1990(平成 2)38万4,736人。 2000(平成12)44万8,600人。 2002(平成14)45万3,600人。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アメリカ合衆国西部、カリフォルニア州(California State)南部の郡。北部をイニョ郡(Inyo County)、南部をリバーサイド郡(Riverside County)、南西部をオレンジ郡(Orange County)・ロスアンゼルス郡(Los Angels County)、北西部をカーン郡(Kern County)に接し、東部をネバダ州とアリゾナ州に隣接。
郡都はサンバーナディノ。 モハーベ砂漠(Mojave Desert)がある。 「サンバーナージノ郡」,「サンバーナジーノ郡」,「サンベルナルディノ郡」,「サンベルナルジノ郡」とも呼ぶ。〈人口〉 1980(昭和55) 87万7,636人。 1990(平成 2)141万8,380人。 2000(平成12)170万9,434人。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | アーリア人がインドに侵入した紀元前13世紀末から始まる身分階層制度。征服した原住民を差別したことに始まる。〈インド〉
<1>バラモン(Brahman)(司祭)。 <2>クシャトリア(Ksatriya)(王族)。 <3>バイシャ(Vaisya)(平民)。 <4>スードラ(Sudra)(奴隷)。 これらの4種姓を基本とする。上位3種は再生族(バルナ)と呼ぶ。その後、混血や職業の分化にともなって複雑に分岐し、今日では2,000~3,000の副カーストが存在する。さらにカーストの外に最下層民として不可触賎民(パリア)が存在する。 カーストは閉鎖的・排他的で職業を世襲し、異種カースト間の結婚から飲食まで厳密に禁止され、深刻な社会差別を生み、インドの近代化の妨げとなった。インド独立後は憲法で禁止されているが、なお根強く残っている。 「四姓(シセイ)」,「バルナ」,「ヴァルナ」,「種姓」,「ジャーティ(jati)」とも呼ばれる。〈ネパール〉 <1>バウン(Bahun)(司祭カースト)。 <2>チェットリ(Chhetri)(王侯・軍人)。 <3>不可触賎民(untouchable):カミ(Kami)(鍛冶屋)・サルキ(Sarki)(皮職人)・ダマイ(Damai)(仕立て屋)など。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | イタリアの画家(1884~1920)。エコール・ド・パリの一員。
リボルノ(Livorno)生れのユダヤ人。 1906年、パリに出て、モンパルナス(Montparnasse)に住む。はじめ彫刻を志したが、セザンヌ(Paul Cezanne)およびフォービスム・キュビスムの影響を受け、画家に転じた。 ほとんどの作品が裸婦か肖像で、細長い首の単純化した独特の形態と重厚な色彩で、一種の哀愁を帯びた美を作り出している。 生前は認められず、貧困と過度の飲酒による荒廃した生活の中、若くして死んだ。 「モジリアニ」,「モディリアーニ」,「モディリアニ」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | インドが実効支配するアルナーチャル・プラデシュ州(Aru-nachal Pradesh State)の中国名。
「蔵南地区(Zangnan Diqu)」とも呼ぶ。プラデシュ州) |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | インド北東部、アッサム州(Assam State)北東部の県。北部をアルナーチャル・プラデシュ州(Arunachal Pradesh State)に隣接。
「デマジ地区」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | インド半島南西部、西ガッツ山脈(Western Ghats)西側のアラビア海(Arabian Sea)に面する海岸地方。
北端がゴア州(Goa State)、北部がカルナータカ州(Karnata-ka State)、南部がケララ州(Kerala State)に属する。 古来から香料の産地・東西貿易の中継地として栄え、ゴア(Goa)・マンガロール(Mangalore)・コジコーデ(Kozhikode)(旧:カリカット)・コーチン(Cochin)・ティルバナンタプラム(Thi-ruvananthapuram)(旧:トリバンドラム)などの港湾都市がある。 「マラバル」とも呼ぶ。盤,真名盤) |
| 言葉 | (1)アンドラプラデシュ州 | 詳しく調べる (2)アンドラ・プラデシュ州 | 詳しく調べる |
|---|---|
| 意味 | インド南東部の州。北部をマハラシュトラ州(Maharashtra State)、北東部をオリッサ州(Orissa State)、南部をタミルナドゥ州(Tamil Nadu State)、西部をカルナータカ州(Karnataka State)に接し、東部をベンガル湾(Bay of Bengal)に面する。
州都はハイデラバード(Hyderabad)。〈面積〉 27万6,814平方キロメートル。〈人口〉 1991(平成 3)6,650万8,000人。 2001(平成13)7,572万7,500人。 2002(平成14)7,720万6,600人。〈県〉 グントゥール県(Guntur District)など。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | インド南端、タミルナドゥ州(Tamil Nadu State)の高地ニルギリで産出する紅茶。
癖(クセ)がなく、主にブレンドのベースとして用いられる。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | インド南端、タミルナドゥ州(Tamil Nadu State)中東部の県。南部をベンガル湾(Bay of Bengal)とマンナール湾(Gulf of Mannar)を結ぶポーク海峡(Palk Strait)に面する。
県都はタンジャブール。 北東部に古都クンバコナム(Kumbakonam)がある。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | インド南端、タミルナドゥ州(Tamil Nadu State)南部のラマナタプラム県東部にある県都。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | インド南端、タミルナドゥ州(Tamil Nadu State)南部の県。東部をポーク海峡(Palk Strait)、南部をマンナール湾(Gulf of Mannar)に面する。
県都はラマナタプラム。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | インド南端、タミルナドゥ州(Tamil Nadu State)東部のナガパティナム県南部側の北東部にある県都。 |
姉妹サイト紹介

| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | インド南端、タミルナドゥ州(Tamil Nadu State)東部の県。県域がポンディシェリー連邦直轄地(Pondicherry Union Ter-ritory)のカライカル(Karaikal)を挟(ハサ)んで南北に分断されている。北部をカッダロール県(Cuddalore District)に接し、東部をベンガル湾(Bay of Bengal)に面する。
県都はナガパティナム。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | インド南西端、西ガッツ山脈(Western Ghats)西側のマラバール(Malabar)地方の州。北部をカルナータカ州(Karnataka State)、東部をタミルナドゥ州(Tamil Nadu State)に接し、西部をアラビア海(Arabian Sea)に面する。
州都はティルバンナンタプラム(Thiruvananthapuram)。 ドラビダ系の住民が多い。 「ケーララ州」とも呼ぶ。〈面積〉 3万8,864平方キロメートル。〈人口〉 1991(平成 3)2,909万8,500人。 2001(平成13)3,283万8,600人。 2002(平成14)3,246万0,500人。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | インド南部、カルナータカ州(Karnataka State)で使用されている言語。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | インド南部、カルナータカ州(Karnataka State)南西部の県。北部をウドゥピ県(Udupi District)に接し、西部をアラビア海に面する。
県都はマンガロール(Mangalore)。〈面積〉 4,560平方キロメートル。〈人口〉 1991(平成 3)269万4,264人(3月1日現在)。 2001(平成13)189万7,730人(3月1日現在)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | インド南部、タミルナドゥ州(Tamil Nadu State)の州都・港湾都市。
北緯13.09°、東経80.27°の地。 近郊にカルパッカム原子力発電所(Kalpakkam nuclear power plant)がある。 旧称は「マドラス(Madras)」。〈人口〉 1971(昭和46)247万人。 1981(昭和56)327万6,000人。 1991(平成 3)379万5,028人/1991(平成 3)385万7,500人。 2001(平成13)421万6,300人。 2003(平成15)438万2,100人。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | インド南部、タミルナドゥ州(Tamil Nadu State)中央部の商業都市。
州都チェンナイ(Chennai)(旧称マドラス)に鉄道が通じ、茶・綿花などの集散地。 「サーレム」,「セーレム」とも呼ぶ。〈人口〉 1970(昭和45)30万2,935人。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | インド南部、デカン高原南部のカルナータカ州(Karnataka State)の州都。
工業都市で、航空機製造・精密機械工業が発達。インドのシリコンバレーとも呼ばれる。 旧称は「バンガロール(Bangalore)」,「バンガロア」。がろはかいとう(バンガロ破壊筒)〈人口〉 1970(昭和45)104万1,900人。 1971(昭和46)154万人。 1981(昭和56)262万8,000人。 1991(平成 3)265万0,659人。 |
| 言葉 | (1)ポンディシェリー連邦政府直轄地 | 詳しく調べる |
|---|---|
| 意味 | インド南部にある連邦政府直轄地。
行政所在地はポンディシェリー。 タミルナドゥ州(Tamil Nadu State)内のポンディシェリーとカライカル(Karaikal)、アンドラ・プラデシュ州(Andhra Pra-desh State)内のヤナム(Yanam)、ケララ州(Kerala State)内のマエ(Mahe)で構成。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | インド東部、アッサム地方アルナーチャル・プラデシュ州(Arunachal Pradesh State)の州都。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | エジプト中東部、ケナ県(Muhafazat Qina)中南部にある村。
ナイル川中流域の東岸、ルクソル(Luxor)の北方に位置する。 古代エジプトの遺跡のカルナック神殿([英]Karnak Temple)がある。 |
姉妹サイト紹介
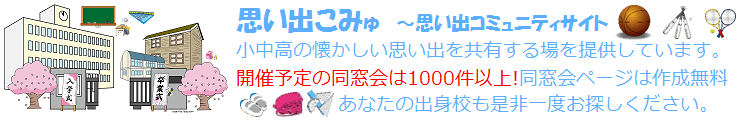
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ギリシア中部のパルナソス南麓にあった古代都市・聖地。
アポロ(Apollo)の神託で有名な神殿があった。 「デルフィ」とも呼ぶ。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ギリシア系のキプロス共和国東部の地区。
行政所在地はラルナカ。〈面積〉 1,129平方キロメートル。〈人口〉 1992(平成 4)10万0,242人(12月15日現在)。 2001(平成13)11万5,268人(10月1日現在)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | スイス中南部ベルン(Bern)南東方にある、アルプス山脈の主脈ベルナー・アルプス(Berner Aplen)の高峰。標高4,158メートル。
美しい山容で知られ山腹は氷河におおわれている。 南西にアレッチュ氷河(Aletschfirn)が流れ、北東にメンヒ山(Muench-Berg)・アイガー山(Berg Eiger)が相接する。 登山電車ユングフラウ鉄道(Jungfrau Railways)が中腹ユングフラウヨッホ(Jungfraujoch)(3,475メートル)まで通じ、ここに高山研究所・気象観測所がある。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | スイス南西部、バレ州(Valais canton)南西部の町。
グラン・サンベルナール峠(Great Saint Bernard Pass)にある。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | スウェーデン中南西部の県。北西部をノルウェーに隣接。
県都はファルン(Falun)。 中央部にシリアン湖(Siljan sjo)がある。 「ダーラルナ県」とも呼ぶ。〈面積〉 2万8,195.6平方キロメートル。〈人口〉 1990(平成 2)28万8,919人。 2000(平成12)27万8,231人(12月31日現在)。 2003(平成15)27万6,520人(推計)。 2004(平成16)27万6,042人(12月31日現在)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | スペインの画家(1904~1989)。カタルニアのフィゲラス生れ。
1921(大正10)サン・フェルナンド王立美術アカデミーに入学。 1926(大正15)アカデミーを退学させられる。 1940~1948(昭和15~昭和23)渡米。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | スペイン王カルロス一世・神聖ローマ皇帝(1500~1558)。スペイン王在位:1516~1556、神聖ローマ皇帝在位:1519~1556。
ハプスブルク家オーストリア大公フィリップ(端麗王)と母ファーニアの子で、外祖父アンゴラ王フェルナンド二世を継いでスペイン国王カルロス一世(Carlos I)となり、祖父ハプスブルク家マクシミリアン一世の死後、神聖ローマ皇帝カール五世を兼ね、スペイン・オーストリア・ドイツ・ネーデルラントにまたがるハプスブルク王国を形成し、スペイン王として新大陸アメリカまで広大な植民地を支配。 ルターの宗教改革にローマ教皇と結び、1521年ウォルムス帝国議会(Reichstag zu Worms)にルター(Martin Luther)を召喚し、ルター派を禁止。 1521~1544年、五世の強大化を恐れたフランス王フランソワ一世(Francois I)と北イタリアを争奪(イタリア戦争)。カンブレー条約でフランスを締め出し、1527年ローマを略奪。 この間、オスマン帝国スレイマン一世のオーストリア侵入などのためにプロテスタント諸侯の協力を得るため、1526年ルター派の布教を許可するが、オスマン帝国の第一次ウィーン包囲を撃退した後、再び1529年禁止して諸侯の反抗を招く。1546~1547年シュマルカルデン同盟を破砕したが、1555年アウクスブルクの宗教和議でルター派の新教承認を余儀なくされる。 翌年、ドイツ帝位を弟フェルディナント一世に、スペイン王位を子フェリペ二世に譲り、退位。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | チェコ共和国の補助貨幣単位。
100ハレル=1コルナ(koruna)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | トルコ南東端の県。北部をワン県(Van Ili)、西部をシルナク県(Sirnak Ili)に接し、東部はイラン、南部はイラクに隣接。
県都はハッカリ。〈面積〉 7,121平方キロメートル。〈人口〉 1990(平成 2)17万2,500人。 2000(平成12)23万5,800人。 2004(平成16)26万0,900人。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | トルコ南東部、シルナク県(Sirnak Ili)東部にあるイラク国境近くの町。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | トルコ南東部の県。北部をシイルト県(Siirt Ili)、北東部をワン県(Van Ili)、東部をハッカリ県(Hakkari Ili)に接し、南部をイラク、南西部をシリアに隣接。
県都はシルナク。 少数民族クルド人が居住。 「シュルナック県」とも呼ぶ。〈面積〉 7,172平方キロメートル。〈人口〉 1990(平成 2)26万2,000人。 2000(平成12)35万4,100人。 2004(平成16)39万1,700人。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | トルコ東端の県。北部をアール県(Agri Ili)、南部をハッカリ県(Hakkari Ili)、南西部をシルナク県(Sirnak Ili)・シイルト県(Siirt Ili)、西部をビトリス県(Bitlis Ili)に接し、東部をイランに隣接。
県都はワン。 「バン県」,「ヴァン県」とも呼ぶ。〈面積〉 1万9,069平方キロメートル。〈人口〉 1990(平成 2)63万7,400人。 2000(平成12)87万7,500人。 2004(平成16)97万0,800人。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ナデシコ目(Caryophyllales)ザクロソウ科(Aizoaceae)ツルナ属(Tetragonia)の多年草。
日本全土・中国・東南アジア・オーストラリア・南アメリカに分布。海岸の砂地に自生し、茎はややつる性(蔓性)で半ば地上を這(ハ)う。茎・葉とも多肉質で、葉は長さ50センチ前後の三角状卵形で互生する。春から秋にかけ、葉腋に小花を1~2個つけ、花弁はなく外面は緑色・内面は黄色。 新芽・葉は食用になり、野菜としても栽培され、浸し物や汁の実に使う。 「浜萵苣(ハマヂシャ)」,「浜菜(ハマナ)」とも呼ぶ。漢名は「蕃杏」。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ネパール中西部の地方。南部をルンビニ地方(Lumbini Zone)、西部をラプティ地方(Rapti Zone)、北西部をカルナリ地方(Kar-nali Zone)に接し、北東部を中国に隣接。
行政所在地はバグルン(Baglung)。〈地区(郡)〉 ムスタン地区(Mustang District)。 ミャグディ地区(Myagdi District)。 バグルン地区(Baglung District)。 パルバット地区(Parbat District)。〈面積〉 8,148平方キロメートル。〈人口〉 2004(平成16)70万9,300人。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ネパール北西部、カルナリ地方(Karnali Zone)中南部の地区。
行政所在地はジュムラ。 「ジュムラ郡」とも呼ぶ。〈面積〉 2,531平方キロメートル。〈人口〉 2001(平成13)8万9,400人。 2004(平成16)9万5,400人。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ネパール西部の地方。北部をカルナリ地方(Karnali Zone)、ラプティ地方(Rapti Zone)、西部をセティ地方(Seti Zone)に接し、南部をインドに隣接。
行政所在地はバンケ地区のネパールガンジ(Nepalganj)。〈地区(郡)〉 ダイレク地区(Dailekh District)。 ジャジャルコット地区(Jajarkot District)。 スルケット地区(Surkhet District)。 バルディア地区(Bardiya District)。 バンケ地区(Banke District)。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | ハンガリー南部、トルナ県(Tolna megye)北東部の都市。
北緯46.62°、東経18.86°の地。 パクシュ原発(Paks Nuclear Power Plant)がある。〈人口〉 1985(昭和60)2万4,276人(推計)。 1990(平成 2)2万0,274人(推計)。 2001(平成13)2万0,954人。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | バングラデシュ南西部、クルナ州(Khulna Division)中央部にあるバゲラット県の県都。
北緯22.66°、東経89.80°の地。 「クールナ」とも呼ぶ。〈人口〉 1991(平成 3)4万4,500人。 2002(平成14)5万8,400人。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | バングラデシュ南西部、クルナ州(Khulna Division)西端にあるサトキラ県の県都。
北緯22.71°、東経89.08°の地。〈人口〉 1991(平成 3) 7万3,100人。 2002(平成14)10万2,700人。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | バングラデシュ南西部、クルナ州の州都・クルナ県の県都。
北緯22.84°、東経89.56°の地。 「クールナ」とも呼ぶ。〈人口〉 1991(平成 3) 92万1,400人/54万5,849人(推計)。 2002(平成14)119万0,000人。 |
| 言葉 | |
|---|---|
| 意味 | バングラデシュ南西部の州。ガンジス川下流のデルタ地帯。
州都はクルナ。 「クールナ州」とも呼ぶ。 |
| 1件目から30件目を表示 | 次の30件 > |