"四"がつく3文字の言葉
"四"がつく3文字の言葉の一覧を表示しています。 検索結果が多い場合は文字数で絞ることが可能です。 文字数は検索結果となる文字の文字数のボタンを押してください。| 31件目から60件目を表示 | < 前の30件 | | | 次の30件 > |
| 言葉 | 四十万 |
|---|---|
| 読み | しじま |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ | 駅 |
(1)石川県金沢市にある北陸鉄道石川線の駅名。
| 言葉 | 四十路 |
|---|---|
| 読み | よそじ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 四十雀 |
|---|---|
| 読み | しじゅうから |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 四半分 |
|---|---|
| 読み | しはんぶん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 四半敷 |
|---|---|
| 読み | しはんじき |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)石敷(イシジキ)の敷き方の一種。
正方形の敷石・敷瓦(シキガワラ)・レンガ・タイルなどを、石敷の縁(フチ)に対して目地(メジ)が四五度になるように斜めにする敷き方。また、敷いたもの。
| 言葉 | 四半期 |
|---|---|
| 読み | しはんき |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 四半石 |
|---|---|
| 読み | しはんせき |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)四半敷(シハンジキ)に敷きつめた石。
| 言葉 | 四合院 |
|---|---|
| 読み | しごういん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)中国北方の民家の伝統的な建設様式。建物が中庭の四方をとり囲む形式。原則として左右対称。
中庭は「院子(yuanzi)」と呼ばれ、奥(北側)には母屋の「正房(zhengfang)(上房
四合院と四合院の間には「胡同(hutong)」と呼ばれる狭い路地がある。
「四合房(sihefang)」とも呼ぶ。
| 言葉 | 四大洲 |
|---|---|
| 読み | しだいしゅう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)古代のインドの世界観・宇宙観。須弥山(シュミセン)を中心とし、その東西南北にある四つの島(大陸・世界)の総称。
金輪王(コンリンオウ)がすべてを治める。
<1>東勝身洲(トウショウシンシュウ)(Purvavideha)は半円形。
<2>南贍部洲(ナンセンブシュウ)(Jambu-dvipa)は台形。「閻浮提(エンブダイ)」とも呼び、人間の住んでいる洲。
<3>西牛貨洲(サイゴケシュウ)(Apara-godaniya)は円形。
<4>北倶盧洲(ホックルシュウ)(uttara-kuru)は方形。「鬱単越(ウツタンオツ)」とも呼び、四大洲のうち最も勝れたところとされる。
「四洲(シシュウ)」,「四天下(シテンゲ)」とも呼ぶ。
| 言葉 | 四大節 |
|---|---|
| 読み | しだいせつ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)旧制の四大祝祭日、四方拝(シホウハイ)・紀元節・天長節・明治節。
1927.11. 3(昭和 2)が最初の明治節で、それまでは三大節と呼ばれていた。
現在、四方拝は元旦( 1. 1)、紀元節は建国記念の日( 2.11)、天長節は天皇誕生日、明治節は文化の日(11. 3)に改められている。
| 言葉 | 四大観 |
|---|---|
| 読み | しだいかん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)日本三景の一つである、宮城県中部の松島湾の代表的な4つの景観。
| 言葉 | 四天王 |
|---|---|
| 読み | してんのう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)仏法を守護するインドの四柱の神の総称。
帝釈天(タイシャクテン)の家来で、須弥山(シュミセン)に住み、四方を守る、持国天(東方を守護)・増長天(南方を守護)・広目天(西方を守護)・多聞天(タモンテン)(北方を守護)の4神。
(2)家来(ケライ)や門下など、ある方面で特にすぐれている4人の総称。〈源頼光の四天王〉 渡辺綱(ワタナベノツナ)・坂田公時(サカタノキントキ)・碓井貞光(ウスイ・サダミツ)・卜部季武(ウラベノスエタケ)。〈藤原道長の四天王〉 平維衡(コレヒラ)・平致頼・源頼信(ヨリノブ)・藤原保昌(ヤスマサ)。〈木曾義仲の四天王(木曾四天王)〉 今井四郎兼平(カネヒラ)・樋口次郎兼光・根井行親・楯六郎親忠。〈徳川家康の四天王〉 本多忠勝(タダカツ)・酒井忠次(タダツグ)・榊原康政(ヤスマサ)・井伊直政(ナオマサ)。〈悪謀之四天王〉 梅田雲浜(ウンピン)・頼三樹三郎(ライ・ミキサブロウ)・池内大学・梁川星巌(ヤナガワ・セイガン)。〈講道館の四天王〉 富田常次郎(ツネジロウ)・西郷四郎・横山作次郎・山下義韶(ヨシアキ)。〈狩野探幽(タンユウ)門下の四天王〉 久隅守景(クスミ・モリカゲ)・桃田柳栄(リュウエイ)・鶴沢探山(タンザン)・神足常雲。〈尾崎紅葉の四天王〉 柳川春葉(ヤナガワ・シュンヨウ)ら。〈歌謡界(作詞家)の四天王〉 中山晋平(シンペイ)・大村能章(ノウショウ)・江口夜詩(ヨシ)・古賀政男。〈安倍派(安倍晋太郎)四天王〉 塩川正十郎・森喜朗・加藤六月・三塚博。
| 言葉 | 四川省 |
|---|---|
| 読み | しせんしょう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)中国南西部の省。北部を甘粛省(Gansu Sheng)(カンシュクショウ)、北東部を陝西省(Shangxi Sheng)(センセイショウ)、東部を重慶市(Chongqing Shi)(ジュウケイシ)に接する。
省都は成都市(Chengdu Shi)(セイトシ)。
| 言葉 | 四徴候 |
|---|---|
| 読み | よんちょうこう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 四念処 |
|---|---|
| 読み | しねんじょ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)悟りを得るための身念処・受念処・心念処・法念処の、四種の観法(修行法)の総称。
世間の実相は無浄(不浄)・無楽(苦)・無常・無我であるのに浄・楽・常・我と誤る四顛倒(シテンドウ)を打破するもの。
「四念処観」,「四念住(シネンジュウ)」とも呼ぶ。
| 言葉 | 四念處 |
|---|---|
| 読み | しねんじょ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)悟りを得るための身念処・受念処・心念処・法念処の、四種の観法(修行法)の総称。
世間の実相は無浄(不浄)・無楽(苦)・無常・無我であるのに浄・楽・常・我と誤る四顛倒(シテンドウ)を打破するもの。
「四念処観」,「四念住(シネンジュウ)」とも呼ぶ。
| 言葉 | 四拍子 |
|---|---|
| 読み | よんびょうし |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
姉妹サイト紹介

| 言葉 | 四方拝 |
|---|---|
| 読み | しほうはい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)旧制の四大節(シダイセツ)・三大節の一つ。四方拝式の略。 1月1日寅(トラ)の刻(現在は午前5時)、宮中の清涼殿の東庭(現在は神嘉殿<シンカデン>)において天皇が、天地四方の神霊および皇大神宮・御陵などを遥拝(ヨウハイ)し、災いを払い五穀豊穣・天下泰平を祈る儀式。国民は祝日として祝った。
| 言葉 | 四方柾 |
|---|---|
| 読み | しほうまさ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)角材の四面に柾目(マサメ)が表れたもの。
木材の角を樹皮側に、その対角を幹の中心(芯)側にして製材(木取り)したもの。一辺一尺の角材では径約三尺(*)以上の原木が必要で、無駄になる部分は多いが、上等の柱材になる。
床柱などに用いる。(*)一尺の対角線はルート2倍(1.414)で、芯を避けることからその倍(2.828)となる。
| 言葉 | 四方津 |
|---|---|
| 読み | しおつ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ | 駅 |
(1)山梨県上野原市にあるJP東日本中央本線の駅名。
| 言葉 | 四日市 |
|---|---|
| 読み | よっかいち |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ | 駅 |
(1)三重県四日市市にあるJP東海関西本線の駅名。
| 言葉 | 四旬節 |
|---|---|
| 読み | しじゅんせつ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)キリスト教で、復活祭の前日(Easter Eve)までの日曜日をのぞく40日間(日曜日の六主日を除く)の斎戒期。復活祭を迎える精神的な準備期間。
キリストが荒野で断食・修行した40日間に因(チナ)み、節食や断食、懺悔(ザンゲ)が行われる。
初日は「聖灰水曜日(Ash Wednesday)」,「灰の水曜日」と呼び、懺悔の象徴として頭に灰を振りかける。
期間中の第1日曜日は「クアドラジェシマ(Quadragesima)」,「クァドラジェシマ」,「クワドラジェシマ」と呼ぶ。
期間中の第5日曜日は「受難の主日(Passion Sunday)」,「シュロの主日(Palm Sunday)」,「枝の主日」と呼ぶ。
最後の週は「聖週間(Holy Week)」,「聖週」,「受難週(Passion Week)」と呼ぶ。
復活祭前の木曜日は「聖木曜日(Holy Thursday)」,「洗足木曜日(Maundy Thursday)」と呼ぶ。
翌日の金曜日は「受難日(Good Friday)」,「聖金曜日」と呼ぶ。
「四旬祭」,「大斎節(タイサイセツ)」,「受難節」,「かなしみのせつ(悲の節,悲しみの節)」,「レント」とも呼ぶ。くようび(聖木曜日)(1)
| 言葉 | 四明公 |
|---|---|
| 読み | しめいこう |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)(『真誥(シンコウ)』闡幽微)四方の鬼を主領する東明公・西明公・南明公・北明公の総称。
| 言葉 | 四明山 |
|---|---|
| 読み | しめいざん |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 四明岳 |
|---|---|
| 読み | しめいがたけ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
| 言葉 | 四条畷 |
|---|---|
| 読み | しじょうなわて |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ | 駅 |
(1)大阪府大東市にあるJP西日本片町線の駅名。
| 言葉 | 四枚肩 |
|---|---|
| 読み | しまいがた |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)普通は駕籠(カゴ)一挺(イッチョウ)に舁(カ)き手が二人のところを、四人が交代で舁くこと。
「よまいがた(四枚肩)」とも呼ぶ。
姉妹サイト紹介
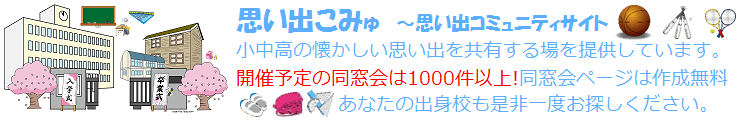
| 言葉 | 四無畏 |
|---|---|
| 読み | しむい |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)無畏とは「畏(オソ)れはばかることなく説法する仏の境地」で、以下の四つの要素があるとされる。
<1>総持不忘(ソウジフモウ):自分が聞いた総(ス)べての教えをしっかりと記憶して忘れないこと。
<2>尽知法薬(ジンチホウヤク):医者が患者の病気の種類や症状の軽重に応じて薬の処方を変えるように、衆生(シュジョウ)の機根(キコン)・欲望・性質・心の持ち方に適応した教えの処方を知り尽(ツク)くしていること。
<3>善能問答(ゼンノウモンドウ):「善(ヨ)く」とはその場限りのごまかしではない真理に従ったということ、「能(ヨ)く」とは相手の能力にあわせてということで、質問や反駁(ハンバク)に答える態度。
<4>能断物疑(ノウダンモツギ):いろいろ異なる解釈や疑問を、慈悲に徹(テッ)することで断案(ダンアン)をくだすこと。
「菩薩(ボサツ)の四無畏」,「仏(ホトケ)の四無畏」とも呼ばれる。
| 言葉 | 四無碍 |
|---|---|
| 読み | しむげ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)菩薩(ボサツ)や仏(ホトケ)が実現する、四つの自在な能力。
「四無礙解(ゲゲ)」,「四無碍解(ゲゲ)」,「四無礙弁(ゲベン)」,「四無碍弁(ゲベン)」,「四無礙智(ゲチ)」,「四無碍智(ゲチ)」,「四無」,「四弁」とも呼ぶ。
| 言葉 | 四無礙 |
|---|---|
| 読み | しむげ |
| 品詞 | 名詞 |
| カテゴリ |
(1)菩薩(ボサツ)や仏(ホトケ)が実現する、四つの自在な能力。
「四無礙解(ゲゲ)」,「四無碍解(ゲゲ)」,「四無礙弁(ゲベン)」,「四無碍弁(ゲベン)」,「四無礙智(ゲチ)」,「四無碍智(ゲチ)」,「四無」,「四弁」とも呼ぶ。
| 31件目から60件目を表示 | < 前の30件 | | | 次の30件 > |